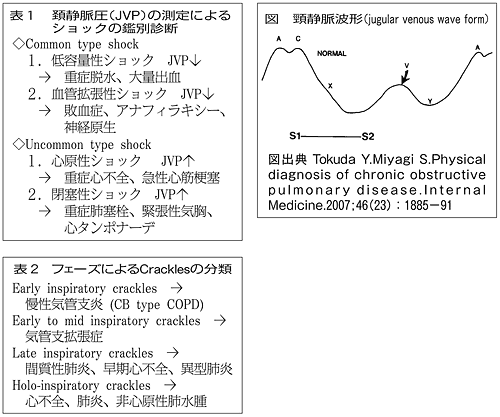医科2010.11.15 講演
アドバンスド身体診察 [診内研より]
筑波大学水戸地域医療教育センター総合診療科 徳田 安春先生講演
血圧計を用いない動脈圧の推定法
検者の両側の2~4指で、患者の片側腕の上腕動脈と橈骨動脈を同時に触診し、上腕動脈に圧迫を加えて、橈骨動脈の脈が消失するかどうかを診る。
軽度の圧迫で脈が消失した場合には収縮期圧はおよそ80mmHg、中等度の圧迫で脈が消失した場合には収縮期圧はおよそ100mmHg、強い圧迫で脈が消失した場合には収縮期圧はおよそ120mmHgである(Jules Constant著:Bedside Cardiologyより改変)。
ショックの定義と鑑別診断
ショックは、「低血圧+主要臓器循環障害」であり、臨床症状・所見を伴わない低血圧はショックではない。
主要臓器循環障害の主な症候には、脳血流の低下による気分不良・意識障害・けいれんなどがあり、腎血流の低下による乏尿、冠血流の低下による心筋虚血などがある。このうち、「脳血流の低下」による症候が最も早く出現する。頚静脈圧の測定は、ショックの鑑別診断に有用である(表1)。
頚静脈圧 jugular venous pressure(JVP)の測定法
頚静脈圧(内頚静脈圧)は、右心房から内頚静脈の「拍動の頂点」までの垂直距離である。
内頚静脈は皮下を走行しており、直視できない。そのため、皮膚の拍動を確認することによって内頚静脈の拍動を診る。内頚静脈の拍動は2峰性の波形をなす(図)。
右心房から内頚静脈の「拍動の頂点」までの垂直距離は、直接体表から測定することは困難である。そのため通常は、胸骨角から内頚静脈の「拍動の頂点」までの垂直距離をまず測定する。体位(座位の角度)にかかわらず、胸骨角から右心房までの垂直距離は約5㎝であるので、胸骨角から内頚静脈の「拍動の頂点」までの垂直距離を測定したあと5㎝加算し、内頚静脈圧とする。
例えば、胸骨角から内頚静脈の「拍動の頂点」までの垂直距離が2㎝であれば、内頚静脈圧は2+5=7cmH2Oとなる。内頚静脈圧の正常値は3~9cmH2Oである。静脈圧が上昇しているかどうかを診る場合には、まず立位(坐位)で右の鎖骨上を観察して、静脈拍動を確認することから始めてもよいが、静脈圧が低下している場合には、立位(坐位)では拍動を確認できないので、静脈圧は測定できない。
外頚静脈と手背静脈を用いた静脈圧の測定
外頚静脈の観察が容易な患者の場合、外頚静脈を用いた静脈圧の推定を行ってもよい。ただその場合は、正確度が落ちる。なぜなら、外頚静脈は上大静脈に直通しておらず(2回の分岐でつながる)、静脈弁の影響もあり、さらには、内頚静脈より細いからである。
内頚静脈と外頚静脈のいずれも観察が困難な場合には、手背静脈を利用してもよい。まず、手背面を上部に向けたまま手を心臓の高さより低い位置に置く。しばらくすると、手背静脈が怒張してくる。手背面を上部に向けたまま、徐々に手の高さを上げていき、心臓の高さを越えて高くしていくと、急に手背静脈が虚脱するポイントに到達する。そのポイントの高さから、右心房までの垂直距離が静脈圧となる。
心拡大(心肥大)の診方
心尖拍動または心拍動最強点(Point of Maximal Impulse:PMI)は通常、坐位で第5肋間鎖骨中線上(胸骨中線より10㎝以内)にある。心拡大があると最強点は外側・下方に移動する。
心 音
心尖拍動の位置を必ず触診で確認してから、心尖部にベル型聴診器をあてて、その後、心基部へ徐々にずらしながら聴診する。
S1の分裂とS2の分裂に加え、A2の消失、P2の亢進にも注意する。心尖部でP2が聴かれれば、P2は亢進している。過剰心音のS3・S4は低音である。そのため、ゆえに心尖部にベル型で軽くあてて聴取する。S1の分裂とS4の判別が困難な場合、ベル型を強くあてて聴取し、消失すればS4の可能性が高い。S4はまた、触診で触れることが多い。
心雑音
心雑音は心臓内血流の乱流により生じる。心音よりも長く、心周期における雑音のタイミングによって、収縮期雑音、拡張期雑音、連続性雑音に分けられる。
心雑音は強度により6段階に分けられる(Levineの分類)。心周期における雑音のタイミングは、その成因と関連する。
呼吸副雑音
呼吸運動に伴って生じる異常呼吸音を、呼吸副雑音と呼ぶ。断続性と連続性のものがある。断続性呼吸副雑音には、Cracklesがあり、これまではFine crackles(soft & high-pitch)とCoarse crackles(loud & low-pitch)に分けられていた。
最近の研究により、聴取されるフェーズによって、成因を推定できることがわかった(表2)。
連続性の呼吸副雑音にはWheezing(下気道狭窄)やStridor(上気道狭窄)、Rhonchi(気道分泌亢進)がある。Rhonchiが触診できるときRattlingと呼び、気道分泌の過剰亢進(重症の畜痰)を意味する。
肝脾腫
肝臓の腫大は触診、打診、聴診(スクラッチテスト)を組み合わせて診る。肝臓の下縁を触診できても肝臓の位置が下方へ移動しているだけのことがある(COPDなど)。
必ず、肝臓のサイズ(右鎖骨中線で打診上6~12㎝が正常)も確認する。脾臓の腫大も触診や打診を組み合わせて診る。左前腋窩線上の最下肋間を打診し、吸気時に濁音dullnessを確認したときはsplenic percussion sign陽性とし、脾腫の可能性を示唆するが、特異度は高くないのでエコーなどと合わせて評価する。
胸水と腹水
胸水の評価では、打診上の完全濁音complete dullnessと触覚振盪音tactile vocal fremitusを診る。触覚振盪音は、患者に大きな声で「ひと~つ」と言わせて、両手で振盪音の左右差を比較する。
腹水の評価では、側腹部の濁音flank dullness、体位による濁音境界線の移動shifting dullness、打診によるfluid waveの確認などを診る。
浮 腫
浮腫の鑑別ではまず、pitting edemaかnon-pitting edemaかを判別する。non-pitting edemaの場合、リンパ浮腫(術後や放射線療法後、フィラリアなどによる)や粘液水腫(甲状腺機能異常による)、脂肪性浮腫lipedemaのことが多い。
Lipedemaは女性のみに認められる脂肪の異常蓄積であり、足関節より末梢には脂肪の沈着はなく腫脹しない。pitting edemaでは、Pit recovery timeの測定を行う。すなわち、浮腫部分を指でpitさせ、pitが元に戻る時間を腕時計などで測定する。40秒以内で戻る「早い浮腫fast edema」は低蛋白血症(低アルブミン血症)を伴う浮腫のことが多い。
聴打診の有用性
胸水、頭部硬膜下血腫、大腿骨頚部骨折の診断に聴打診auscultatory percussionが利用できる。大腿骨頚部骨折疑いでは、聴診器の膜型を恥骨結合上に固定して聴診しながら、膝蓋骨を指で軽くタップし、左右差を聴き分ける。