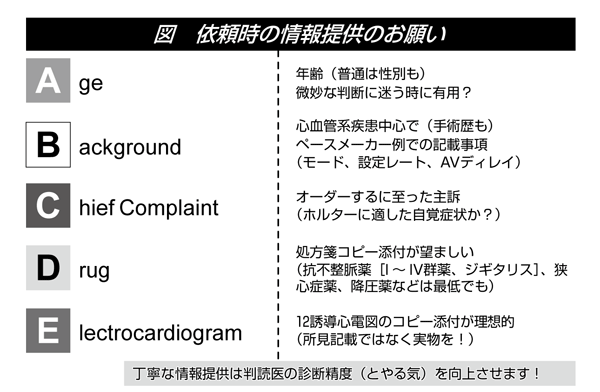医科2013.02.23 講演
秘伝!診療に生かすホルター心電図 [診内研より]
東京大学大学院医学系研究科・循環器内科 杉山 裕章先生講演
ホルター心電図は、現代の診療では欠かせない診断検査となっている。比較的安価でもあり(保険点数:1,500点)、国内主要施設だけでも年間80万件以上施行されている。通常、依頼医側が自身で解析まで行うケースは少なく、循環器専門医により作成された判読レポートを受け取るスタイルが大半と思われる。すなわち、実地医家にはホルター心電図の正しい適応決定や、結果を受けての臨床判断が求められているといえる。
1.基本事項のおさらい
近年では、ホルター心電計の軽量化(100g未満)が進み、記録中にシャワーや入浴なども可能な耐水性のものも、標準的になりつつある。基準電極を含めて、前胸腹部に計五つの電極を装着し、NASAおよびCM5の二つの誘導の24時間モニタリングとして実施されることが多い(順にV1誘導、V5誘導類似の心電図波形が得られると考えれば良い)。
ホルター心電図は、日常生活下の各時刻における行動や自覚症状と、心電図波形とを対比させるイベント心電計であり、内蔵時計の調整および患者への行動記録カードの記載方法説明などを、事前に正しく行っておく必要がある。
記録終了後、臨床検査技師ないし専門解析センターでの初期解析を経て冊子化され、心拍数、期外収縮や徐脈性・頻脈性不整脈、ST変化に関する専門医による判読レポートとともに返却されてくる。
なお、依頼医側は判読医に対して、依頼書として適切な診療情報提供を行うのが望ましく、そのためのポイントをまとめた(図)。
以上が、一般的な外来診療におけるホルター心電図の流れである。
2.動悸精査時のワンポイント
動悸を訴え受診する患者は多く、欧米から診療ガイドラインも公表されている。動悸の原因として、頻脈性不整脈を中心とする心原性要因が約4割を占め最多である。
しかし一方で、約3割は不安や精神疾患に関連しており、不整脈疑いの患者において症状出現時の約3分の2は洞調律が記録されるという報告もあり、動悸が主観的な訴えであることも認識しておくべきである。
ホルター心電図を用いて動悸診断を行う場合、症状記載前後、ないしイベントボタン操作直前の心電図所見との比較を行うのが基本スタイルである。ホルター心電図を用いた動悸精査の対象の多くが、発作的に生じる不整脈イベント(特に頻脈性)であるため、約24時間と限定された記録時間内に当該イベントが出現しなかった場合には診断的意義に乏しく、その診断感度は35%程度と決して高くない。
そのため、患者の年齢・性別、心疾患の既往、12誘導心電図異常や動悸持続時間(5分以上持続するか)などを考慮した問診が肝要である。また、対象イベントの頻度を意識する必要もあり、1週間に1回程度以上生じるイベントでない場合には、単回のホルター心電図で原因特定に至るのは困難とされている。
病的不整脈が見つかった場合の個別の対応については、紙幅の関係もあるため述べないが、成書やガイドラインの参照や専門医コンサルテーションなどが可能である。むしろ、適切な症例を選択してオーダーする判断力の重要性が高く、やみくもな動悸精査のホルター心電図が有用性を発揮するケースは、きわめて少ないことを再認識すべきである。
3.冠動脈疾患に対する基本認識
安静時12誘導心電図では、T-Pライン(1拍前のT波と注目心拍のP波とを結ぶ線)に対してSTレベル計測が行われるのが一般的であるが、日常生活動作の中で記録されるホルター心電図では、体動などによる基線動揺が問題となり、かわりにPR部分がST計測の基準として用いられる。
ホルター心電図では、同基準点に対し、J点近傍に設定された計測点での電位計測値がSTレベルとして全心拍ごとにストアされており、STトレンドグラムやスーパーインポーズ波形として視認・理解しやすい形で表出するものまであり重宝する。
実際の解析では、CM5誘導(時にCC5誘導)を中心にこれらの情報に加えて心拍数増減の有無や完成・回復のタイミングや所要時間、ST変化の形状(低下の場合には水平ないし下行型が虚血性ST変化に特徴的)などを参考に、虚血性ST変化か否かを判定する。
胸痛精査ないし虚血性ST変化の検出も、主なホルター心電図の依頼理由の一つであり、自験例のうち20〜25%が該当した。もちろん、典型的な労作性狭心症に伴う虚血性ST変化が記録中にドキュメントされることはあるものの、欧米および本邦(日本循環器学会)のガイドラインにて、運動可能な胸痛患者における初期評価としてのホルター心電図の適応はクラスⅢとされていることは意外と知られていない。
これは、ホルター心電図の心筋虚血に対する感度、特異度がともに約60%と十分でないためである。その原因として、検査中に行われる日常生活動作では心負荷が軽く(特に都市型生活)、デマンド・イスケミアが誘発されにくいため、冠動脈疾患を有することが判明している患者でも通常の24時間記録では3分の1以上の心筋虚血イベントを見逃してしまうとされる。
また、体動や呼吸、体位変換などによるST変化と虚血性変化の鑑別も時に難しく、さらにはジギタリス薬などの服用や既存のST-T変化(左室肥大、脚ブロック、非特異的ST-T変化など)が強い場合には、基本的に虚血性変化が判定できないなどの"弱点"もある。加えて、比較的影響は少ないとされるが、12誘導を利用する運動負荷心電図に比べて、少ない誘導数の影響もないわけではない。
したがって、一般診療における冠動脈疾患の診断検査としては、運動負荷心電図に一日の長があり、偽陽性や偽陰性が多いホルター心電図はその代替とはならないと認識しておくべきである。
設備や人材面でトレッドミル検査は困難としても、マスター階段試験は簡易的な装置で施行可能であるため、有効活用したい。後者は一定の危険性のある検査ではあるが、禁忌や判定法に加えて、基本的な緊急対応(提携医療機関への搬送含む)さえおさえておけば、ワシントン・マニュアルでも強調されている的確な問診と組み合わせることで、クリニック・診療所レベルでも安全かつ有効な冠動脈疾患の診療が可能である。
筆者は、ホルター心電図で"お茶を濁す"的なオーダーは、決して低くない偽陽性や偽陰性に翻弄されるだけなので、ホルター心電図におけるST評価はオマケ程度と重要視しない方が無難と考えている。
ただ、他検査ではとらえにくい異型狭心症(冠攣縮性狭心症)に伴うST変化の検出には、ホルター心電図は比較的優れており、適切なイベント発生頻度であれば有用な診断検査となりうる(クラスⅡa)。
参考文献
1)杉山裕章(監修:永井良三、執筆協力:今井靖、前田恵理子)『個人授業 心電図・不整脈 ホルター心電図でひもとく循環器診療』医学書院、2011
2)杉山裕章『心電図のみかた、考え方[基礎編]』中外医学社、2013(新刊)
杉山裕章(すぎやまひろあき)
2003年東京大学医学部卒。内科初期研修、都内循環器専門病院での研修の後に大学院へ進学し修了。日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本不整脈学会−日本心電学会認定不整脈専門医、医学博士。
※ ご意見・ご質問、各種ご依頼その他はすべてhsugiyama-tky@umin.orgまでお気軽に。