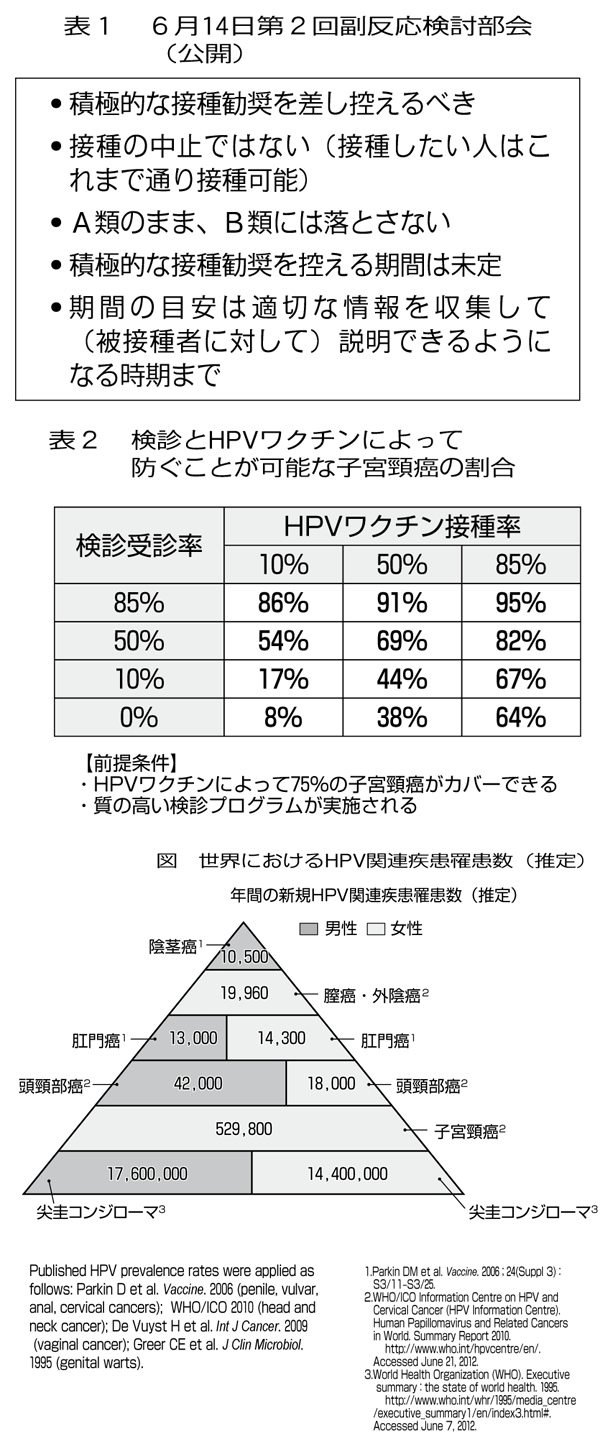医科2013.06.15 講演
かかりつけ医に伝えたい子宮頸癌検診とワクチン接種 [診内研より]
社会保険相模野病院婦人科腫瘍センター長
北里大学医学部客員教授
上坊 敏子先生講演
はじめに
最初に、6月14日厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会における、「HPVワクチン定期接種に関する決定事項」をお知らせします(表1)。産婦人科医として、日ごろから子宮頸癌患者さんが苦しむ姿を目の当たりにし、それを予防することができるHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの認可・定期接種化に助力してまいりました。
今回、HPVワクチン接種に伴う説明のつかない有害事象のために、上記の決定がなされたことは大変残念です。一日も早く通常の定期接種再開が実現できるように情報が収集されること、さらに副反応に悩む方々の早期回復を願っております。
HPV関連疾患
子宮頸癌は、HPVに関連する代表的な癌ですが、頭頸部癌、肛門癌、腟癌、外陰癌、陰茎癌も、HPVと関連がある癌です。さらに、低リスクHPVは尖圭コンジローマの原因になり、図に明らかなように、HPV関連疾患は世界中で多くの男女に発生しています。子宮頸癌は子宮頸部にできる癌で、わが国では年間約9,800人が浸潤癌に、11,000人が上皮内癌に罹患していると報告され(2008年、地域がん登録全国推計値、国立がんセンターがん対策情報センター)、死亡数は年間3,500人と推定されています。
近年のわが国の子宮頸癌罹患の最大の問題点は、若年化が進んでいることです。罹患率は20歳代後半から急上昇し、ピークは30歳代です。子宮頸癌の治療では、後遺症が大きな問題ですが、特に若い女性では妊孕能の喪失が問題になります。若い女性を子宮頸癌から守るために、早急な対策が求められているのが現状だと考えます。
HPVは150以上の型に分類されていますが、発癌に関係するのは15種類程度で、その代表が16型、18型です。HPVは、性交渉により子宮頸部の粘膜上皮に感染します。性交を経験した女性の約8割は、生涯に一度は感染すると言われていますが、多くは自然に消失することも明らかになっています。
しかし、感染者の1割は感染が持続化し、その一部は前癌病変(上皮内腫瘍)を経て、癌に発展します。浸潤癌になるのは、高リスクHPVに感染した女性の0.1%程度で、発癌までには5年以上の時間がかかります。
ワクチンと検診が子宮頸癌撲滅の両輪
子宮頸癌を予防する手段には、一次予防としてはワクチン(感染を予防する)、二次予防としては子宮頸癌検診が考えられます。ワクチンには、2価ワクチン(サーバリックス®)と、4価ワクチン(ガーダシル®)があります。いずれも、16型・18型HPVの持続感染、16型・18型に起因する上皮内腫瘍をほぼ完全に予防することが報告されています。16型・18型は子宮頸癌の70%程度の原因になっていて、特にわが国の若年頸癌では90%から16型・18型が検出されています。16型・18型は他の高リスクHPVより短期間で高位の病変に進行します。
また、細胞診陰性の女性を対象にした検討では、わが国の若い女性からは、中高年女性より高頻度に16型・18型が検出されることも報告されています。セクシャルデビューを果たした女性は、速やかにHPVに感染することも明らかにされています。
以上のような状況から、HPV感染を予防するワクチンは、小学6年生から高校1年生を対象にすることが決められました。さらに、4価ワクチンは、子宮頸癌以外のHPV関連疾患も予防することが知られています。
一方、子宮頸癌検診には、浸潤癌を減少させる効果があります。問題は、わが国の検診受診率が24.5%と、先進各国の80%前後と比較すると非常に低いということです。特に、20歳~30歳代の受診率の低さが問題となっています。
子宮頸癌検診の無料クーポン(20歳から5歳刻みで40歳まで)の発行・啓発活動などで、以前より受診率はやや上昇したものの、厚労省が目標とする50%にはほど遠い現状です。
ワクチンには、HPV16型・18型に起因する頸癌しか予防できないという弱点があります。検診も、精度という問題点があります。そのため、ワクチンと検診が子宮頸癌撲滅の両輪であると考えられています。
表2は、検診とワクチンで予防できる子宮頸癌の頻度を試算したものです。子宮頸癌撲滅のためには、高いワクチン接種率と高い検診受診率が必要であることが分かります。
おわりに
冒頭に述べた、ワクチン接種勧奨中止の結果として、ワクチン接種率の低下が懸念されます。10年後、20年後に各国から子宮頸癌罹患率と死亡率減少の報告が出される中、日本だけが取り残されることのないように、ワクチン接種と検診に対する諸先生方のご尽力をお願いいたします。
最後に、兵庫県保険医協会第486回診療内容向上研究会に講演の機会をいただき、ご関係の諸先生方に感謝いたします(見出しは編集部)