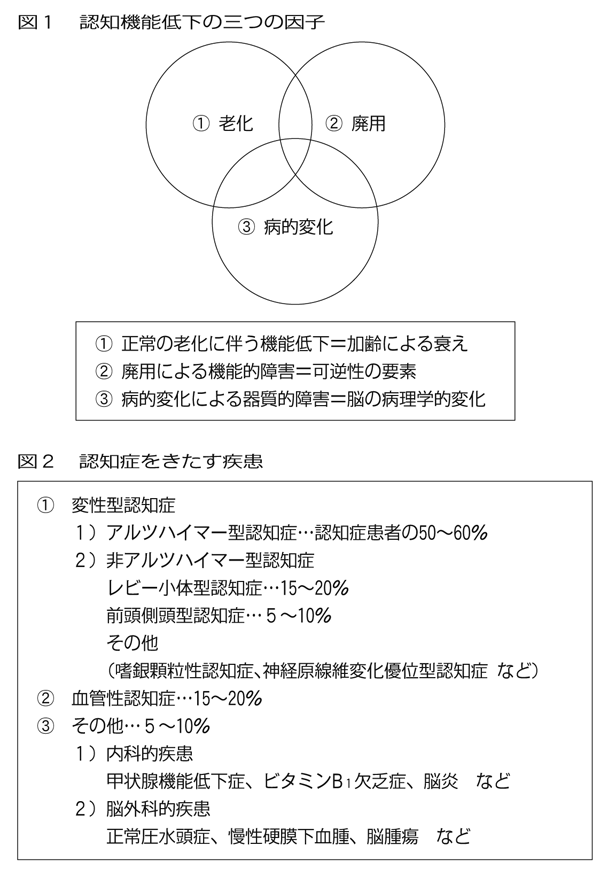医科2014.09.27 講演
[保険診療のてびき] 認知症の理解と多職種連携
西宮市・つちやま内科クリニック 土山 雅人先生講演
1980年代の世界のトップリーダーであったアメリカのレーガン元大統領とイギリスのサッチャー元首相の共通点をご存知ですか? それは2人とも引退後にアルツハイマー型認知症を発症したことです。世界でも最高水準の健康管理を受けていたと思われる人でも患う病気、それが認知症です。日本では2012年の時点で認知症高齢者は462万人、その予備軍である軽度認知障害の方は400万人と推定されており、認知症はまさにcommon diseaseです。さて、認知症の定義にはいくつかありますが、おおむね「一度正常に達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続性に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態(認知症疾患治療ガイドライン、2010)」とされています。これには二つのポイントが含まれています。一つは「後天的な脳の障害」によって認知機能が落ちること、すなわち認知症は特有の脳の病気であること。もう一つは「日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態」、すなわち医療機関での診察だけでは知ることが難しいその人の生活状況の把握が重要であることです。前者は医師による医学的な判断が大切ですが、後者はその人に関わる各職種(訪問看護師、ケアマネジャー、介護スタッフ...)からの情報提供が欠かせません。認知症を正しく評価・診断しようとすれば、その時点からすでに多職種との連携が必須と言えます。
次に注意すべきは、認知機能が落ちる状態(=認知症状態)は認知症という脳の病気(=認知症疾患)以外でも起こるということです。筆者は認知機能の低下は、(1)老化、(2)廃用、(3)病的変化の三つの因子から考えるようにしています(図1)。(1)の老化は、加齢に伴う脳の機能低下ですが個体差が大きく、変化も緩徐で判定が難しい面があります。(2)の廃用は、脳を活用しないことで生じる可逆性の要素を持つ機能的障害ですが、適切な対応がなければ回復困難になることがあります。(3)の病的変化は、脳の病理学的所見による器質的障害であり、より有効な診断、治療、ケアが模索されています。個々のケースでこれらの三つの因子がそれぞれどの程度認知機能の低下に関与しているかを想定しながら、その人に応じた治療やケアを考えることが重要です。
特に(2)の廃用は避けられる脳機能の低下であることを忘れてはいけません。最近では、高齢者において通常の加齢のレベルを超えて心身の働きが低下した状態を「フレイル」(以前は「虚弱」とも呼ばれていました)として捉えるようになっています。フレイルはしかるべき介入によって再び健常な状態に戻る可能性がある病態であるために、高齢者の健康管理を考える際には各職種が理解しておくべき概念です。フレイルには身体的、精神・心理的、社会的側面があると言われていますが、廃用性の脳機能の低下(認知症状態)もフレイルの一側面と捉えて対応を考えることが必要でしょう。
(3)の病的変化は認知症疾患(図2)によってさまざまです。例えば、アルツハイマー型認知症では老人斑(主成分はアミロイドβ蛋白)や神経原線維変化(タウ蛋白)の出現を伴う神経細胞の脱落・消失、レビー小体型認知症ではレビー小体(α−シヌクレイン蛋白)の出現を伴う神経細胞の脱落・消失などが挙げられます。このような変化が脳のどの部位から生じて、どのように広がっていくかにより、その認知症特有の症状が生じます。認知症に関わる各職種が認知症患者さんに対してより適切に対応するためには、このような脳の病的変化について一定のレベルの医学知識を持っておくことも大事でしょう。
認知症では患者さん自身に関わることと同様に家族との関わりも大切です。近年、認知症に関する情報はさまざまなところから得られるようになってきました(情報の中身は玉石混交ですが...)。しかし、いざそれが自分の身内に実際に起こると家族は戸惑ってしまうものです。家族だけで認知症を抱えることはできません。認知症に携わる者にとって、各々の専門職としての知識や経験を生かして、なかなか先の見えない認知症介護の家族を支えていくことも大きな役割の一つと言えます。
認知症に特効薬はありません。認知症における医療の役割は限られています。認知症に関わるということは本人、家族の生活に関わる部分も大きく、個々の家庭に応じた対応が求められます。そのためには正しい医学知識に裏打ちされた認知症の理解と多職種の連携が欠かせません。
(2014年9月27日 北播支部研究会より)