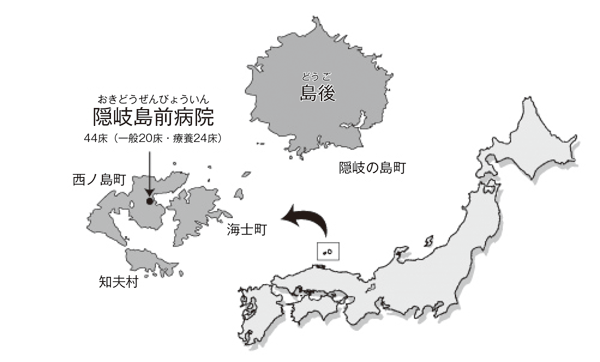医科2015.07.18 講演
「離島医療はおもろいで!」
〜地域医療の仕組みづくりから整形エコーまで〜[診内研より483]
隠岐諸島
隠岐諸島は島根半島の北約40〜70㎞に浮かぶ四つの有人離島と付属の約180の小島からなる。北東側にある大きな島を34歳で院長に
1998年に当時の19床の島前診療所に赴任。外科出身の診療所長、大学派遣の腹部外科医、小児科医、自治医大出身の内科医(私)で構成されていた。島の「なんでも医者」として3年ほど勤務したのちに、2001年に療養型病床を増設し、隠岐島前病院となった。同時に前診療所長が定年となり、まさかの展開で院長を拝命。まだまだ臨床全開でやりたかったこともあり、一度は断ったのだが当時の島根県立中央病院長、町長に詰め寄られ(笑)、「わしらが支えるからやれ!」の一言で決意。看護師は全員年上、人材管理、経営指標の見方など全く分からないまま、院長としての仕事が始まった。
地域医療支援ブロック制・web型電子カルテによる医療情報共有・テレビ会議システム
基本的に大学や県から派遣された医師が1年ごとに交代する以外は、コメディカル、事務は地元採用。医師が1年交代では、5年先のことは誰も分からず、これではいい医療の提供はできない、逆に医師が少しでも長居したくなるような環境作りができればこの地域の医療は必ずよくなると考えた。同じ島にある浦郷診療所、内航船で15分の隣の島にある知夫診療所の医師の勤務を一括管理することとした。診療所長も病院当直に入り、週に2〜3日は当院で勤務することによって検査や外来を受け持ち、逆に当院の医師が両診療所に出かけて診療をするという体制をとった。島の厳しい環境で医師が一人きりにならないようにする。相談やカンファレンスが容易にできる。診療所勤務でも、ある程度手技的な医療行為を行ったり、入院医療に参加したりできる。
また、独りよがりとなりがちな診療所での医療に複数の医師の目が入ることになり、また患者の側からは複数の医師から選ぶことができるようになる。現在は若手医師も3〜5年当院で勤務をするようになっている。
それをサポートするためにweb型電子カルテを採用し島前内の医療機関では医療情報が共有できる仕組みを作っている。島前内の医療機関、本土の後方病院などとテレビ会議システムを構築し、講演会の聴講や合同カンファレンスなどを行うことを可能としている。
処置系外来における超音波診療
大学派遣の小児科医、腹部外科医の撤退に伴って、現在は当院の常勤は内科系総合医6名。非常勤医師により眼科、精神科、整形外科、産婦人科、耳鼻科の外来が行われる。内科兼小児科外来が2診体制、外科外来という名前の処置系外来が1診体制で行われている。この外科外来も内科系総合医によって行われている。処置系外来としての外科外来へ来院する疾病区分としては50%が整形外科、皮膚科・形成外科が30%、外科が5%、以下耳鼻科、眼科疾患とつづく。整形外科医による診察は月に2回で、非整形外科医が運動器疾患を診ざるを得ない状況である。診療の質を少しでも上げるために外科外来診察室に超音波診断装置を設置している。外科外来を受診する約40%の患者に超音波診断装置を利用し、診断、治療を行っている。腰痛症、頸肩腕症候群などの生食筋膜リリース、肩関節周囲炎の滑液胞注射やサイレントマニュピレーション、ガングリオン、肋骨骨折、手根管症候群、ばね指など、ありとあらゆる運動器疾患に及ぶ。ペインクリニックとしての神経ブロック、感染性粉瘤や皮下腫瘤の摘出時の局所麻酔も超音波下で行っている。
国民の多くが煩わされている運動器疾患を誰が診ていくのかという議論はあるが、いずれにしても質の高い処置系外来を行うことが必要とされている。安全でかつ適切な医療の提供のために超音波診断装置は必須の医療機器である。この場合、超音波診断装置は検査の機器ではなく、診療の道具であるため、外来診察室に常に電源を入れた状態で設置することが不可欠である。
終わりに
へき地離島というと、つらくて大変だというイメージが先行する。しかし仕組みづくり、仲間づくり、総合診療医としての技量を上げることで、豊かで楽しく人生を過ごすことのできる場所になると確信している。(7月18日診療内向上研究会より)
図 隠岐諸島