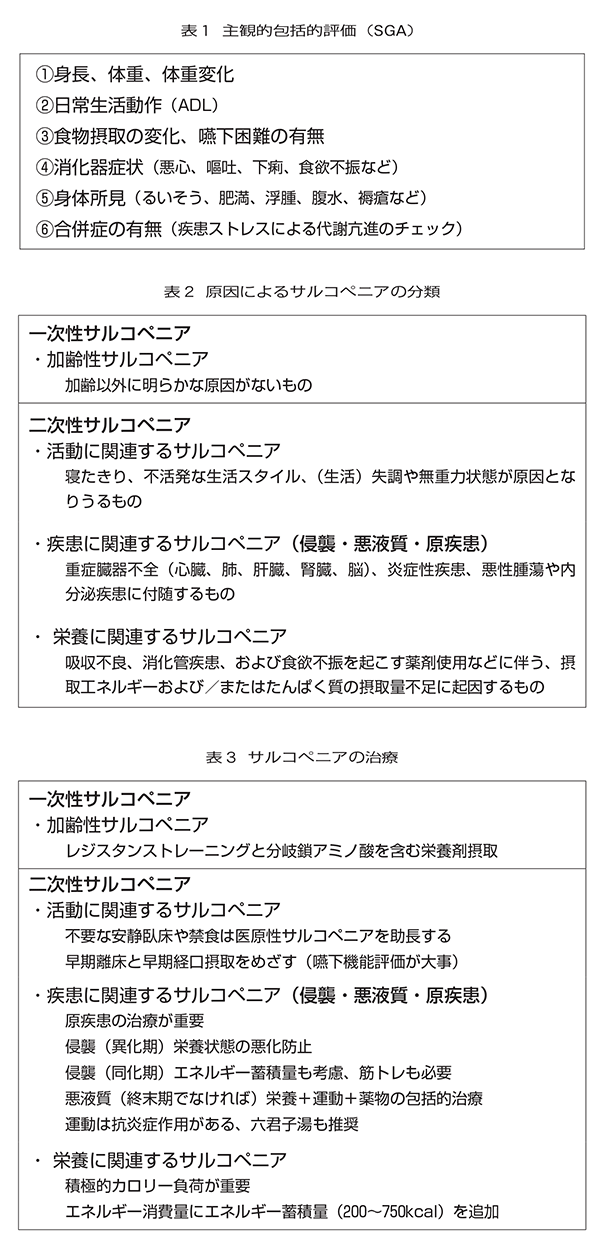医科2015.09.26 講演
[保険診療のてびき] さぁ始めよう"楽しい栄養管理"〜多職種の視点から考える〜
長田区 神戸医療生活協同組合 神戸協同病院 石川 靖二先生講演
【栄養サポートチーム(NST)】医師 石川靖二、管理栄養士 山崎絵里、摂食嚥下障害看護・認定看護師 遠藤 拓、言語聴覚士 齋藤剛、歯科衛生士 秋山初美
栄養管理は重要とはわかっていても"なんとなく漠然としていてとっつきにくい"、そんな印象がありますよね。
在宅医療研究会では、医師、管理栄養士、摂食嚥下障害看護・認定看護師、言語聴覚士、歯科衛生士がそれぞれの立場からの栄養管理について報告させていただきました。
はじめに
チームのモットーは、「フィッシュ哲学」に学んで、「メンバー自らも楽しみ、患者さんに寄り添って、早く元気になってもらいたい」ということです。この哲学の四つの骨子は「遊び心を忘れない」「患者さまを楽しませる」「患者さまに向き合う」「働く時の態度を選ぶ」。とても示唆に富んだ考え方なので、くわしくは成書をお読みください。栄養士の視点から
栄養状態の悪化は、必要エネルギーの不足やたんぱく質の摂取不足から起こります。病院だけではなく、施設や自宅でも起こります。体の中の筋肉が不足した状態のことを「サルコペニア」と呼びます。たんぱく質は、肉・魚・大豆製品・卵などに多く含まれています。自宅でも簡単にできる食事の適切な量の評価として、「手ばかり」という方法があります。サルコペニア予防に必要不可欠なたんぱく質の1食あたりの目安は、手のひらに乗る量です。この量で、おおよそ20g前後のたんぱく質がとれます。
また、個別の疾患によって必要な栄養素も変わってきます。特定の栄養素のみを食事から補うのは困難なこともあるため、その場合は補助栄養の使用も有効です。
看護師の視点から
●NSTにおいての看護師の役割看護師は病棟に常駐しており、入院から退院までの患者の栄養状態、栄養摂取状況に関わっていくため、いち早く患者の問題点を抽出し、また栄養療法の評価をすることができる職種となります。
●栄養障害のスクリーニング
主観的包括的評価(表1)といったツールや嚥下障害テスト(RSST、MWST、FT)などの問診が必須です。これらのスクリーニングでは、問題の有無だけでなく、どこに問題があるのかを考えながら行うことが重要です。
●ベッドサイドでのアセスメントと観察
摂食状況を観察してその人の問題が、食べ物を噛むこと、つまり口に問題があるのか、それとも飲み込みにくさやむせなど喉に問題があるのかをアセスメントし、口に問題があるなら歯科へ、喉に問題があるなら言語聴覚士へ連携をとるのも看護師の重要な仕事です。
医師の視点から
サルコペニアは、栄養を考える上で重要な考え方です。Sarco(筋肉)+penia(減少)が語源のようです。筋肉量と筋力の進行性かつ全身性の減少に特徴づけられる症候群で、身体機能障害、QOLの低下、死のリスクを伴うもの、と定義されます。"筋肉量の低下"が必須項目であり、"筋力の低下"、もしくは"身体能力(運動能力)の低下"の因子を有する場合、サルコペニアと診断されます(表2・3)。予防も含めてサルコペニアの治療は、NSTにとっての最大の課題となります。
言語聴覚士の視点から
言語聴覚士は、ことばや食事のリハビリを専門とします。近年の高齢化に伴い、食事がうまく食べられず、肺炎になる方が増えています。そのうち7割が誤嚥性肺炎といわれており、食べたものが肺に流れ込むことによって起こっています。さまざまな機能が年齢とともに低下しますが、食べる機能も例外ではありません。おいしく、安全に食べるためには、その方にあった食べもの、食べ方を工夫する必要があります。食べることに介助を必要とされている方にとっては、介助の仕方でも大きく変わってきます。まずは肺炎や窒息を予防して、生命を守り、ひとりでも多くの方の食べる喜びを維持するため、われわれ専門職種が発信していく必要があります。
歯科衛生士の視点から
口は、主に食べて飲みこむ働きと、話す働きをします。しかし、単に栄養を取り込むだけではなく、美味しい食事を家族や仲間と味わい楽しむ器官でもあり、口は人間が人間らしく生きていく中で最も重要な部分です。「食べられる口」の環境には、健全な歯・歯肉、口腔周囲筋や舌の機能、潤った口腔内が必要です。口腔ケアを行うことで、肺炎発症減少、嚥下機能向上、低栄養・脱水の予防につながります。また、口腔内の粘膜を刺激(マッサージ)することで唾液分泌が促され、口腔内が潤います。乾燥した口腔内では、しゃべることも食べることも飲み込むことも難しくなります。機能的口腔ケアを行うことで「食べられる口づくり」につなげましょう。
以上、5人の発表の要旨を簡潔にまとめたので、雑ぱくな文章になりました。お許しください。NSTの活動や学習等についてお役に立てることがあれば、当院栄養科、あるいは医局までご連絡ください。
(9月26日 第34回在宅医療研究会より)