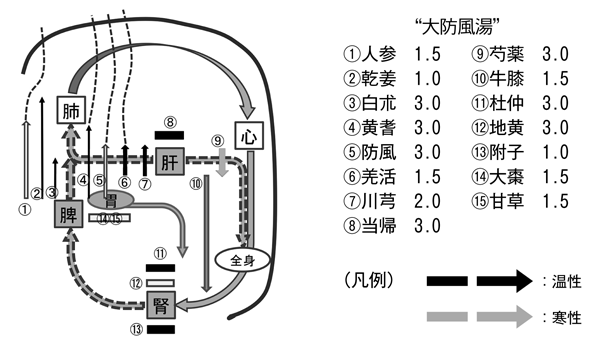医科2020.10.10 講演
[保険診療のてびき]
見える漢方薬(陰陽五行学説)(下)
-新型コロナウイルスの発熱外来の3例-(2020年10月10日)
東大阪市・小阪医院 曹 桂植先生講演
(前号からのつづき)新型コロナウイルス流行期の発熱外来の3例
新型コロナウイルス流行期に発熱を来した患者を3例経験した。緊急事態宣言は2020年4月7日より5月25日まで続いた。患者は発熱を来すと、保健所に電話連絡して、自宅待機し、症状を自己管理(発熱37.5℃以上、4日間、治療せず放置)して、症状の経過によって、PCR検査、入院が指示された。自宅待機中の治療は一切、行われていない。そこで、患者の自宅待機中に漢方薬を投与して、少しでも症状の緩解が得られるように試みた。症例提示
《症例1 O.T. 67歳、女性》5月18日 昼頃より発熱(38.3℃)肩こり、頭痛、全身倦怠感をみる。
夜間診察中にTEL連絡あり、保健所の電話番号を教えて、漢方薬を服用するように伝え、家族に薬を取りに来させる。
五虎湯7.5gr+大防風湯10.5gr、食前、3回/日、当日は3時間空けて2回服用した。
夜中に発汗をみる。
5月19日 朝 解熱(36.2℃)し、体の症状も軽快し、気分が良いとのこと。
薬は朝、昼の服用後、廃薬とした。その後、発熱は見られず、元気である(TELにて確認)。
《症例2 N.J. 47歳、男性》
5月21日 朝より咽頭痛、悪寒発熱(38.2℃)がみられた。12時すぎに来院させ、完全防御のうえ、診察した。保健所に電話するように伝えて、五虎湯7.5gr+大防風湯10.5gr、食前、3回/日を投与して、自宅待機を説明した。
夜には、発汗(微似汗)をみている。
5月22日 体温37.5℃、悪寒発熱は軽快し、体は楽になった。食欲も良好で、仕事は休んでいる(TELにて確認)。
5月23日 体温は平熱に下がっており、体も正常に戻ったとの連絡あり。投薬は当日、1日服薬して廃薬とした。
以後、発熱はみられていない。
《症例3 Y.C. 91歳、女性》
8月20日 昼頃、発熱(38.4℃)、全身倦怠感、寒気がみられた。夕方に息子さんより、電話あり。保健所に電話するように伝えて、神秘湯6.0gr+大防風湯10.5gr、食前、3回/日、(5日分)を家族に取りに来させた。当日は3時間あけて2回服用させた。夜に発汗がみられ、翌朝には解熱し、気分もよくなった。投薬は5日間、服用させた。以後、発熱はみられていない。
考察
新型コロナウイルスは一般的な風邪やインフルエンザと同様の感冒症状を呈する。しかし、この新型コロナウイルスは表層の口、鼻、目の粘膜から感染すると、早期に肺へ侵入して肺炎の症状を呈する。さらに、持病を持っている患者は侵襲のスピードが速く、重症化してDICから多臓器不全に至って、死亡する症例もみられる(例:28歳、相撲取り)。漢方薬治療は、昔から命を脅かす病気として風邪が存在し、その治療のため長い戦いの歴史が存在している。そして、1800年前には風邪治療の集大成の専門書として"傷寒雑病学"が出版されている。風邪に対する漢方薬治療の基本は、体の内から表層に向かって不足している免疫力(衛気=漿液性免疫)を運び出して、外邪(ウイルス、風寒邪、細菌)と戦い病因を取り除くことにある。治療の目的は免疫機能を最大限に引き出して、人体が持つ自然治癒力を発揮させることである。
新型コロナウイルスの病態は肺気不調、表層衛気不足である。外邪によって表層は冷え、皮膚の汗孔が閉塞すると、無汗、頭痛、頸肩部痛、関節痛がみられる。また、皮膚の冷えによって悪寒や発熱が出現する。肺へ進むと咳や痰、呼吸困難がみられる。
以上の症状に対する治療方法は表層での十分な衛気(含陽気)を充実させて、皮膚を温め、頭、頸肩部の汗孔、腠理を開いて"微似汗"を出させ、体温を調節、解熱させて、肺気不調を調節し、外邪を排除することである。東洋医学的治療は表層に十分な衛気を充足させるために葛根湯、麻黄湯、小青竜湯、麻杏甘石湯、桂枝湯等(112処方)の処方が準備されている。
今回の新型コロナウイルスは表層から肺に侵入して肺気不調(呼吸障害)を合併しやすいため五虎湯(麻杏甘石湯、神秘湯)を使用し、さらに体の陽気(免疫力)を高めるため大防風湯を合方して投与した。3症例は新型コロナウイルスの感染は不明だが、投薬によって、早期に感冒症状が軽快し、治癒した。
五虎湯の薬効は清肺熱、止咳平喘である。五虎湯は麻杏甘石湯に桑白皮を加えた処方である。麻黄、杏仁によって肺気不調を改善し、肺の熱や痰飲は石膏、杏仁によって取り除き、さらに、桑白皮により瀉肺平喘、利水消腫する(図5)。
神秘湯は五虎湯や麻杏甘石湯の作用に加えて、肝(柴胡)の発揚作用が加わり、表層への衛気、津液の巡りが増強される(図6)。
大防風湯の薬効は祛風湿、散寒、補気血、益腎肝である。地黄、杜仲、附子、人参、白朮、黄耆は腎、脾の陽気を高める。また、白朮、防風、羌活は表層、四肢の風湿を除き、止痛に働く。人参、白朮、甘草、大棗は補気健脾に、当帰、川芎、芍薬、地黄は補血活血、行気止痛、滋腎益精に働く(図7)。
五虎湯、神秘湯、大防風湯の可視化について
処方生薬は生薬の帰経に従って表裏五臓循環図に記入した。生薬の温性、寒性を色で示している。矢印は上行性、下降性を示しており、麻黄、杏仁、桑白皮は肺の巡りの改善を図って、止咳平喘に作用している。表層への点線は麻黄、黄耆、防風、羌活の上昇発散作用を示し、表層での祛風寒湿に働く。人参、白朮、黄耆、杜仲、地黄、附子により脾腎の陽気は高まり、表層の陽気(免疫力)が増強される。腎脾肺の機能は五虎湯や大防風湯により高められ、表層に衛気、津液が増強され、表層の免疫力が高まる。神秘湯はさらに肝の発揚作用高めて五臓の巡りを強化する。生薬の順番は生薬の帰経の臓腑に従って脾胃、肝、肺、心、腎の順とし、大棗、甘草は最後尾に配置した(図5,6、7)。
"微似汗":傷寒論には感冒の治療目標として定めている。表層の皮膚に十分な衛気(陽気)、津液が満たされた時にみられる症状である。
(10月10日、薬科部漢方研究会より、終わり)
参考文献
1)仙頭正四郎著「標準東洋医学」金原出版 2006年4月2)劉 渡舟、姜 元安、生島忍編著「宋本傷寒論」東洋学術出版社 2000年11月
3)神戸中医学研究会編著「中医臨床のための中薬学」東洋学術出版社 2011年9月
4)神戸中医学研究会編著「中医臨床のための方剤学」東洋学術出版社 2012年11月
5)曹 桂植著:陰陽五行図学説と五臓循環図、中医臨床35(2):57-61,2014
6)曹 桂植著:三焦と間質液スペース、中医臨床38(2):62-66,2017
7)佐々木賢二著「金匱要略を読み解く」たにぐち書店 2018年9月
8)曹 桂植著:生薬および処方証の可視化~見える漢方薬~、中医臨床39(2):74-77,2018
図5 五虎湯証(病態)と生薬の作用形態
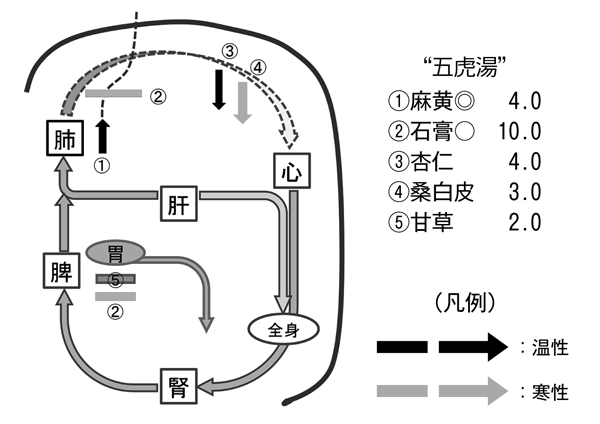
図6 神秘湯証(病態)と生薬の作用形態
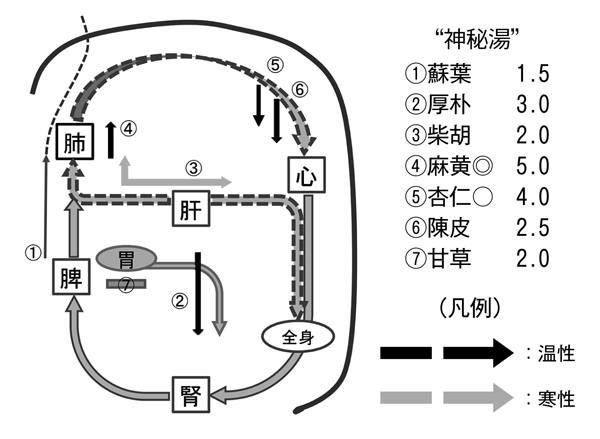
図7 大防風湯証(病態)と生薬の作用形態