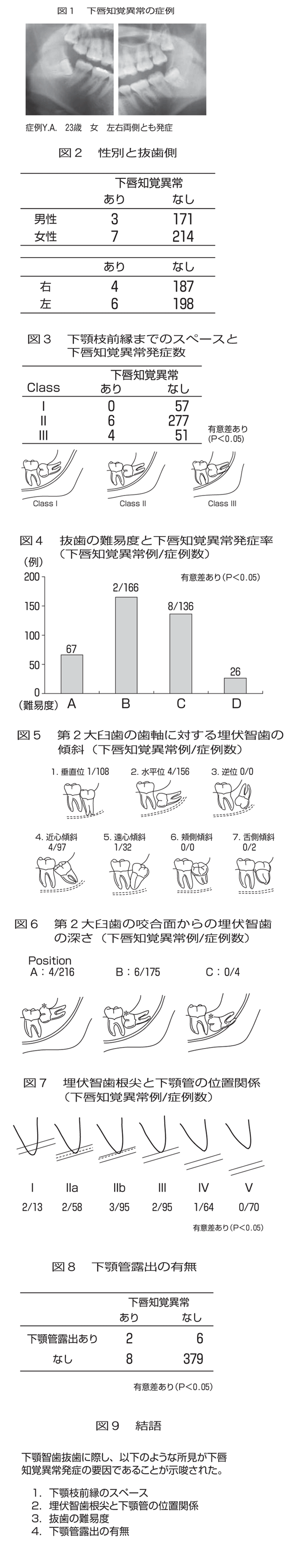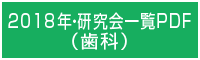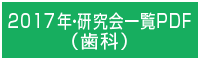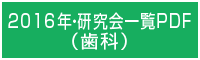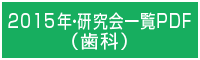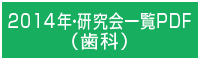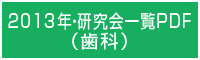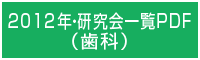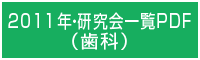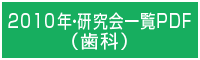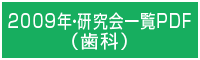歯科2012.06.05 講演
保険診療のてびき ―656― 下顎埋伏智歯根尖と下顎管との位置関係についての検討―パノラマX線写真と歯科用CT画像における比較(上)―
三田市・大槻歯科医院 大槻 榮人先生
共同研究 奈良県立医科大学口腔外科学講座 大阪歯科大学高齢者歯科学講座
はじめに
近年、歯科用コンビームCT(CBCT)の普及に伴い、顎顔面領域でも立体的な高解像度の画像が得られるようになってきた。そこで、パノラマX線写真で下顎智歯が下顎管に近接している症例について、パノラマX線写真とCBCT検査を行って、両所見の関連性について検討するため、2回に分けて報告する。
今回は、2007年の第16回日常診療経験交流会で発表した「下顎埋伏智歯抜歯後に発症した下唇知覚異常の要因(抜粋)」を述べたい。
下顎智歯の抜歯は、口腔外科領域でもっとも頻繁に行われる処置である。しかし、他の部位の抜歯に比べて偶発症の発症頻度が少なくない。なかでも、下唇からオトガイ部の知覚異常は、0.4~5.5%で発症するという報告があり、なかなか知覚異常が治らないケースもある。患者のみならず術者の身体的・精神的ストレスを助長し、医事紛争へ進展することもしばしば報告されている。
下唇知覚異常
図1は、当院で両側下顎智歯抜歯を行った23歳女性のパノラマX線写真である。両側とも下顎管に根尖が近接しており、とくに左側では下顎管と重なっているように見える。この症例は、抜歯後、左右ともに患者は下唇知覚異常を訴え、治癒するまでに、右側で1週間、左側で2週間かかった。
下唇知覚異常の原因には、さまざまな要因が考えられているものの、必ずしも一定の見解が得られていることはなく、供覧した症例のように、比較的大丈夫そうな症例でも、発症することがある。
研究対象
下顎智歯抜歯時に、抜歯後の偶発症をできるだけ予測できないかと考え、本研究では、下顎智歯抜歯を行った症例を対象として、臨床所見、パノラマX線所見、術中所見ならびに術式について調査し、下顎智歯抜歯後の下唇知覚異常の発症に関する要因について検討を行った。
対象は、2004年1月から2006年12月までの3年間に当院で下顎埋伏智歯抜歯を行った342症例、395歯である。男性174例、女性221例で、平均年齢は30.9歳であった。
下顎智歯395例のうち、術後下唇の知覚異常を訴えた症例が10例あり、男性3例、女性7例であった。抜歯側は、右4例、左6例で、発症に左右差はなかった(図2)。
下唇知覚異常の症例は、Winterの分類の中で下顎枝前縁までのスペースが小さいClassIIや、ほとんどないClassIII症例が認められた。統計学的検定で、下顎枝前縁のスペースと下唇知覚異常発症とに有意な関連性が認められた。すなわち、第2大臼歯遠心部のスペースが少ない症例では下顎智歯抜歯後の知覚異常を起こしやすいと言える(図3)。
埋伏智歯抜歯の難易度
次に下顎埋伏智歯抜歯の難易度との関連について調査した。吉増秀實の分類に従って、難易度Aとして、埋伏歯の歯軸は正常で、歯冠は歯肉下にあるかもしくは一部歯肉がかぶっているもの。難易度Bは、下顎智歯は近心傾斜し、歯冠の一部が骨に覆われているもの。難易度Cは、下顎智歯は近心傾斜あるいは水平であり、ほとんど骨に覆われているもの。難易度Dは、完全骨性埋伏智歯で、水平埋伏が多い―以上四つに分類し検討した。
その結果、下顎智歯の症例数は、難易度Bがもっとも多く、次いでC、Aの順であったが、下唇知覚異常の発症は、難易度Cが最も多くなっていた(図4)。
この場合も、統計的有意差を認め、抜歯が難しいと思われる難易度Cの智歯に多く発症することがわかった。しかし、完全骨性埋伏歯である難易度Dでは、下唇知覚異常発症が認められなかった。
下顎智歯の位置を検討すると、2の水平位を示すものが最も多く156例で、下唇の知覚異常は156例中4例あった。垂直位は108例で知覚異常は1例、近心傾斜は97例で、下唇の知覚異常は97例中4例であった。遠心傾斜は32例と比較的少なかったが、下唇の知覚異常が1例あった。逆位や頬側傾斜、舌側傾斜の症例はなかった(図5)。
埋伏智歯の深さ
埋伏の深さについて検討としては、先のWinterの分類に従って、PositionA:埋伏智歯の最も上の点が第2大臼歯の咬合面より上にあるもの。PositionB:埋伏智歯の最も上の点が第2大臼歯の咬合面より下で、歯頸部より上にあるもの。PositionCとして、埋伏智歯の最上点が第2大臼歯歯頸部より下にあるもの―に分類した。
症例数は、PositionAが最も多く、216例、次いでPositionBが175例、PositionCが4例であった。
下唇知覚異常症例は、PositionBが多く、175例中6例、PositionAが216例中4例で、PositionCには、症例数が少なかったせいか、発症は認められなかった。この場合、埋伏歯の深さと下唇知覚異常との関係に、統計学的有意差は認められなかった。しかも、パノラマX線上での下顎管上壁の白線消失の有無についても、知覚異常との関係は認められなかった(図6)。
そこで、パノラマX線写真上で下顎智歯と下顎管の位置関係を詳しく調査するために、下顎智歯根尖と下顎管との距離について、天野克比古らの報告に準じて、分類してみた。
下顎智歯根尖が下顎管下壁に重なり交差している状態をⅠとし、根尖が下顎管上壁に重なっているが、下壁には重ならない状態で、下顎管の幅2分の1以上重なっている状態をⅡa、重なっている量が2分の1以下をⅡbとした。根尖が下顎管上壁に接している状態をⅢとし、根尖が下顎管から離れている状態で、下顎管よりの距離が2㎜未満をⅣ、2㎜以上をⅤとした。
下唇知覚異常との関係は、根尖が下顎管下壁を越えて交差しているⅠで、13例中2例あり、根尖が下顎管中央まで交差しているⅡaで58例中2例、下顎管の幅2分の1以下で95例中3例であった。根尖が下顎管上壁に接しているⅢでは95例中2例、下顎管と離れていて、2㎜未満の場合で64例中1例、2㎜以上では下唇の知覚異常発症はなかった。
この場合、各群間に統計学的有意差が認められ、下顎管に重なるあるいは近接しているものほど、下唇の知覚異常を生じやすいことが明らかとなった(図7)。
下顎管露出の有無
下唇の知覚異常を発症する要因として、術中の所見、術式や抜歯操作が考えられる。そこで、抜歯施術時の所見と下唇の知覚異常発症との関係について調べた。
まず、抜歯操作中あるいは、抜歯後に下顎管露出を認めたケースが8例あり、そのうち2例が下唇の知覚異常を発症していた。両者の関係に統計学的有意差を認め、術中に下顎管が露出した場合は、下歯槽神経への影響があると考えられる(図8)。
結語
当院で行った下顎の埋伏歯抜歯を集計したところ、図9に示すような要因が、術後の下唇知覚異常発症と関係することがわかった。
これらの要因を術前に把握し、患者への説明やインフォームドコンセントに役立てることが、術後の患者とのトラブルを防止することにつながると思われる。
(以上、第16回日常診療経験交流会演題発表からの抜粋。次号につづく)