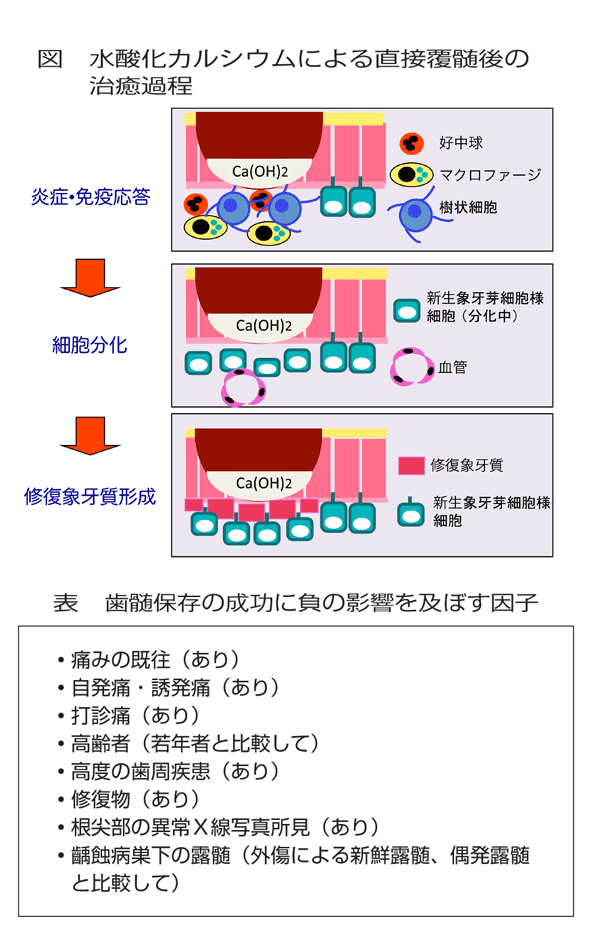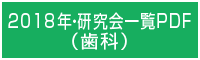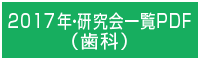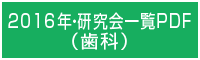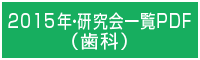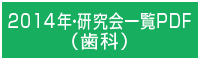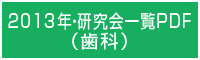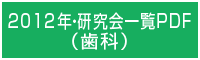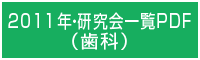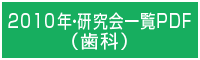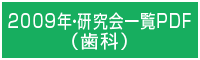歯科2013.03.10 講演
歯科定例研究会より 臨床に役立つ歯髄・象牙質の知識 ―象牙質/歯髄複合体の防御・修復機構と歯髄保存の臨床―
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座う蝕学分野 興地 隆史先生講演
はじめに
歯髄の保存により歯の構造を可及的に温存することが、口腔内で患歯を長期間機能させる上で、かけがえのない意義を有することは詳述するまでもないが、歯髄保存療法の予知性がいまだ十分と言えないことも残念ながら事実である。しかしながら、その成功の基盤というべき基礎的知見は確実に蓄積されつつある。すなわち、歯髄で巧妙に営まれるさまざまな生体防御反応の実態、あるいは修復象牙質形成などの修復機構について、タンパク・遺伝子レベルでの解析が進められている。
失われた歯髄を再生させる試みも活発となりつつあり、再生医療の対象組織として歯髄が扱われることも、決して夢物語ではない。
本稿では、歯髄保存の基礎と臨床に関する最近の話題を概説したい。
1.歯髄の樹状細胞と免疫学的防御機構1)
齲蝕、外傷、歯の切削などにより象牙質の欠損が生じると、象牙細管経由の傷害性因子の影響を排除するための防御反応として、歯髄で炎症や免疫応答が営まれる。歯髄保存療法およびその後の修復処置は、これらの因子の除去と再侵入防止を図り、修復機転による健康状態への回復を図る処置ととらえることができる。
歯髄には、他の結合組織と同じく樹状細胞、マクロファージ、Tリンパ球などの免疫担当細胞が分布している。とりわけ樹状細胞は、細長い突起を樹の枝状に周囲の細胞間に伸ばす特有の形態と、MHCクラスⅡ分子(免疫応答における自己・非自己の識別に際し、いわば「自己のマーカー」として機能する分子)の発現で特徴づけられる白血球の一種である。
抗原の侵入を監視するとともに、抗原の情報をTリンパ球に伝達し活性化させること(抗原提示)により、免疫応答の発動に重要な役割を演じる。
歯髄の樹状細胞は象牙芽細胞層近傍に集積しており、象牙芽細胞間に突起を伸ばしつつ規則正しく配列している。外部からの細菌侵襲が最初に到達する部位に、その監視を主要な機能とする細胞が合目的的に配置されていると考えることができる。また、象牙質窩洞や象牙質齲蝕病巣の直下にこれらの細胞が集積を示すことや、コンポジットレジン修復後に集積が不明瞭になることも確認されている。さらに、浅在性象牙質齲蝕歯ではTリンパ球、樹状細胞主体の細胞浸潤がみられる。
以上より、齲蝕に対する歯髄の初期防衛反応として、浅在性齲蝕の段階より樹状細胞とTリンパ球との相互作用(抗原提示)によるTリンパ球活性化が営まれていることが推定される。
2.象牙質/歯髄複合体の修復機構2)
適切な歯髄保護(覆髄)が講じられた後の治癒経過は、歯髄保存療法の基礎となる重要な事項の一つである。新生硬組織形成を歯髄保存療法の組織学的なゴールと考えることができる。象牙芽細胞への刺激が比較的弱い時には、静止状態にある既存の象牙芽細胞が象牙質形成に転じ、新生硬組織が形成される。この機構で形成された硬組織は、後述の修復象牙質と区別して反応(性)象牙質と呼ばれることがある。
一方、刺激の強さがある一線を超えると象牙芽細胞は死滅するが、この際には創傷部に好中球、マクロファージ、樹状細胞などが一時的に出現したのち、歯髄内の間葉系幹細胞より新たな象牙芽細胞様細胞が分化し、修復象牙質が形成される(図)。
以上の経過の細胞・分子レベルでの解析、とりわけ新生象牙芽細胞様細胞への分化過程で作用する分化制御因子の解明は、象牙質の生物学的再生療法の創生につながることから、多くの研究者の注目を集めている。
3.直接覆髄の是非2)
直接覆髄と抜髄の選択は、今なお歯内療法が抱える最大の争点の一つと言っても過言でない。本稿では、直接覆髄の予後に影響を及ぼす主要な因子をあげ、その適応や施術上の留意点を考えてみたい。
(1)術前因子(診断、症例選択)
正常もしくは可逆性歯髄炎と診断された症例が直接覆髄の適応症となる。ところが、痛みの有無、程度や持続時間が感染や組織破壊の程度と必ずしも相関しないことから、術前に歯髄の状態を的確に診断することは困難である。この点は、今なお歯髄保存療法の予知性を低下させる大きな要因となっている。
したがって、筆者は歯髄保存に負の影響を及ぼすさまざまな因子(表)の有無を検討し、これらを多数抱える症例は、原則として直接覆髄の適応から除外している。
判断に迷われる症例では、待機的診断法を採用する。また、深在性齲蝕の症例では、後述の歯髄温存療法(暫間的間接覆髄、IPC法)の適用を検討する。
(2)術中因子
直接覆髄の予後に負の影響を及ぼす術中因子として、多量の出血や血餅の残存をあげることができる。
次亜塩素酸ナトリウムによる露髄部の清浄化(ケミカルサージェリー)は、わが国独自の術式であるが、近年では海外の文献にも有効性を示唆する報告がなされている。
(3)術後因子(細菌感染)
負の影響を及ぼす術後因子として、微少漏洩による細菌感染をあげることができる。
水酸化カルシウムは封鎖性に乏しく、溶解性も高いことから、適切な修復材との併用が不可欠である。また、露髄部の新生硬組織(デンティンブリッジ)もトンネル状の欠損を示す場合があり、必ずしも感染経路を完全に遮断しない。
接着性レジンなど、高度の封鎖性を示す材料で速やかに修復を施すことは、覆髄法成功のポイントの一つであろう。
4.歯髄温存療法(暫間的間接覆髄、IPC法)2)
深い齲蝕を有し可逆性歯髄炎と診断される症例を対象とし、感染歯質深層を残存させたまま数カ月間覆髄剤(水酸化カルシウム製剤など)を作用させたのち、感染歯質の硬化や修復象牙質の形成を待って数カ月後にリエントリー(再度の感染歯質の除去)を行うもので、段階的な感染歯質除去(stepwise excavation)により露髄を避けようとするところに特徴がある。治療期間が長く、患者のコンプライアンスが重要となるが、露髄を避けることの意義から、推奨されるべき処置法と筆者は考えている。
5.Mineral trioxide aggregate (MTA)2,3)
MTAは、建築用セメント(ポルトランドセメント)を歯科用に改変した「ケイ酸カルシウム系水硬性セメント」ともいうべき材料で、本邦では「歯科用覆髄材料」として薬事承認され、2007年より市販されている。MTAの第一の特徴は、優れた生体親和性にあり、直接覆髄後に新生硬組織による露髄部の閉鎖が高率に生じることも組織学的に報告されている。また、MTAの高い封鎖性も多くの研究で確認されている。さらに、MTA硬化体の崩壊は水酸化カルシウム製剤より格段に少ない。
MTAは、多少の水分の存在下でも物性を低下させないため、湿潤環境下の操作がある程度許容されることも特徴の一つである。MTAは抗菌性もある程度備えるが、これは本セメントがアルカリ性を示すことによる。
以上の性質の多くは、MTA硬化体が水酸化カルシウムの結晶を含み、いわば「水酸化カルシウム徐放体」として作用することで説明される。また、リン酸イオン存在下では硬化体からのカルシウムイオンの放出に続いて表層にアパタイト様の結晶生成が生じることも知られており、生体親和性や封鎖性につながる性質と考えられている。
MTAは新しい材料であるため、臨床成績に関する報告は十分とはいえない。直接覆髄で、従来の水酸化カルシウム製剤と同等以上の臨床成績を収めるとの報告はなされつつあるが、MTAが従来の適応症を大きく拡大させるとの臨床エビデンスは今のところ得られていない。したがって、偶発露髄や外傷後の新鮮露髄は良好な適応症と考えられるが、齲蝕病巣内の露髄例には慎重な適用が望まれよう。
MTAによる覆髄の術式に水酸化カルシウム系セメントとの大きな相違はないが、MTAの練和物は稠度が低くやや扱いづらいため、その適用には専用器具(小口径のアマルガムキャリア様器具など)がしばしば有用である。
おわりに
歯髄保存療法は、成功時に患者が受ける大きな恩恵とは裏腹に、時には予知性の不確実さと隣り合わせの部分を抱えた処置でもある。近年の生物学的解析からは、歯髄が比較的高い防御・修復機能を備えることが示唆されるが、臨床の現場でこの能力を引き出そうとする場合、感染の制御という障壁がしばしば立ちふさがっているように思われる。成功に導くためには、的確な診断と施術のみならず、患者のコンプライアンスや患者とのコミュニケーションをも含めた症例選択の妥当性が要求されよう。拙文が、そのための指針として参考となれば幸いである。
参考文献
1)興地隆史.歯髄の免疫防御システムと歯髄保存.歯科医療,2013;27:14-20.
2)興地隆史.歯髄保存療法の新たな可能性.日歯医師会誌,2010;63:713-721.
3)興地隆史他.MTAの理化学的・生物学的特性と臨床.日歯内療誌,2012;33:3-13.