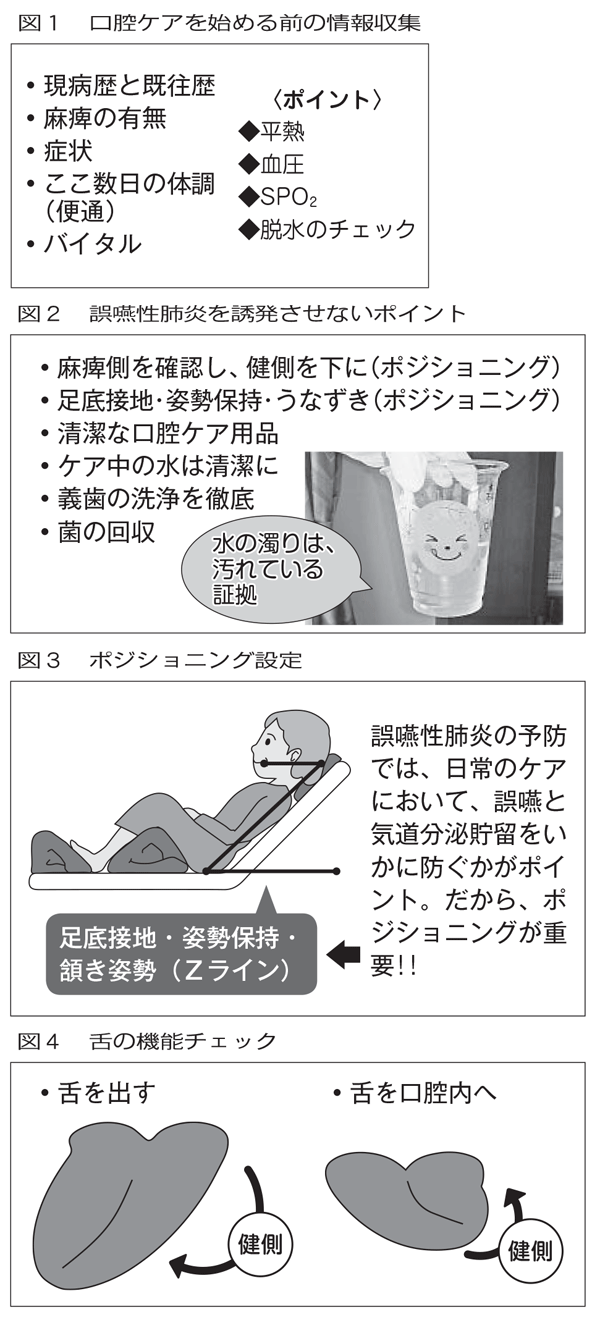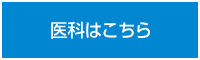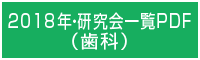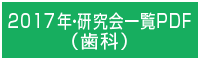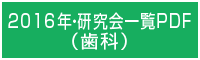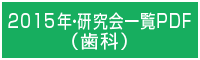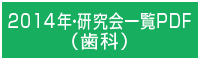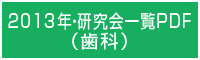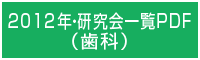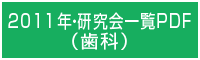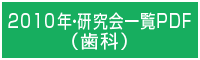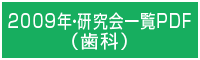歯科2017.05.14 講演
歯科定例研究会より
効果を出すための実践的口腔ケアと口腔リハビリテーション
NPO法人健口サポート歯るる 副理事長・歯科衛生士 平松 満紀美先生講演
口腔ケアとは
近年、歯科領域を超えて医療・福祉・介護の現場においても口腔ケアの重要性が叫ばれています。これは、誤嚥性肺炎の予防、口腔機能向上、摂食嚥下リハビリテーションを語る上で口腔ケアの必要性が再確認されたためです。口腔ケアとは、単なる歯磨き・入れ歯磨きではなく、摂食嚥下リハビリテーションまでを踏まえたケアでなければならないと考えています。なぜなら、摂食嚥下を考えるときに口腔ケアは重要なポジションにあり、摂食・嚥下の成功の鍵は口腔ケアにあるといっても過言ではないと考えられているからです。年齢・疾患のいずれから見ても決まった枠にはまるようなものではなく、口から食べる・話す・呼吸することは、医療のみならず介護・福祉の領域でも重要であることから、関わるすべての職種の方にご理解と共通認識をいただきたいと考えてお話しさせていただきました。
医療・介護の現場で「歯科衛生士が行う口腔ケアは、やっぱり違うよね」と言ってもらえる一方で、「歯科衛生士のケアの後には誤嚥性肺炎になる」とか「歯科衛生士のケアの後には熱発する」とささやかれることもあります。誤嚥性肺炎の予防につながる専門的口腔ケアを実施している歯科衛生士にとって、そのささやきは非常に残念な言葉です。これは歯科衛生士だけの責任ではなく、歯科医院の口腔ケアに対する資質が問われていると理解しなければなりません。なぜなら、歯科衛生士は歯科医院の看板を背負って単独訪問しているからです。
誤嚥性肺炎を予防する
医療・介護の現場で「私たちの役割は何か」を考えたとき、歯科衛生士の専門性を活かして、誤嚥性肺炎の予防および食べることを支援していくこと。そのために必要な知識として、摂食嚥下のメカニズムと摂食嚥下リハビリテーションを理解しておくべきと考えます。口腔ケアを始めるその前に、必ず情報収集と現状評価を行ってください。現病歴・既往歴・麻痺の有無など。中でも、普段の平熱、血圧、SPO2は貴重な情報です。例えば平熱が35.5℃の方が36.8℃あれば明らか何かに感染していると想定し、多職種と連携をとる必要があります。しかし、平熱を把握していないと、感染を見落とし重篤になる場合があります。私は0.5〜0.8℃以内の上昇ならばこもり熱を疑い、それ以上の上昇ならば体調の変化(感染を疑う)と考え、主治医等に連絡し情報を共有しています(多職種連携)。(図1 口腔ケアを始める前の情報収集)
歯科衛生士が行う専門的口腔ケアは、誤嚥性肺炎の予防を期待されています。そこで今一度、誤嚥性肺炎とは何か?を考えてみたいと思います。誤嚥性肺炎とは、鼻や喉、口の中の細菌が食べ物や唾液と一緒に気管や肺に侵入し肺炎を起こすこと。口腔内が不潔な方は、たびたび肺炎を起こす。きれいな唾液を誤嚥しても簡単に肺炎にはなりません。
口腔粘膜のケアを意識
だから、口腔内を清潔にする必要があるのです。ここで強くお伝えしたいのが「単なる歯磨きではなく、口腔ケアであること」です。口腔を100%とした場合、単なる歯磨き・入れ歯磨きならば30%程度のケアとなります。残りの70%は口腔粘膜なのです。歯磨きで口腔粘膜に飛沫した菌の回収を行う必要が重要です。義歯の洗浄も同様です。目に見える汚れ、触って分かる汚れはブラシを掛けて除去し、目に見えない汚れは義歯洗浄剤で除菌してください。あなたは、要介護者が使用する義歯の洗浄に自信がありますか? 一度染め出し液で確認してみてください。健常者と違い、要介護者の義歯は汚れ方が違います。このとき、義歯用歯磨き剤もおすすめです。どうか「義歯の汚れが原因で誤嚥性肺炎に」ということがないように。また、口腔ケアのポイントとして、清潔な水を使用すること。ケア中の水が濁っている間は、菌の回収中であると理解してください。常に清潔な水でブラッシングや口腔清拭を行ってください。それが誤嚥性肺炎を誘発させないポイントとなります。(図2 誤嚥性肺炎を誘発させないポイント)
歯科衛生士による専門的口腔ケアを実施し、ご本人・ご家族・多職種を巻き込み普段のケアで清潔維持を心がけることにより、口腔内の清潔を維持することで、誤嚥性肺炎のリスクは軽減されます。ここで見落としてはいけないポイントとして、口腔ケアや食事時のポジショニングが重要になります。足底接地・姿勢保持・頷き姿勢でポジショニング設定します。(図3 ポジショニング設定イラスト)
また、食べることを支援していくためには、口腔機能と食形態がマッチングしているかを確認し、必要ならば口腔リハビリテーションを行います。口腔機能のチェックは不可欠です。私たちは口腔を預かる専門職です。口腔を診る、観る、看る専門職として、口腔機能(舌機能)の麻痺がないか確認してください。身体麻痺の情報はあるが、口腔の麻痺に関して情報がないことが多いのが実情です。(図4 舌機能チェックのイラスト)
誤嚥性肺炎の原因を調べる
現場で「誤嚥性肺炎の予防のために専門的口腔ケアをお願いしたい」と依頼があったら、「何が原因で誤嚥性肺炎になったのか」を紐解く必要があります。なぜなら、誤嚥性肺炎の原因が口腔内の不潔によるものならば、専門的口腔ケアで予防可能となりますが、逆流による誤嚥性肺炎なら歯科の領域だけでは予防できないからです。(逆流による誤嚥性肺炎を歯科の責任にされないように)口腔機能の状態に合わせた口腔リハビリテーションを実施するとき
(1)舌骨上筋群にアプローチするなら頭部挙上訓練(シャキアエクササイズ)や嚥下おでこ体操。
(2)鼻咽腔閉鎖(口蓋帆・咽頭閉鎖)にかかわる筋群にアプローチするなら、ペットボトルを使ってブローイング訓練。
(3)基礎訓練および嚥下反射を誘発するなら、アイスマッサージなど。
おわりに
すべての人が、一生涯おいしく楽しく安全に食生活を営み、たとえ食べられなくなっても、健康な口腔を通じて豊かな人生をお過ごしいただけるように、在宅・施設での症例を交え「効果を出すための実践的口腔ケアと口腔リハビリテーション」についてご紹介させていただきました。歯科衛生士の単独訪問が認められた今、効果を出すためには、歯科医師の診査・診断と現場における歯科衛生士の判断が必要です。また、歯科衛生士には「歯科医院の看板を背負っている」自覚と、院内での歯科医師と歯科衛生士の連携が多職種連携と同様に重要と考えます。「歯科衛生士が行う専門的口腔ケアは、やっぱり違う」と患者・家族・多職種に感じてもらえるケアが実施されますように。そして、今回の講演が地域医療貢献の一助となれますように。(5月14日、歯科定例研究会より、小見出しは編集部)