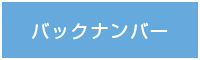2011年4月25日(1653号) ピックアップニュース
主張 東日本大震災 医療・福祉などの復旧へ制度改善を
東日本大震災の多くの被災者と、原発事故で難儀をされている人々に心からお見舞い申し上げる。
私たちは16年前、阪神・淡路大震災を経験した。多くの医療機関が被災し、日常診療が行えない状況に陥ったことは記憶に新しい。
命と健康を守る医療体制の立て直しにむけ、全国の多くの支援を得ながら、制度面からも行政交渉が積み重ねられ、一定の前進をかち取ることができた。当時から闘いがスタートした「被災者生活再建支援法」も、この間の多くの災害における被災者救援の闘いの中で、不十分さを残しながらも一定の成果を収めることができた。
私たちはこれらの経験を踏まえ、このたびの未曾有の大災害に対して情報を発信し、一日でも早い復旧に向けて協力していく義務がある。
復旧に向けた課題
(1)被災者の医療費の一部負担金免除
当初は免除規定の範囲が厳しく、阪神・淡路大震災以下の条件であり、社会保険は免除ではなく“猶予”であった。協会・保団連はただちに厚労省と交渉を行い、速やかに改善がされた。しかし、5月末という期限の問題に加え介護保険制度が定着している現在では、これらの一部負担金の免除規定も必要であろう。
(2)診療報酬等の概算請求
これらにおいては比較的速やかに対応がなされた。しかし、一部負担金(窓口負担)免除に対する十分な手当てと、資金ショートさせない融資等の充実が求められる。同時に歯科をはじめ調剤薬局、介護保険の事業所にも同様のことが求められる。
(3)すべての被災民間医療機関への公的助成
阪神・淡路当時は「医療設備近代化設備整備事業」の拡大解釈と運用を求めた。しかし、政策上救急医療の整備のためとされ、2次救急病院群輪番制参加病院、在宅輪番、休日当番等出務医療機関に限られた。一人医療法人、産婦人科・歯科医療機関が除外されたため、全・半壊、一部損壊の医療機関の一割弱にしか適用されなかった。
地域医療崩壊を食い止めるために、2009年第1次補正予算で、都道府県に「地域医療再生基金」が設置されている。2次医療圏を対象に13年度までの5年間の事業で、予算総額3100億円。さまざまな計画で執行されていると思われるが、全国の力を合わせるならば、被災地の医療再生に向けてかなりのことが可能ではないかと考える。
「創造的復興」より暮らしと街の復旧を
復旧において民主党は、復興基本法案の原案で「復興は単なる原型復旧ではなく、新たな『地域社会の再生』」とし、「わが国の再興(再創造)を目指す」と強調し、手法はPFI方式で行うとしている。
しかし思い出してほしい、あの阪神・淡路大震災における「創造的復興」のことを。現在、兵庫県も神戸市も財政的危機に直面しているという。原因は震災復興のための財政出動だとしているが、“創造的”と称してゼネコン奉仕の乱開発を行ってきた結果であることは間違いない。
元に戻す=復旧こそが私たちの望みであった。このことは多くの場で確認されてきたはずである。この教訓もしっかり伝えることが大切であり、安心して住み続けられる街の復興のあり方を、住民が主体で考え作り上げていくこと、そしてそのことにわれわれも協力していくことが重要だ。