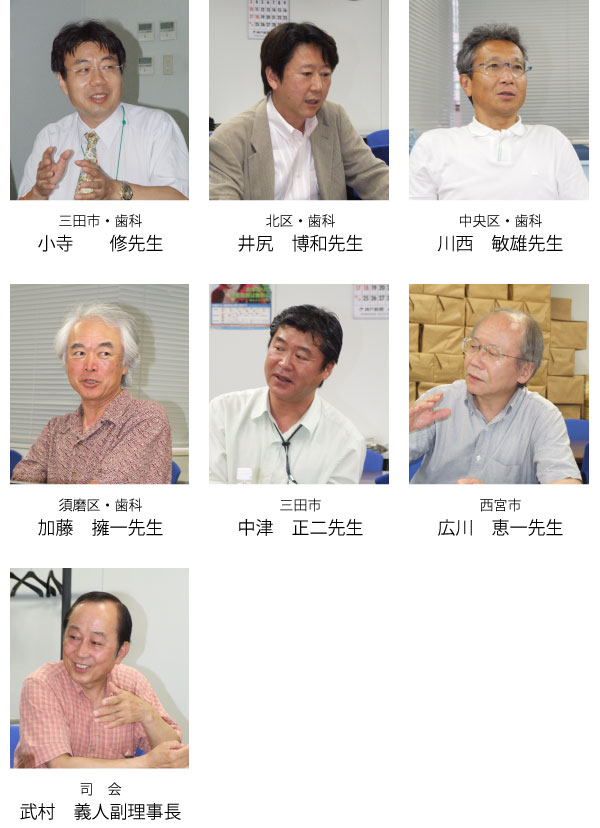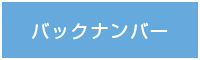2011年8月25日(1663号) ピックアップニュース
"阪神・淡路"の教訓を今こそ 東日本大震災特集 被災地訪問者座談会

(3月20日、仙台市)
3月11日の東日本大震災発生後、医療活動のため被災地入りした先生方による座談会を、7月9日に協会会議室で行った。出席者は、広川恵一理事、加藤擁一副理事長、中津正二先生、川西敏雄副理事長、井尻博和評議員、小寺修先生、司会は武村義人副理事長が務め、現地での医療活動を通じて感じたことや被災地の今後の課題について語っていただいた。
武村 東日本大震災発生直後の3月12日の理事会で、協会は当面の被災地支援策などを確認し、被災者支援に全力をあげてきた。現地での医療活動に参加された皆さんに、今後の復旧・復興の課題などについて話し合っていただきたい。
被災地の課題をどう見つけるか
井尻 5月のゴールデンウィークに川西先生や小寺先生らと被災地入りしたが、依然として現地はがれきの山だった。避難所の方々も将来が見えない中で生活されていて、疲れ切っていた。何も希望がないという様子がひしひしと伝わってきた。多くのことが手つかずのままになっている。被災地で政府の顔が全く見えてこなかった。
阪神・淡路大震災と違い、被害は非常に広範囲だ。仙台市から東松島市や石巻市まで、神戸-大阪間と同じくらいの40~50キロの距離を往復しただけだったが、車がひっくり返っている景色がずっと続いていた。すごい津波だったんだと実感した。ヘドロの異臭もすごく、テレビを見ているだけではわからないことだらけだった。
川西 政府はもっと迅速に対応しなければならない。被災地の医療支援はボランティアに頼っている状況で、マンパワーが不足していた。政府自身による手立てが必要だと強く感じた。そして現在も同じだ。
小寺 北摂・丹波支部で中津先生が被災地支援に行かれた話を聞き、「私も現地に行かなければ」との思いに駆られ、川西先生、井尻先生らと共に避難所を回った。医療活動にあたっては、兵庫や宮城協会の事務局が現地の医師・歯科医師につないでくれたことが大変貴重で助かった。
避難所では温かい食事はカップラーメンくらい。東北の人の気質かもしれないが、出されたら全部食べないといけないと思っている人が多く、結果として塩分の高いものを食べ続けることになり、血圧の高い人が多かった。
中津 震災から1カ月後くらいに宮城県を訪問した。避難所の石巻高校を訪れ血圧を測ったが、皆、異常に高く、10人ほど測って3人が200mmHgを越えていた。塩分の高い食事とともに、余震による不眠やストレスの増加、長引く避難生活による運動不足が大きな要因だろう。
私の診療科である脳神経外科の医療支援については当時、「3カ月覚悟で、できれば4カ月間滞在できる人に来てほしい」との要望も言われていたが、ほとんどのドクターは3カ月も滞在できない。保険医協会で実施した短期間の「弾丸ツアー」の形でも、まとまった人数で発災直後の早い時期に行けば、十分に支援活動ができると思った。「医者が来るよりインフラをなんとかしてほしい」という意見もあったが、避難所は「歯科医療は足りている」という事前情報とは全然違い、圧倒的にマンパワーが不足していた。今振り返って、発災から1カ月前後の早い段階で、もっと大量に医師・歯科医師を投入できなかったかと強く思う。
加藤 私は震災1カ月後くらいに近畿の歯科医師の先生方や中津先生と共に被災地を訪問したが、石巻市は街ごと壊滅状態だった。避難所の被災者の口腔内の状態は、非常に問題のある人が多かった。中津先生が言われたように、行く前は歯科医療の需要はあまりないと聞いていた。しかし避難所で一人ひとり丁寧に声をかけて回ると、歯茎が腫れて食事ができないなど、問題を抱えている人が多かった。阪神・淡路大震災のときも、口腔内に限らず以前から抱えていた病気が、環境の激変で悪化することがよく見られた。歯ブラシも行き渡っていると聞いていたが、個々の避難者に聞くと足りていない人も多く、持参した義歯洗浄剤はあっという間になくなった。
阪神・淡路大震災のときも歯科医療のために避難所を回ったが、当時と同じような状況だった。今回、震災関連死につながる誤嚥性肺炎の防止には口腔ケアが大切だと声をかけて回った。神戸から来たとあいさつすると、「遠い所からよく来てくれた」「神戸も大変だったでしょう」と温かい言葉を返してくれた。大地震を体験した者同士として、初対面でも話しやすい雰囲気ができた。
広川 3月と4月に、被災地を訪問させていただいた。最初の被災地訪問で宮城県塩釜市の坂総合病院の医師に話を聞いて驚いたのは、搬送されてきた人たちに低体温の人が多かったことだ。阪神・淡路大震災のときには聞かれることはなかった。東北は寒い時期で、津波被害の中で灯油不足で暖房もなく、毛布も足りていなかったためだ。
被災地は日々変化し、課題やニーズも変わっていく。避難所から仮設住宅へ、仮設住宅から恒久住宅へと被災者の生活の場は移っていくが、敏感に課題を先取りしながら対策をとっていくことが大切だ。避難所・仮設住宅での課題は、何よりも二次災害としての「避けられる死」を防ぐことだ。
仮設住宅に入っている人たちに温泉で休んでもらおうと青森協会が取り組んでいる「ほっと一息プロジェクト」に私も参加させてもらい、被災者の人たちの血圧を測らせてもらったが、中津先生が言われたように180から200以上の人が多くみられた。この状態が続くと、今後、脳血管障害の人が増えてくる恐れがある。血圧は誰でも測れるので、血圧測定を入口にして、被災者の健康状態を見直し生活改善をしていく、食事を改善するなど、いろいろな形で今後につないでいくことが大事だ。
井尻 新聞に「介護施設 被災後死亡2倍」という記事があった。岩手、宮城、福島の被災42市町村の介護施設で、震災は生き延びたが体調悪化などで亡くなる方が増えているようだ。阪神・淡路では多数の震災関連死が出た。避難所での関連死だけでなく、要介護者などが多く搬送されている介護施設で「避けられる死」をなくすことも大きな課題だろう。
広川 支援者のあり方として大事なことは、被災地から受け入れられている存在であること、支援活動が被災地の人々に支えられているということ、そして被災地の人々の話を聞かせてもらい教えてもらうこと、そのなかで学ばせてもらうということ。
同時に、被災地の人々は、外部から「してもらう」という存在ではなく、全国からの支援が円滑に進んでいくために力を発揮するという大切な役割がある。地域の人々と外部からの人々の相互関係を正しくとらえることが大切だ。地域の人々の支えがあってこそと思う。
被災者にお話を聞かせていただくこと、医療につなぐことなど、被災地のなかでの看護師の役割は大きい。阪神・淡路大震災でも看護師による避難所訪問が行われたが、その時の柱は、被災者の感情の表現を支えること、適切な看護ケアを行い、必要な人には医療機関への受診を促しそれを支えること、この3点であった。
被災医療機関の再建のためには
中津 医療支援にあたっては、災害コーディネーターのもとでエリアごとに活動するのも大事だが、できれば、被災した地元開業医のもとで巡回し、被災者の診療記録をその開業医に託すことで、地域医療機関の再建を支援することが必要ではないかと思った。
小寺 例えば被災した歯科医院の勤務医という形で診察して回れば、その診療所が保険請求できるようになる。ボランティアによる医療支援が、被災地の医療機関の再建にもつながるような仕組みを国はつくってほしい。そのほか、転倒や浸水で医療機器の買い替えが必要な被災地の医療機関へ、全国から中古品を集めれば、診療を再開するにあたっても大きな負担軽減になる。これも、被災地をPL法の適用外にするなど国がシステムを整えるべきだろう。
川西 被災した多くの医療機関が、再開のためには公的な補助・助成が不可欠だと感じている。現時点では、公立病院に対する補助に限られ、同じように地域医療を支えている民間病院・診療所への支援がまったく不十分だ。阪神・淡路のときは「医療施設近代化施設整備事業」の拡大適用で、民間を含む230の医療機関に合計94億円の国庫補助が行われ、被災地の医療機能回復に一定の役割を果たした。被災者が安心して必要な医療を受けられるよう、民間医療機関にも迅速な支援策が必要だ。とにかく遅い。
武村 被災3県は、旧自公政権時代の「公立病院ガイドライン」による病院の統廃合で、もともと医師不足が深刻な地域だ。震災が地域医療崩壊に拍車をかけたと言える。政府による病院の“再編・集約化”路線を見直し、普段から災害に備えて余裕のある医療体制を構築するための診療報酬の改善が必要不可欠だろう。

小寺(中央)、井尻(左端)各先生
(5月4日、石巻市)
生活・営業の再建最優先に
武村 被災地では、いまだに10万人近い住民が不自由な避難生活を余儀なくされている。生活基盤の回復や仕事と営業再建のめどが立っていない人たちも大勢いる。阪神・淡路大震災の経験から、今後どのような復興施策が必要だと考えるか。
川西 政府は被災者を本当に救おうと思っているのだろうか。例えば、被災者の医療費窓口一部負担金免除は、当初は対象者を著しく限定していた(その後、兵庫協会・保団連などの要請で拡大された)。政府広報の被災者生活ハンドブックで、保険証がなくても受診できることや、免除機関が来年2月までに拡大されたことなど重要な情報が欠落していたことなどは一例だ。
加藤 阪神・淡路のとき、被災者が求めたのは何よりも個人補償だった。家屋が潰れた被災者は、「こんなときこそ住宅再建に税金投入を」と切実に願っていたが、当時の村山首相が「資本主義の国では個人補償はありえない」と主張したように、国は一貫して「自己責任で」との態度をとった。必要な個人補償がなされなかったため、阪神・淡路の被災者の多くは今でも苦しい生活を強いられている。
広川 阪神・淡路のときと同様に、二重ローンが大きな問題になっている。小売業の人たちの仕入債務のことなど、社会的に小売業を支えていくことに努めなければならない。暮らしを支える適切な消費が可能な街づくりにしていかなければならない。
中津 被災地での消費をどう支えるかは重要な問題だ。仙台市で入った飲食店の若い女子店員と話をしたが、家を流されていたにもかかわらず、それでも懸命に働いていた。被災者の生活を支えるには、現地に関わる消費に努めることが大切だ。そうしないと、被災者は県外に出ざるを得なくなってしまう。
井尻 現地ではがれきの処理やヘドロかきが進んでおらずニーズが非常に高かったが、ボランティアに頼っている状態だった。がれき処理やヘドロかきの仕事を被災者に提供し、被災地で生活していけるシステムを構築しないといけない。現地の人たちが職を得られる仕組みにすることは、復旧・復興の一番の原動力になるだろう。
〝創造的復興〟押し付けるな
川西 日本経団連の米倉会長は、「復興特区」の設置を提案している。当初から増税ありきの政府の復興構想会議が6月末に発表した「復興への提言」でも、規制緩和で国内外の大企業誘致を進めることや、福島県に医療産業の「特区」を設置するなどとしている。大企業中心の、いわゆる「創造的復興」路線が敷かれようとしている。しかし、これらは被災者・避難者の方々が中心の施策と言えるだろうか。どうみても、目線が違うように感じる。今後は、そのあたりも注視したい。
加藤 上から押し付ける復興施策ではだめだ。最悪の例が、阪神・淡路の震災復興事業として進められた神戸空港建設と新長田の再開発。黒字になると宣伝されていた神戸空港は結局大赤字で、神戸市は市民の税金で穴埋めしようとしている。新長田の再開発事業も、大きなビルはできたがテナントはガラガラだ。阪神・淡路大震災の復興事業費約16兆3千億円のうち、半分以上の約8兆3千億円が神戸空港など被災者支援とは直接関係のない事業に充てられた。東北でも同じことが繰り返されようとしているが、私たちは「それはアカン」と声を大にして言わないといけない。住民が再び元の場所で生活できる街づくりを、住民自身の手で進めないといけない。
広川 発災直後から、地域救援の第一の担い手は地域の住民。諸救援組織や外部の医療団体が行く以前から、自分たちで守りあい、がれきに埋もれた人や津波で溺れている人、低体温となっている人たちを助けたのは地域の人々だった。救援活動だけでなく復旧・復興の全過程においても、地域の人たちが第一の主体だということを全国に伝えていくことが、阪神・淡路大震災を経験した私たちの役割の一つ。
「創造的復興」がだめというのはまさにその通りで、東北の文化を守る形での復旧・復興がなによりも大事だ。そのためには、地域の人たちこそ主人公であるべき。
小寺 奥尻沖地震やスマトラ沖地震などで、津波の実態をメディアは伝えてこなかった。阪神・淡路大震災も、鎮魂の行事は報道されるが、全国にその教訓が報道されていない。今回の東日本大震災のさまざまな教訓も、繰り返し全国に伝えていくべきだ。
武村 被災者の生活再建へ国・地方自治体が責任を果たすよう求めることを目的にした「東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター」が発足するなど、被災者・被災地が主役の復興をめざす動きも始まっている。大企業中心の上からの復興か、地域住民主体の復旧・復興か、これから大きな闘いが始まる。阪神・淡路大震災の被災協会として、被災者の命と健康を守る取り組みの課題や、被災地の復旧・復興の教訓を被災地と全国に伝えていきたい。本日はお忙しいところ、ありがとうございました。
最後に一言
広川 兵庫協会を通して、「被災地での生活と医療と看護」(兵庫県保険医協会/協会西宮・芦屋支部編 2011年2月17日)と東京保険医新聞2011年8月5・15日合併号「震災後の復興と医療機関の役割」をお読みいただければ幸いです。
加藤 復興まで長い時間がかかると思うが、息の長い支援を続けていきたい。阪神・淡路大震災の教訓を少しでもいかせるようにしていきたい。
中津 時間を経るに従い、現地の状況は複雑になると思われます。今後は東北関連の消費に自ら努めるようにしたいと思います。
川西 被災地へボランティアに行く者の心得(イロハ)について研修会開催を!
井尻 微力ながら支援活動に参加させていただけたことに感謝申し上げます。
小寺 協会の支援を得て被災地に出向けたことは非常に有意義で、私自身の人間としての向上になったと感謝いたしております。