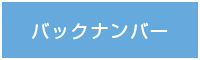2012年4月25日(1685号) ピックアップニュース
女医の会インタビュー (8)
父の死きっかけに在宅ホスピス医へ 灘区 関本 雅子
 私は、2001年に開業し、在宅ホスピスに取り組んでいます。
私は、2001年に開業し、在宅ホスピスに取り組んでいます。毎日、患者さんの座りなれた椅子に座ってもらって状態を診ます。お孫さんが寄って来られる家や、たくさん昔の写真を飾られて話題が尽きない方など、いろいろな方がいます。がんは痛みとの闘いですが、在宅では、病院で見る患者さんの表情とは全く違い、日常生活を過ごされながら自分らしさをもっておられます。
神戸大学医学部卒業後、麻酔科医として病院勤務していましたが、父をがんで亡くしたことがきっかけで緩和医療に目を向けるようになりました。
父は、私が勤めている病院に運ばれ、回復の見込みはありませんでしたが、息を引き取るまで点滴で栄養を送り続けました。このとき、父はこのような人生の終わり方を望んだのかなと不安になりました。
近年になって「患者さんの意思を尊重した医療を」と言われますが、従来の終末期医療は技術に応じた延命治療を行うだけが普通だったのです。
人生の先輩たちをがんで亡くしたとき、ホスピス医になると決めました。麻酔科医からホスピス医への道は手探りでした。いろいろな研修の機会をいただき、ギッシリとメモをとる毎日でした。若くしてがんで亡くなった先生が「医療者のための緩和ケアにならないで」との言葉を残され、私は今でもその言葉を肝に銘じています。
今まで経験したこと、人との出会いが全て今の医者人生にプラスになっています。
これまで、たくさんの方を看取りましたが、「その人らしい最期は日常生活の延長にある」と確信しています。患者さんが人生の総まとめをするメチャクチャ貴重な時間をともに歩めるなんて、とても幸せな仕事です。
お茶教室が元気の源 姫路市 宗実 琴子
 医師になって50年、人を大切にすることを一番に診療し続け、協会や医師会などの活動にも積極的に関わってきました。
医師になって50年、人を大切にすることを一番に診療し続け、協会や医師会などの活動にも積極的に関わってきました。多忙な毎日の中、若いころから、釣りやゴルフなど、夫と一緒にさまざまなことにも挑戦してきましたが、50年間変わらず続けているのがお茶です。京都で勤務時、武家手前の石州(せきしゅう)流の師匠につき、お稽古を重ね、お免状をいただきました。
紫雲庵(しうんあん)という庵号をいただき、自宅に茶室を作りました。診療が忙しくても、白衣を脱いで1時間だけでも座ると気分が変わります。
お茶は、味を楽しむのはもちろん、道具やお茶菓子なども工夫し、季節を感じ、ゆったりとした空間を味わうものです。何気ないお茶碗や茶道具など一つひとつにもこだわり、由来や歴史などを知るという楽しみもあります。
毎週木曜日の午後には、医院の職員にお稽古をつけています。教室を始めてから、職員が着付けを習ってきてくれて、着物を着てお稽古するようになりました。普段はばたばたと医院内を走り回っていても、この時間だけは皆で座って、静かな時間を過ごします。
教室ももう20年続いています。皆が長く働いてくれているからで、嬉しいですね。結婚し子どもができても、ずっと勤め続けてくれます。子どもの患者さんが親になり、10年ぶりに来院されても、見慣れた顔を見て安心されます。職員は大切な存在だと実感します。お茶も診療も続けられたのは、たくさんのご縁や出会いに支えられたからこそです。人と向き合い大切にしなければと強く思います。
協会は、先生方が顔をつきあわせて議論しあうのがいいところ。若い先生にもどんどん活動にご参加いただきたいです。
女性の先生の活躍も期待します。医学部も女性が3分の1という時代なのに、出てこられる先生が少ないように思います。会議や研究会中に子どもを預かってくれるとか文化行事を増やすとか、協会にも工夫してもらえればいいですね。