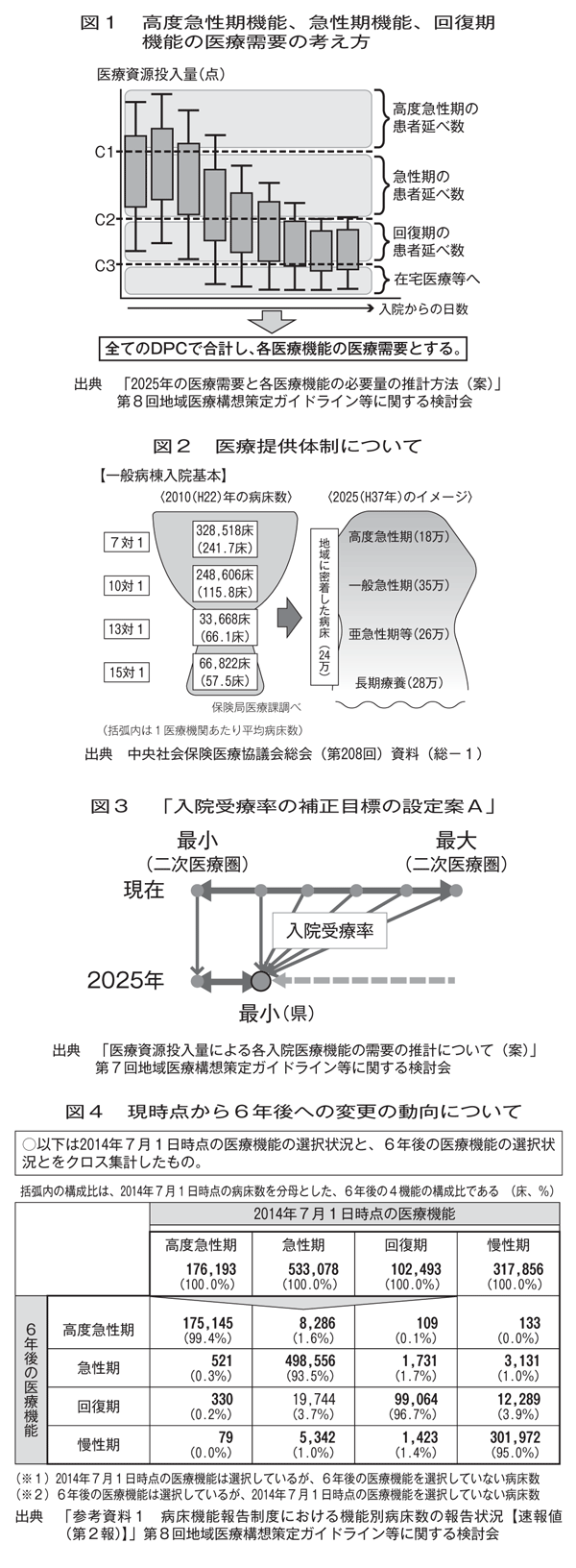2015年3月15日(1777号) ピックアップニュース
統一地方選特集 政策解説(上)
強制的な病床削減をねらう 「地域医療構想」
4月12日と26日に投開票予定の第18回統一地方選挙にあたって、今号より地方自治体が深く関わる医療、社会保障制度について3回に分けて解説する。第1回目は、医療・介護総合法で都道府県に策定が義務付けられた「地域医療構想」について取り上げる。
厚労省の「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会(以下、検討会)」で示された「地域医療構想策定ガイドライン(案)(以下、ガイドライン案)」では、構想策定のプロセスとして、現在の2次医療圏を基本に構想区域を定め、その区域ごとに高度急性期、急性期、回復期、慢性期、それぞれの医療需要の将来推計を算出、それに合わせた必要病床数を算出するとしている。また、構想策定後は、医療機関の自主的な取り組みや基金の活用を通じて、将来の必要病床数と現状の病床数の乖離を埋めるとしている。なお、現状の病床数の把握には、医療・介護総合法で改定された医療法で新たに設けられた病床機能報告制度を利用するとしている。病床機能報告制度とは、病床を有する病院・診療所が、担っている医療機能の現状と今後の方向を都道府県に報告する仕組みのことである。
第1に医療需要の将来推計が本当に、地域住民のニーズを反映したものになるのかという点である。
「ガイドライン案」では、医療需要の将来推計について「平成25(2013)年度のDPCデータ及びNDBのレセプトデータに基づき、住所地別に患者を配分した上で、構想区域ごとの性年齢階級別...」(に)、「行われた診療行為を診療報酬の出来高点数で換算し」、「入院から医療資源投入量が落ち着く段階までの患者数を、高度急性期及び急性期の患者数とし、急性期と回復期とを区分する境界点を、○点として推計を行う」などとしている。つまり、地域、疾患、年齢、性別ごとに、入院から退院まで1日にかかった医療費を経過日数順に並べ、病床機能毎に境界線を引き(C1=3000点・C2=600点・C3=225点・入院基本料等を除く)、その境界線の中にいる患者数を対象の人口で割って受療率を算出。その受療率を将来の人口推計に乗じて、地域、疾患、病床機能ごとの将来の患者数を算出するということである(図1)。
厚労省はすでに「検討会」の中で、政府が発表している病床削減方針を示しながら、「具体的には、やはり改革の方向性というものは維持しつつ、この推計方法がいかに説得性のあるものであるのかということについて御議論いただきたい」と、病床削減の方向性を既定路線として、医療需要の推計方法を議論するように釘を刺している。
しかし、この病床削減計画は全く現実的でない。これから高齢者がますます増え、入院患者も大幅に増える。こうした中、患者を現在と同じように入院させるためには、厚労省の推計でも現在107万床ある一般病床を129万床に増やさなければ対応できないとされている。
もし、このまま急性期病床の削減が強行されれば、急性期医療を受けられない患者が続出する一方、病院には急性期病床を維持するために在院日数の短縮が求められるが、それを7対1や10対1で行えば、医療現場の労働強化は大変なものになる。
たった10年でそこまで在宅医療を充実させることなどできるのだろうか。
日医総研が2013年に行った「在宅医療についての郡市区医師会アンケート調査」では、「在宅医療を進めるために重要かつ困難な項目」として、「在宅医療を担う医師の確保」が最も多く35.3%、次いで「後方支援病床の確保」が23.9%となっている。また、同様に日医総研が全国1931の200床以下の病院を対象に行った「病院の在宅医療機能および退院支援に関する実態調査」では、在宅療養患者の受け入れについて「常に受け入れできる」と回答した病院は17.6%しかなかった。
つまり在宅医療を充実させるためには、医師の確保とともに後方支援病床の確保が必要であるが、すでに、多くの病院で病床に空きがなく、救急の際、在宅患者を受け入れることができないのである。
こうした現状を無視して、強引な誘導で「在宅医療等を増やせば急性期病床を削減できる」との考えは、あまりに実態からかけ離れている。
つまり、地域医療構想調整会議で都道府県は、療養病床を持つ民間病院に対して病床を放棄し、患者を在宅に移すよう要請することができるだけでなく、従わない場合は管理者の変更命令までも出すことができるということである。
これは、事実上、都道府県による民間病院の管理である。これまで民間病院は国の低医療費政策の下で、地域の医療ニーズになんとか応えてきた。こうした努力をないがしろにして、何の経営的な担保もせずに、無理矢理、病床機能の転換や病床削減をさせれば、立ちゆかなくなる病院が発生することも考えられる。
すでに運用されている、病床機能報告制度の集約結果(図4)を見ると、ほとんどの医療機関が6年後も現在と同様の機能を維持すると回答している。つまり高度急性期・急性期病床が6割強を占める現況と変わらないのである。これらの回答は、政府が描く将来の各医療機能の必要病床数と大きく乖離しており今後、都道府県による民間病院への病床転換や病床削減要請が頻発する可能性もある。
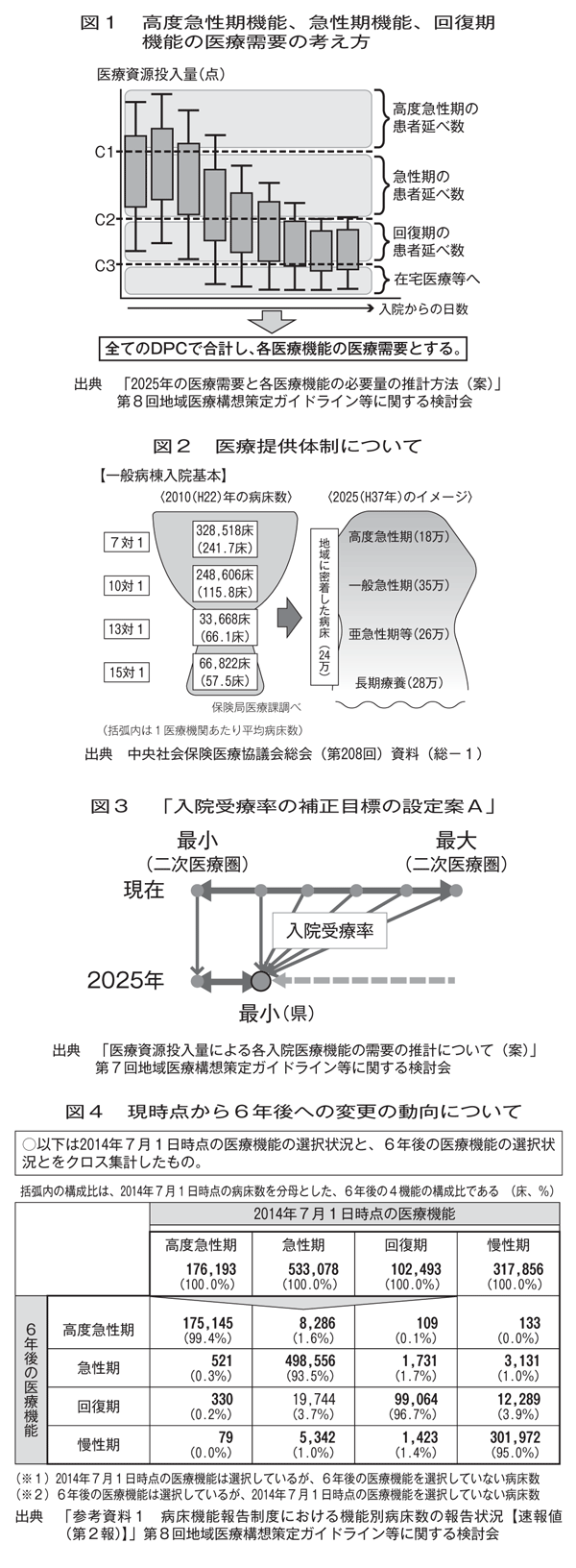
「地域医療構想」とは
医療・介護総合法による医療法改定で、都道府県は医療計画として、「地域医療構想」、「構想区域における病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量」などを定めるとされた。厚労省の「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会(以下、検討会)」で示された「地域医療構想策定ガイドライン(案)(以下、ガイドライン案)」では、構想策定のプロセスとして、現在の2次医療圏を基本に構想区域を定め、その区域ごとに高度急性期、急性期、回復期、慢性期、それぞれの医療需要の将来推計を算出、それに合わせた必要病床数を算出するとしている。また、構想策定後は、医療機関の自主的な取り組みや基金の活用を通じて、将来の必要病床数と現状の病床数の乖離を埋めるとしている。なお、現状の病床数の把握には、医療・介護総合法で改定された医療法で新たに設けられた病床機能報告制度を利用するとしている。病床機能報告制度とは、病床を有する病院・診療所が、担っている医療機能の現状と今後の方向を都道府県に報告する仕組みのことである。
将来の医療ニーズ推計
しかし、ここには多くの問題点がある。第1に医療需要の将来推計が本当に、地域住民のニーズを反映したものになるのかという点である。
「ガイドライン案」では、医療需要の将来推計について「平成25(2013)年度のDPCデータ及びNDBのレセプトデータに基づき、住所地別に患者を配分した上で、構想区域ごとの性年齢階級別...」(に)、「行われた診療行為を診療報酬の出来高点数で換算し」、「入院から医療資源投入量が落ち着く段階までの患者数を、高度急性期及び急性期の患者数とし、急性期と回復期とを区分する境界点を、○点として推計を行う」などとしている。つまり、地域、疾患、年齢、性別ごとに、入院から退院まで1日にかかった医療費を経過日数順に並べ、病床機能毎に境界線を引き(C1=3000点・C2=600点・C3=225点・入院基本料等を除く)、その境界線の中にいる患者数を対象の人口で割って受療率を算出。その受療率を将来の人口推計に乗じて、地域、疾患、病床機能ごとの将来の患者数を算出するということである(図1)。
目的は病床削減
「検討会」では、機能区分ごとの将来の病床数の必要量について、このように一見科学的、中立的な手法をとるとしている。現状では、3000点以上を高度急性期、600点以上を急性期、225点以上を回復期とする案が明らかにされているが、本質は将来にわたって厚労省の線引き次第でどのようにも各病床数を設定することができるということである。そのため、最終的には7対1病床を2025年までに現在の36万床から18万床に減らすなどとした政府の病床削減方針(図2)に沿ったものになる危険性もある。厚労省はすでに「検討会」の中で、政府が発表している病床削減方針を示しながら、「具体的には、やはり改革の方向性というものは維持しつつ、この推計方法がいかに説得性のあるものであるのかということについて御議論いただきたい」と、病床削減の方向性を既定路線として、医療需要の推計方法を議論するように釘を刺している。
しかし、この病床削減計画は全く現実的でない。これから高齢者がますます増え、入院患者も大幅に増える。こうした中、患者を現在と同じように入院させるためには、厚労省の推計でも現在107万床ある一般病床を129万床に増やさなければ対応できないとされている。
もし、このまま急性期病床の削減が強行されれば、急性期医療を受けられない患者が続出する一方、病院には急性期病床を維持するために在院日数の短縮が求められるが、それを7対1や10対1で行えば、医療現場の労働強化は大変なものになる。
さらに進む受け皿なき在宅誘導
「ガイドライン案」では、「退院して在宅医療等を受ける患者数を何らかの方法により推計する必要がある」とされている。また、「検討会」で示された「2025年の医療需要と各医療機能の必要量の推計方法(案)」では、「慢性期の医療需要については、...現在では療養病床で入院している状態の患者のうち一定数は、2025年には、在宅医療等で対応するものとして推計する」「どの程度...在宅医療・介護施設で対応するかについて、目標を定める」としており、「目標としては、現在、療養病床の入院受療率に地域差があることを踏まえ、この差を縮小(させる)」との提案までしている。これは、診療報酬が包括算定となっており、急性期や回復期などのような手法で推計が行えない慢性期病床については、在宅への移行を前提として、全ての2次医療圏の入院受療率を全国最小レベルまで低下させるということである(図3)。もしこの案が採用されれば、現在療養病床の受療率が人口10万人当たり953.4人と最も高い高知県の幡多医療圏を長野県の人口10万人当たり122人に合わせることになり、これまで療養病床に入院していた人のうち、10人中9人は入院できなくなるということである。兵庫県下でも淡路医療圏では10人中8人は在宅などに移行するということになる。たった10年でそこまで在宅医療を充実させることなどできるのだろうか。
日医総研が2013年に行った「在宅医療についての郡市区医師会アンケート調査」では、「在宅医療を進めるために重要かつ困難な項目」として、「在宅医療を担う医師の確保」が最も多く35.3%、次いで「後方支援病床の確保」が23.9%となっている。また、同様に日医総研が全国1931の200床以下の病院を対象に行った「病院の在宅医療機能および退院支援に関する実態調査」では、在宅療養患者の受け入れについて「常に受け入れできる」と回答した病院は17.6%しかなかった。
つまり在宅医療を充実させるためには、医師の確保とともに後方支援病床の確保が必要であるが、すでに、多くの病院で病床に空きがなく、救急の際、在宅患者を受け入れることができないのである。
こうした現状を無視して、強引な誘導で「在宅医療等を増やせば急性期病床を削減できる」との考えは、あまりに実態からかけ離れている。
都道府県による強制的な病床削減
「ガイドライン案」では、「地域医療構想調整会議を設け、...将来の病床数の必要量を達成するため...に必要な協議を行う」とされており、例として、「療養病床について在宅医療等への転換を進める」ことなどが上げられている。また、「関係者の合意事項の履行を担保するため、都道府県知事は、公的医療機関等への不足している医療機能に係る医療の提供等の指示(公的医療機関等以外の医療機関には要請)を講ずる」とされており、「公的医療機関等以外の医療機関が、正当な理由がなく、要請に従わない場合には勧告を、...勧告等にも従わない場合には医療機関名の公表、地域医療支援病院・特定機能病院の不承認又は承認取消し、管理者の変更命令等の措置を講ずることができる」とされている。つまり、地域医療構想調整会議で都道府県は、療養病床を持つ民間病院に対して病床を放棄し、患者を在宅に移すよう要請することができるだけでなく、従わない場合は管理者の変更命令までも出すことができるということである。
これは、事実上、都道府県による民間病院の管理である。これまで民間病院は国の低医療費政策の下で、地域の医療ニーズになんとか応えてきた。こうした努力をないがしろにして、何の経営的な担保もせずに、無理矢理、病床機能の転換や病床削減をさせれば、立ちゆかなくなる病院が発生することも考えられる。
すでに運用されている、病床機能報告制度の集約結果(図4)を見ると、ほとんどの医療機関が6年後も現在と同様の機能を維持すると回答している。つまり高度急性期・急性期病床が6割強を占める現況と変わらないのである。これらの回答は、政府が描く将来の各医療機能の必要病床数と大きく乖離しており今後、都道府県による民間病院への病床転換や病床削減要請が頻発する可能性もある。
住民本意の県政に
医療提供体制の強引な改悪を止めさせるためには、政府に働きかけることはもちろん大切である。しかし、それだけではなく、今回の計画では、地域医療構想は都道府県が策定するとされているし、病床機能の転換を要請する権限も知事にあるため、都道府県の立場をいかに、地域住民本位のものにするのか、という点も大切である。これまで、兵庫県は国の「公立病院改革ガイドライン」に則って、「県行革」の一環として、県立塚口病院の統廃合や、但馬地域での病床の集約を行ってきた。こうした県の立場では、今回の医療提供体制の改悪も国のいいなりに進められる可能性が高い。今回の統一地方選挙を絶好の機会ととらえて、国のいいなりに病床削減を進める地方政治ではなく、国の計画から、地域住民や医療関係者を守ることのできる地方政治を実現するために、各政党、候補者の政策を問い、慎重に選択する必要がある。