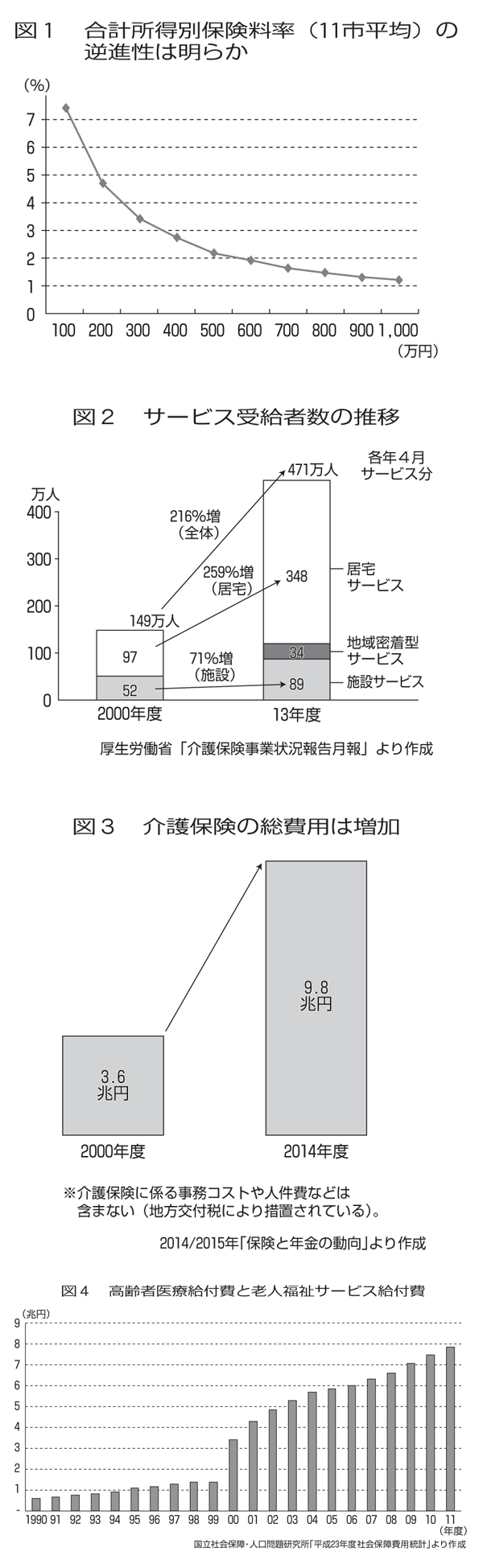2015年6月05日(1784号) ピックアップニュース
政策解説 介護保険料はなぜ高いのか
−低所得者ほど負担が重い保険料の逆進性
介護保険料の第6期改定が行われ、保険料の引き上げが大きな問題になっている。厚労省によれば全国平均月額5514円で、2000年の制度発足時の2911円から、15年間でほぼ倍増している。「高齢者が増えているのだから仕方がない」とあきらめる声も少なくないが、実は、介護保険料には低所得者ほど負担が重い逆進性があることはあまり知られていない。介護保険の財源問題として、介護保険料の仕組みと逆進性について解説する。
1号被保険者の特異な保険料構造を明らかにするために、まず2号被保険者の保険料について確認しておきたい。
2号被保険者は、健康保険に加入する40歳から64歳までの被保険者本人である。2号被保険者の人数に応じて保険料の総額が算出され、介護納付金として支払基金に支出される。しかし、2号被保険者個人が負担する保険料は、人数割りされた金額ではない。納付金の総額を、加入者全体の標準報酬総額で割って、標準報酬に対する保険料率を算出し、個々人の標準報酬に応じた保険料としている。
例えば協会けんぽでは、標準報酬月額に対する介護保険の保険料率は0.86%(事業主負担含めて1.72%)である。標準報酬月額表(表1)を見れば、月額10.4万円の場合の介護保険料は895円。標準報酬月額が10倍の103万円になると、介護保険料も10倍の8858円になる。報酬月額が変わっても保険料率は同じで、標準報酬に10倍の格差があれば、介護保険料も10倍の格差となる仕組みである。
ところが、1号被保険者はそうではない。1号被保険者の保険料計算は「段階別定額保険料」方式と呼ばれるもので、これは保険料総額を1号被保険者数の人数で割って得られた額を「基準保険料」としている。「基準保険料」は人数割であるから、加入者の所得と基準保険料との間には、何の関係もなく、加入者の経済状況は一切反映されていない。
ただし、加入者は合計所得別に「段階」に分けられ、「段階」ごとに「基準保険料」に積算する調整倍率が設定されている。高所得者には1.5倍、低所得者には0.5倍など、傾斜配分する仕組みである。一見、所得の多寡に応じているように見えるが、高所得者の分類は、国基準で「合計所得190万円未満」と「同以上」の2枠しかなく、調整倍率の範囲も1.5倍にすぎない。つまり、合計所得が190万円以上は、1千万円でも、1億円でも、保険料はすべて同額で、しかも人数割基準保険料のわずか1.5倍にすぎない。従って、所得に対する実質的な保険料率は、所得が上がるほど減少する。
ただし、「段階」は市町が独自に決めることができる。そこで兵庫県下の実例を示そう。紙面の都合から、表2で神戸市の課税所得者に対する「段階」を示した。神戸市は、最高段階を「1000万円以上」とし、調節倍率を2.5倍まで引き上げ、所得が少ない人ほど負担が重くなる逆進性を緩和しようとする工夫がみられる。しかし、こうした自治体の努力にもかかわらず、逆進性の緩和はきわめて限定的である。
県南部の尼崎市から赤穂市までの11市について、合計所得金額が100万円の場合から1千万円の場合まで100万円きざみで、それぞれに対する保険料率を算出した(表3)。
その結果、11市すべてで「合計所得100万円」の場合の保険料率が最も高く、最高は尼崎市の8.53%で、なんと介護保険料だけで合計所得の1割近いという実態が明らかになった。一方、合計所得が高くなるほど保険料率は下がり、「1000万円」で最も保険料率が低かったのは相生市で、わずか1.02%であった。
「段階」の設定の仕方は、自治体により異なるが、逆進性については、ほぼ同じ傾向が示された。11市の平均値では(図1)、合計所得100万円に対する保険料率は7.5%、同1千万円に対する保険料率は1.31%で、格差は約6倍であった。これが所得に応じた負担と言えるだろうか。
生活保護受給者などの非課税所得者の負担もきわめて重い。非課税所得者は基準保険料の半額などの設定で、一見、負担が軽減されているように見える。しかし、協会けんぽの2号被保険者と比較すれば負担の重さが際立つ。生活保護受給者等を対象にした第1段階の保険料月額は、11市平均で2500円だが、2号被保険者で近似値を探す(表1)と、標準報酬月額30万円に相当する。所得がゼロの非課税所得者が、月収30万円程度で働く勤労者並みの介護保険料を課されているのである。
多くの自治体が逆進性緩和に努力しているものの、段階別定額保険料方式を変更しない限り、焼け石に水と言わざるを得ない実態となっている。
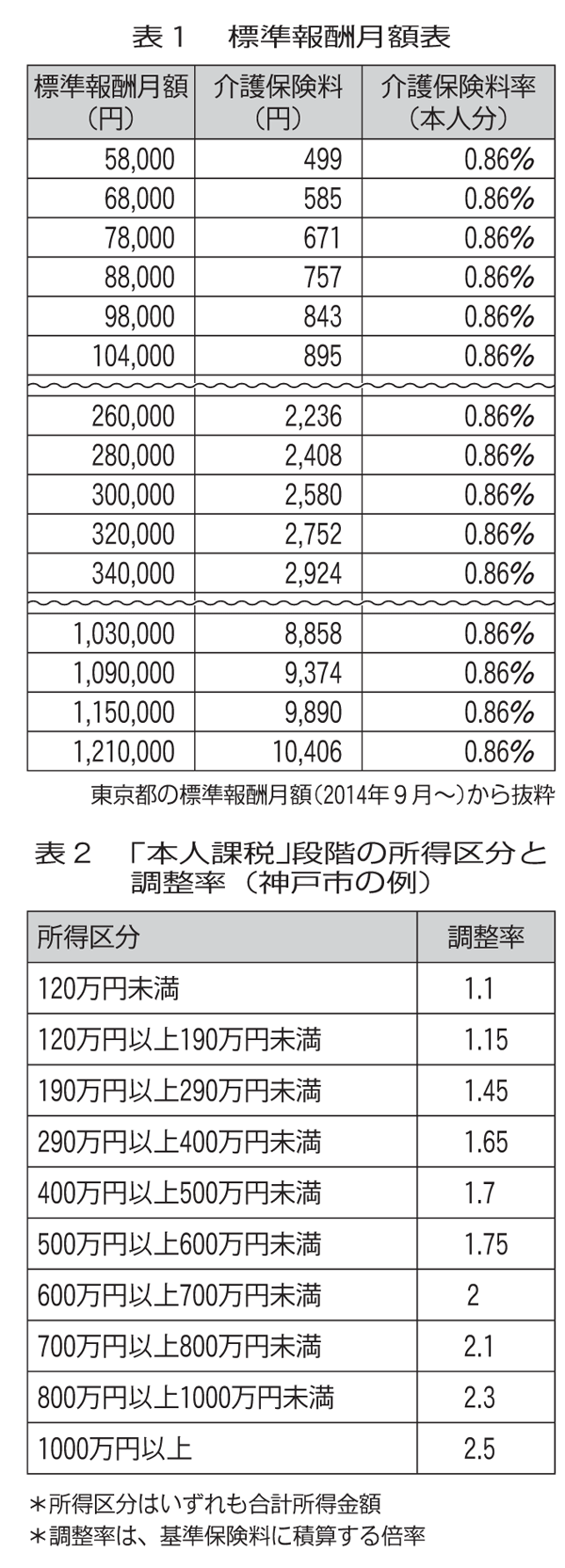 下記画像をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。
下記画像をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。
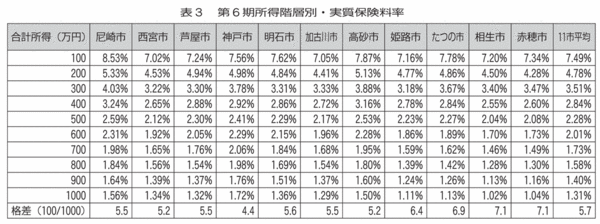
介護保険が出発した2000年度の老人福祉サービス費は3.4兆円に急増しているが、介護保険での国庫負担はそのうちの25%であるから、粗計算すると国が負担したのは8500億円ということになる。国は介護保険制度の創設によって、1.4兆円から8500億円へと、5500億円も国庫負担を削減した格好なのである。
2016年度予算でみても、介護給付費9兆2669億円に対して、国庫負担は1兆6680億円で、措置制度時代の1.4兆円と比べても、わずか2700億円の増にすぎない。「介護の社会化」といいながら、低水準の国庫負担を維持したまま、安上がりの介護保険制度を追求してきた政府の姿が浮かびあがる。
総費用の増加が、保険料負担増の一因であることは間違いない。しかし、介護サービスの需要増との関係では、介護現場の人手不足が指摘されているように、むしろ介護報酬が追い付いていないのである。
保険料の応能負担原則の強化と適切な国庫負担で介護保険の財源を確保し、介護報酬を引き上げてサービスの提供体制を拡充することが求められている。
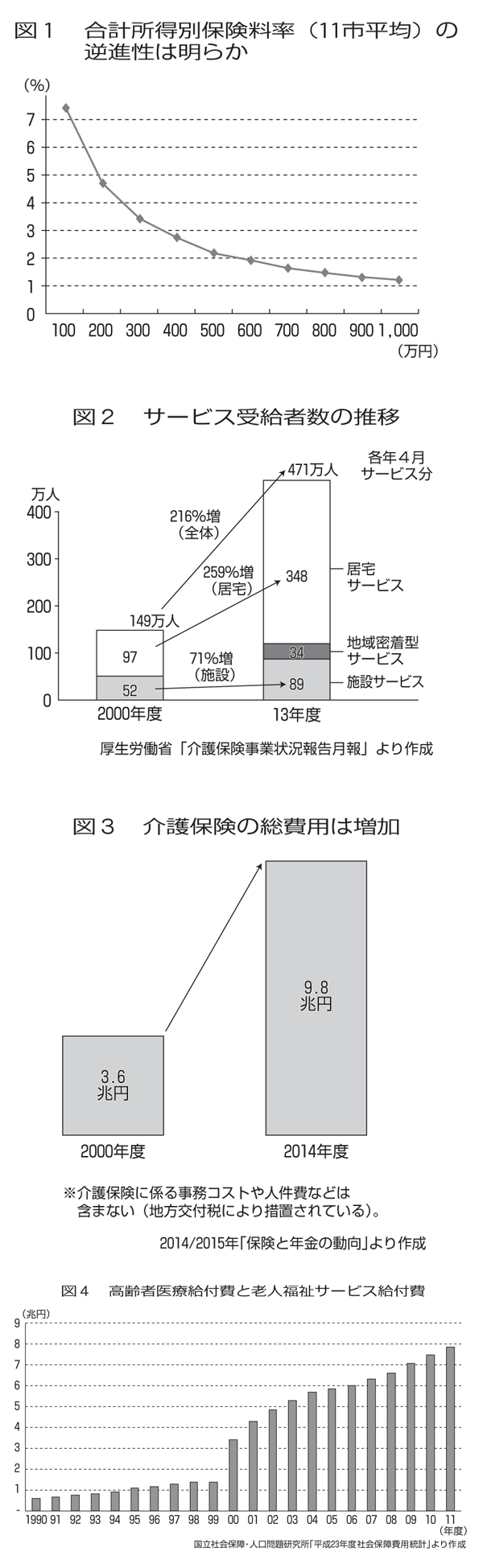
実質保険料率の格差は6倍
介護保険料の構造は、65歳以上の1号被保険者と65歳未満の2号被保険者では大きく異なる。1号被保険者の特異な保険料構造を明らかにするために、まず2号被保険者の保険料について確認しておきたい。
2号被保険者は、健康保険に加入する40歳から64歳までの被保険者本人である。2号被保険者の人数に応じて保険料の総額が算出され、介護納付金として支払基金に支出される。しかし、2号被保険者個人が負担する保険料は、人数割りされた金額ではない。納付金の総額を、加入者全体の標準報酬総額で割って、標準報酬に対する保険料率を算出し、個々人の標準報酬に応じた保険料としている。
例えば協会けんぽでは、標準報酬月額に対する介護保険の保険料率は0.86%(事業主負担含めて1.72%)である。標準報酬月額表(表1)を見れば、月額10.4万円の場合の介護保険料は895円。標準報酬月額が10倍の103万円になると、介護保険料も10倍の8858円になる。報酬月額が変わっても保険料率は同じで、標準報酬に10倍の格差があれば、介護保険料も10倍の格差となる仕組みである。
ところが、1号被保険者はそうではない。1号被保険者の保険料計算は「段階別定額保険料」方式と呼ばれるもので、これは保険料総額を1号被保険者数の人数で割って得られた額を「基準保険料」としている。「基準保険料」は人数割であるから、加入者の所得と基準保険料との間には、何の関係もなく、加入者の経済状況は一切反映されていない。
ただし、加入者は合計所得別に「段階」に分けられ、「段階」ごとに「基準保険料」に積算する調整倍率が設定されている。高所得者には1.5倍、低所得者には0.5倍など、傾斜配分する仕組みである。一見、所得の多寡に応じているように見えるが、高所得者の分類は、国基準で「合計所得190万円未満」と「同以上」の2枠しかなく、調整倍率の範囲も1.5倍にすぎない。つまり、合計所得が190万円以上は、1千万円でも、1億円でも、保険料はすべて同額で、しかも人数割基準保険料のわずか1.5倍にすぎない。従って、所得に対する実質的な保険料率は、所得が上がるほど減少する。
ただし、「段階」は市町が独自に決めることができる。そこで兵庫県下の実例を示そう。紙面の都合から、表2で神戸市の課税所得者に対する「段階」を示した。神戸市は、最高段階を「1000万円以上」とし、調節倍率を2.5倍まで引き上げ、所得が少ない人ほど負担が重くなる逆進性を緩和しようとする工夫がみられる。しかし、こうした自治体の努力にもかかわらず、逆進性の緩和はきわめて限定的である。
県南部の尼崎市から赤穂市までの11市について、合計所得金額が100万円の場合から1千万円の場合まで100万円きざみで、それぞれに対する保険料率を算出した(表3)。
その結果、11市すべてで「合計所得100万円」の場合の保険料率が最も高く、最高は尼崎市の8.53%で、なんと介護保険料だけで合計所得の1割近いという実態が明らかになった。一方、合計所得が高くなるほど保険料率は下がり、「1000万円」で最も保険料率が低かったのは相生市で、わずか1.02%であった。
「段階」の設定の仕方は、自治体により異なるが、逆進性については、ほぼ同じ傾向が示された。11市の平均値では(図1)、合計所得100万円に対する保険料率は7.5%、同1千万円に対する保険料率は1.31%で、格差は約6倍であった。これが所得に応じた負担と言えるだろうか。
生活保護受給者などの非課税所得者の負担もきわめて重い。非課税所得者は基準保険料の半額などの設定で、一見、負担が軽減されているように見える。しかし、協会けんぽの2号被保険者と比較すれば負担の重さが際立つ。生活保護受給者等を対象にした第1段階の保険料月額は、11市平均で2500円だが、2号被保険者で近似値を探す(表1)と、標準報酬月額30万円に相当する。所得がゼロの非課税所得者が、月収30万円程度で働く勤労者並みの介護保険料を課されているのである。
多くの自治体が逆進性緩和に努力しているものの、段階別定額保険料方式を変更しない限り、焼け石に水と言わざるを得ない実態となっている。
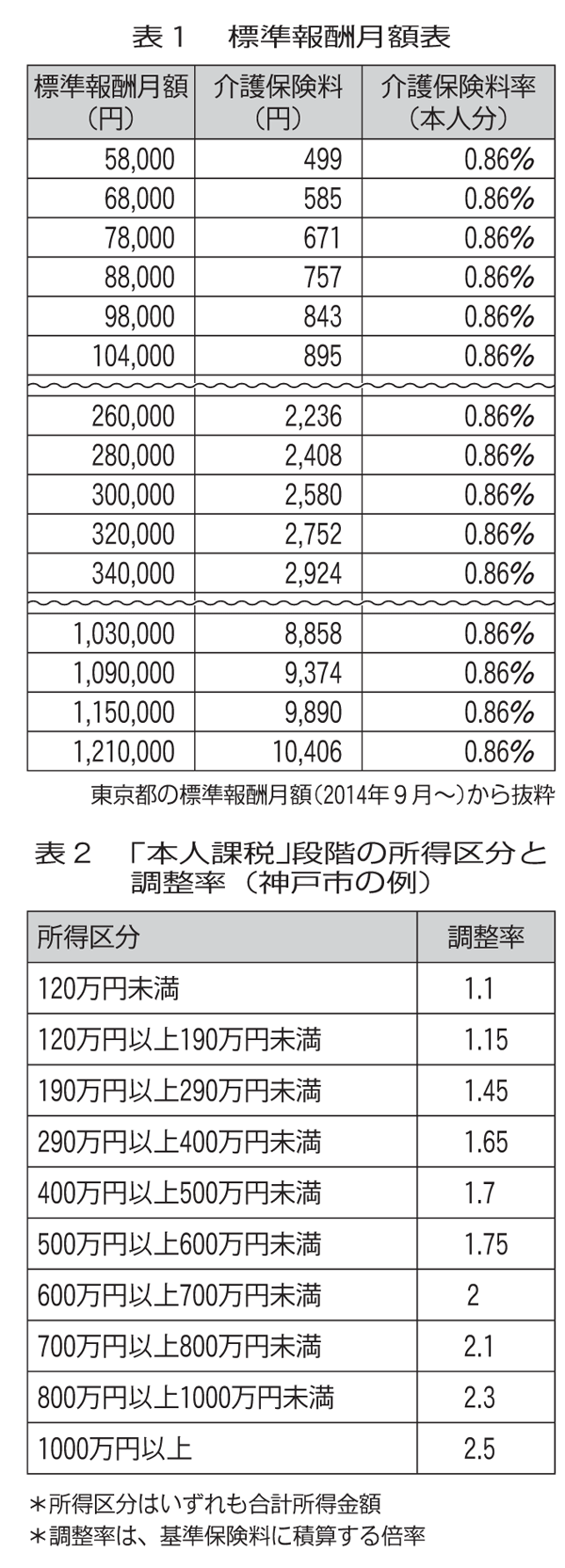 下記画像をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。
下記画像をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。
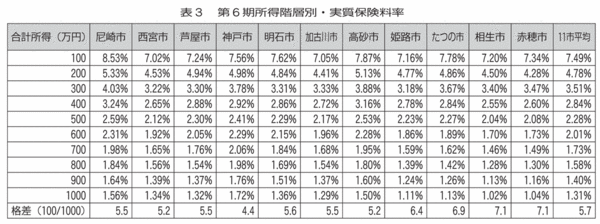
低すぎる国庫負担率
もう一つ、国庫負担の低さが、財源としては最も重要な問題である。介護保険が創設される以前の介護サービスは、老人福祉サービスとして行われ、1999年度で約1.4兆円であった(図4)。これは措置費であり、全額が国庫負担である。介護保険が出発した2000年度の老人福祉サービス費は3.4兆円に急増しているが、介護保険での国庫負担はそのうちの25%であるから、粗計算すると国が負担したのは8500億円ということになる。国は介護保険制度の創設によって、1.4兆円から8500億円へと、5500億円も国庫負担を削減した格好なのである。
2016年度予算でみても、介護給付費9兆2669億円に対して、国庫負担は1兆6680億円で、措置制度時代の1.4兆円と比べても、わずか2700億円の増にすぎない。「介護の社会化」といいながら、低水準の国庫負担を維持したまま、安上がりの介護保険制度を追求してきた政府の姿が浮かびあがる。
介護保険の財源は応能負担でこそ
介護保険は、高齢人口の増加とともに、「介護の社会化」を名目に、家庭内に潜在していた介護ニーズを介護保険の対象サービスとして需要を掘り起こし、顕在化させてきた。介護サービス受給者数は、発足時の2000年度(4月サービス分)149万人から、2013年度同471万人へと、3.2倍に増加した(図2)。一方、総費用は同期間に3.6兆円から9.8兆円へと2.7倍増となっている(図3)。総費用の増加が、保険料負担増の一因であることは間違いない。しかし、介護サービスの需要増との関係では、介護現場の人手不足が指摘されているように、むしろ介護報酬が追い付いていないのである。
保険料の応能負担原則の強化と適切な国庫負担で介護保険の財源を確保し、介護報酬を引き上げてサービスの提供体制を拡充することが求められている。