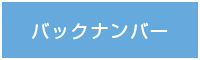2017年8月05日(1853号) ピックアップニュース
特別インタビュー 熊本地震被災地は今 中小病院への支援充実を
熊本市・本庄内科病院 本庄 弘次先生

【ほんじょう こうじ】1960年生まれ。87年聖マリアンナ医大卒業、89年開業。熊本県保険医協会常任理事
精神的ケアが被災者の課題
森岡 先生には、昨年8月に神戸で行った日常診療経験交流会プレ企画などでも、震災直後の経験や教訓などについてお話いただきました。本日は、1年以上経った現状と新たに生まれている課題などについて、お話をうかがえたらと思います。
本庄 地震後の対応で兵庫の先生方には、本当にお世話になりました。
余震によりまだこれから倒壊する可能性のある建物も残ってはいますが、現在の熊本は、社会機能はほぼ復旧したと言っていいと思います。被災者の課題は、急性期から慢性期のものに移行しており、一番問題となるのはメンタルヘルスです。
実は当院の職員も、地震を経験した職場にいたくないと、2名ほど退職しました。地震直後は、当時の映像を見て防災の勉強会ができたのですが、今やろうとするとかえって、職員の中に抵抗感があります。やっと忘れたのに、という感覚があるようです。ストレスチェックを実施したところ、職員の有所見率が18%もありました。
森岡 被災者は、どのような状況におかれているのでしょうか。
本庄 家族と仮設住宅に入居している職員と話をすると、いつも明るく仕事をしていますが、壊れてしまった住居をどこにどう再建するのか、展望が全く立っておらず、大変な状況のようです。また、避難所は解消され、復興住宅も徐々に完成していますが、入居先が近所の人と離れてしまうという問題が起こっています。市営住宅やアパートに入居した患者さんを往診していても、なじみのコミュニティから離れ、孤立してしまっており、厳しい状況です。
孤立の結果として、従来からあった孤独死の問題が顕在化してきています。50歳代の独居男性のアルコール依存、孤独死が多くなっています。政府に陳情しても国は孤独死を高齢化社会の結果として、あまり問題視していません。
森岡 コミュニティの大切さは、阪神・淡路大震災の時から大きな問題になっていましたが、まだ同じ問題が熊本でも繰り返されているのですね...。
本庄 そんな中、患者窓口負担の免除措置が昨年9月で打ち切られようとしていたのですが、保団連や協会の要望もあって、延長されて、非常に助かっています。

聞き手 森岡芳雄副理事長
医療政策の矛盾地震で拡大
森岡 医療体制についてはいかがでしょうか。熊本市民病院、熊本日赤病院という二大基幹病院をはじめ、多くの医療機関が被害を受ける中、先生の病院も、スプリンクラーが誤作動し大変な目に遭われました。本庄 当院は、地震で建物が傾き病室の窓が落下した上、スプリンクラーにより院内が水浸しになり、天井が抜け落ちたりしました。1度目の地震のあと、職員が入院患者さんをすべて廊下に移してくれていたので、幸い患者さんは皆無事だったのですが、夜間のことでもあり、とにかく人手が足りずに苦労しました。
熊本地震では、医療についてはうまくいったと言われていますが、それはDMATとJMATが入った避難所と基幹病院の話です。地震直後の医療体制を支援していただき大変ありがたかったのですが、われわれ中小病院には残念ながら、公的支援は全くありませんでした。医師会もほとんど動いてくれず、それぞれの病院独自で、避難してきた人とともに、被災直後を乗り切ることになりました。介護職が必要だったのですが、介護士会との情報共有ができず、全国からたくさん来てくださった介護職のボランティアが何もされないまま帰られるという状況もありました。

本庄内科病院。建物の一部(写真右側)が地震被害を受け、建て直された
本庄 それを痛感しました。阪神・淡路大震災、東日本大震災の後、一通りの防災意識は持っておりましたが、まさか熊本が被災するとは思ってもみなかったので、充分な対応策がとれてはいなかったですね。
現在、深刻だと感じるのは、地震後、転院して県外などに出ていった高齢の患者さんが熊本に帰ってこないことです。中小病院にとっては厳しい患者減です。
福島のように地域産業に致命的なダメージがあったわけではありません。特にもともと老健などの介護施設に入所されていた方が、住宅を失ったことで同じ施設に戻れず、サービス付き高齢者住宅(サ高住)に入居しなければならなくなり、毎月十数万円の負担が発生するので、経済的な事情で帰れず、そのまま転居先や子ども、親族のもとに残るといったケースが多いようです。
また、医療が充分に提供されないようなサ高住に要介護度の高い方が入居したりして、肺炎や尿路感染などを起こして、すぐ再入院するケースが多く見受けられます。そういったケースにはわれわれの目も充分に行き届かないので、充分な医療が受けられているのか、大変不安を感じています。
森岡 医療・介護制度の負担増や施設整備の問題点によるしわ寄せが、経済格差を伴って震災でより顕著に表れているということですね。次年度に医療と介護の診療報酬改定をひかえ、ますます危うい状況と言えますね。
本庄 その通りです。地域医療計画も地震後変更されるかと思っていましたが、逆に病床削減を進めていくような状況です。
さらに、地震で大きな被害を受けた熊本市民病院は、病院黒字化のために地域包括ケア病棟をつくるという計画が出ており、周辺の中小病院の役割を奪うと問題になっています。市民病院に求められているのは、NICUなど基幹病院としての重要な機能の復旧です。
森岡 基幹病院が地域医療での役割を果たさず、目先の収支を求めるのは大問題です。
本庄 もう一点、被災者の方を診ていると、かかりつけ医の役割の重要性を感じます。被災者の抱える疾病、問題は一つではありません。それをかかりつけ医として診ることができているのだろうかという思いがあります。
森岡 開業医の先生方は、専門領域を持った上で、さまざまな疾患を診るよう研鑽を積んでおられます。それぞれが総合医であり、かかりつけ医であり、連携し合って地域医療を支えているのが、今の日本の地域医療だと私は日ごろ感じています。
だから現在、専門医の中に「総合診療医」をつくるという議論が進んでいるのには違和感があります。逆に、若い医師に、総合診療医でなければ特定の疾患だけ診たらいいと、間違った考えを植え付けてしまいかねないと思います。
本庄 災害時は特に、内科でも外傷処置など、何にでも対応する総合性が求められますね。
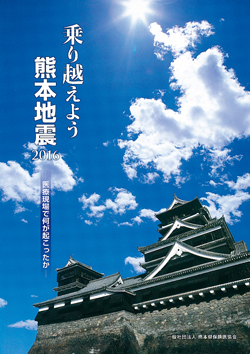
熊本県保険医協会が今年5月に発行した、地震の経験や教訓をまとめた記録集
震災の教訓をどうつなぐか
森岡 最後に、1年3カ月を振り返ってみて、阪神・淡路大震災、東日本大震災など、これまでの教訓の何が活かされ、何が活かされなかったとお感じになられますか。本庄 教訓が活かされたのは、ライフラインに関してです。電気は地震当日にすぐに復旧し、また、都市ガスの供給をすぐに止めたため、火事の発生が防止できました。
逆に一番問題だったのは情報共有です。全国から支援をいただき、大量の物資が届いていても、どこに何があるか誰も知らず、取りに行けない状況でした。情報対策ができてないと実感しました。窓口負担免除措置についても、皆、免除になると知らず、「避難所は薬が無料」という情報が流れて、避難所に人が詰めかける有様でした。
他にも、病院としての避難者の受け入れや職員への対応など、葛藤したことや学んだことがたくさんあります。熊本県保険医協会では、経験を伝えなければと昨年、記録集を発行しました(右上)。
森岡 大切な取り組みですね。地震は次に、いつどこで起こるか分かりませんし、長期的なたたかいになります。記録集の続編もつくっていただきたいと思います。
本庄 地震後、全国で経験をお話させていただく機会が増えましたが、もうあれ以上の地震はこないだろうと、逆に熊本の対策が一番遅れているように感じます。もっと積極的に行政も巻き込んで、次への備えを考える必要を感じています。
森岡 ありがとうございました。熊本でも20年以上前の阪神・淡路大震災と同じような問題が起こっていること、医療・介護の課題が震災でいっそう過酷な状況を生んでいることを教えていただきました。被災者の方々、医療機関の復興までまだまだ大変だと思います。兵庫協会も連帯していきたいと思います。