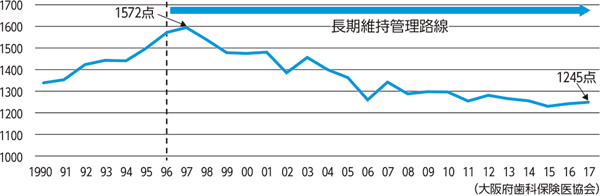2020年8月05日(1949号) ピックアップニュース
歯科政策研究会 宇佐美宏先生講演録
国民と医療者が手を携え運動を

全国保険医団体連合会歯科代表・副会長
宇佐美 宏先生
【うさみ ひろし】1966年日本大学歯学部卒業。1970年千葉県松戸市で開業。全国保険医団体連合会理事を経て1996年から同副会長、2004年から同歯科代表。千葉県保険医協会副会長
歯科部会が6月21日、協会会議室で開催した歯科政策研究会「歯科保険診療の歴史から学ぶ~保険でより良い歯科医療の実現の課題~」の講演録を掲載する。
世界的に新型コロナウイルス感染が拡大し、多くの死者が出ている。特に影響を受けているのが、貧困層だ。アメリカや南米諸国など、格差が大きく、皆保険もない国では、感染拡大も甚大である。
日本も貧困と格差の問題は深刻である。労働者の賃金が大幅に減らされる一方、大企業の内部留保は、コロナ禍でも過去最高の488兆円に到達した。国中が危機に晒されている今こそ、医療関係者と患者・国民が共同して、医療改善運動に取り組むべきだ。
歯科医療を巡る厳しい現況
歯科医師数は総医師数の3割を占めるにもかかわらず、歯科医療費が公的医療費の総体に占める割合はわずか7%に過ぎない(図1)。2020年3月時点での歯科診療所数は6万8332施設だが、内訳をみると個人立診療所が減り、法人立診療所が増えており、経営的な厳しさが伺える。
厚労省が10人以上の事業所についてまとめている「賃金構造基本統計調査」(2012年版)によると、歯科医師の平均年収は679万円であり、1000万円をゆうに超える医師とは大きく乖離がある。都市部ではスタッフを雇わずに歯科医師1人が受付・治療などをすべてこなす「ワンオペ診療所」も増加している。保険診療での経営が難しいため、「完全自費治療」への移行を煽る報道も散見される。
さらにコロナ禍で出された、〝不要不急〟の歯科治療の延期を求める厚労省通知(4月6日)で、患者が激減した歯科医療機関は大きな打撃を受けている。マスコミからも「歯科医院は感染リスクが高い」などの歯科バッシングがなされ、歯科医療の経済的脆弱性がいっそう浮き彫りになった。
歯科医院が経済的に苦しい根本原因は、歯科の低診療報酬政策にある。医科と異なり歯科医療は、長年にわたり公的保険の中に、あまり取り入れられてこなかった。保険診療だけでは歯科医療機関経営が難しいため、自費診療で補完するという「トータルバランス論」も唱えられて久しい。現在でも厚労省交渉の場で、技官が「保険診療だけで歯科医院経営を支えるのは難しい」と公言するなど、診療報酬が低すぎることは、誰の目にも明らかである。
なぜ、現在の低診療報酬問題が引き起こされたのか。その歴史的経緯を紐解き、解決策を考えたい。
歯科診療報酬の歴史的経緯
1.50~60年代 国民皆保険成立とその影響
国民皆保険制度前夜の50年代前半には、指導・監査の嵐が吹き荒れ、悪名高い水野技官による不当な指導で自殺者も多数出た。
しかし58年には、現行の診療報酬体系の原型とも言える「新医療費体系」が施行された。「物と技術の分離」が議論され、甲表と乙表の2種類の点数表ができ、甲表を病院と歯科が、乙表を医科診療所が採用した。重要なのは、単価を1点10円に固定したことだ。戦前は、歯科は医科の半分の単価でしかも地域差があり、1点単価が固定されておらず、戦後しばらくその状態だったのが、医科・歯科同時に固定化されたことは画期的だった。
国民皆保険が61年に発足した。医科は「制限診療撤廃」という宣言を出し、保険診療を全面展開した。武見太郎日医会長(当時)は自由診療医だったが、「医学・医療の進歩は患者に等しく還元する」「医療全体は保険診療でなくては...」という考えを持っていた。その結果、医科では何十万点かの心臓大手術も保険診療の中でなされるようになった。
しかし、歯科では依然として欠損補綴の歯数制限や材料機器の制限など「制限診療」が横行した。それでも、歯科医療需要の顕在化や技術革新等によって医療費が急増し、大蔵省(当時)は医療費抑制策を強化する方針を固め、68年に「財政制度審議会」報告を提出している。そこでは「皆保険発足以降の医療費急増による財政再建の基本方向」として、以下の点を挙げている。
(1)保険給付に格差を設ける
(2)本人1割負担
(3)差額徴収認可
(4)療養費払い方式導入
これらを受けて翌69年、自民党は「国民医療対策大綱」を公表。この基本理念が、今日に続く疾病の「自己責任原理」「相互扶助」である。ここで早くも皆保険制度の見直しが打ち出された。当時、国鉄と米と健保の「3K赤字」キャンペーンがマスコミを賑わし、攻撃の対象となった。
2.70年代 日歯の脱保険路線と「51年通知」
70年代には日歯の脱保険路線が始まる。当時日歯が各県の歯科医師会に出した公式文書には「歯科は保険点数が低いので、差額徴収をどんどんやりなさい」「保険点数の2~3割を余分に患者から取りなさい...」とあった。こうしたことが読売新聞で暴露され、マスコミの「悪徳歯科医キャンペーン」が始まった。
当然社会的に大きな批判に晒され、1976(昭和 51)年には「保険で保存治療を終了した後の補綴は、保険診療と自費診療どちらで行うかは患者が選択できる」とする管理官通知(通称51年通知)によって差額徴収制度は撤廃されたが、一方で現在に続く保険と自費の混合診療は容認されることになった。また、厚労省は、歯科医師の自費診療への誘導にこの通知を巧みに運用してきた経緯がある。
3.80年代 臨調行革路線と「失われた16年」
80年代に始まった第2臨調(土光臨調)路線で、診療報酬改定に新たな財源を設けないとする厳しい医療費抑制策が取られることになったが、医科では、薬価引き下げで生み出される財源を潜在技術料として本体に振り替えるというシステムが導入された。一方、薬価差益の少ない歯科はそのシステムから外された。財源なしの厳しいマイナス改定が続いたため、この間に初・再診料の医科・歯科格差が拡大していった。これがいわゆる「失われた16年」である。しかもその後さらなる歯科医療費抑制策が取られることになる。
4.90年代 「保険でより良い入れ歯を」運動と長期維持管理路線
厳しい歯科医療費抑制政策を押し返そうと、患者と医療者の協同の運動が模索され、92年に「保険で良い入れ歯を」運動が発足した。結果、総義歯の保険点数を40%アップさせるなどの成果が生まれた。
しかし、政府からの巻き返しというべき、「補綴物維持管理料」(補管)が96年に導入され、(1)2年間の包括、(2)保証書の義務付け、(3)未届医療機関への減算などが設定された。今日に至る歯科医師の裁量を奪う「長期維持管理路線」の端緒がこの時代にある。
5.2000年代前半 「か初診」施設基準の導入、日歯連汚職事件
厚労省は、2000年の「かかりつけ歯科医初診料(か初診)」を皮切りに、次々と施設基準を導入し、患者の長期管理を名目に、施設基準をクリアできる歯科医療機関とそうでないものを差別化。歯科医師を分断支配するようになった。この長期維持管理路線は「失われた16年」より抑制効果が高かったことが証明されている(図2)、また、日歯連汚職事件後のいわゆる「報復改定」と言われる2006年改定では、歯科マイナス3.16%と、全体1200億円マイナスのうち700億円を歯科が背負うという、あまりにひどい改定内容となった。
6.2000年代後半~今日まで
民主党政権が誕生した2009年の政権交代後の2010,2012年改定では、医科の改定率を歯科の改定率が上回る状況が続き、自公政権に戻ってからもこの流れは変えられていない。
こうした中で2016年に導入されたのが「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」である。高い届け出基準を満たした歯科医療機関には歯周病安定期治療(SPT)やエナメル質初期う触(Ce)処置など、どの医療機関でもできる処置に特典を与えられた。これにより「一物二価」の不合理が生み出されるとともに、いっそう歯科医師間の分断が進んだ。
2018年に保団連は、歯科医療費総枠拡大を求める運動を提起した。これは「保険で良い歯科医療を」運動の再起動をその背景としている。患者・国民と医療者が結びついて、「歯科保健医療の拡充を求める」という運動の旗印をいっそうしっかりと掲げることが求められる。
さいごに
以上にみるように、歯科医療は徹底して、医科と切り離された独自の抑制策に苦しめられている。
歯科の低診療報酬の根本的問題は、「補綴治療の低評価」に尽きる。歯が欠けたり、なくなったりした場合、クラウンや入れ歯等の人工物で補うという、歯科医師と技工士以外にできない歯科治療の基本となる技術料点数が極めて低く、また範囲も狭い現状は極めて不当だ。
現状を打開するためには、政府の社会保障費削減政策を転換するとともに、歯科における「トータルバランス論」を乗り越え、歯科関連予算を拡充し、低すぎる診療報酬の引き上げと保険適応の拡大・窓口負担の引き下げを実現していくことが求められる。
コロナ禍のもと、密を避けるためのコスト増と、減収にどのように対処するのか、協会・保団連の取り組みが重要になる。繰り返しになるが、医療者と患者・国民が手を携えた全国規模での『保険でより良い歯科医療を』運動と、窓口負担軽減の運動とセットにした歯科医療費総枠拡大のうねりを起こしてほしい。
図1 国民医療費に占める歯科診療医療費の割合
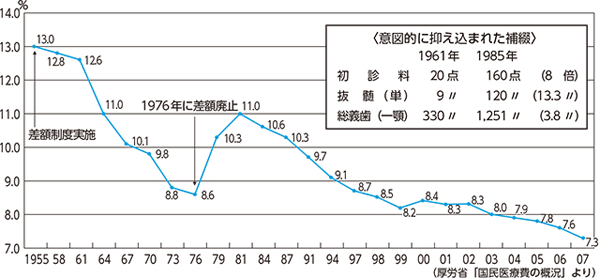
図2 1件当たりの点数の推移