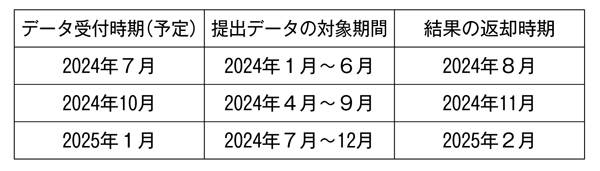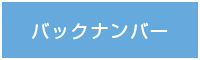2024年5月15日(2069号) ピックアップニュース
医科 新点数Q&A〈その2〉
※厚労省疑義解釈「その1」(2024年3月28日)、「その2」(4月12日)、「その3」(4月26日)、保団連『新点数・介護報酬Q&A』より抜粋・改編
初・再診料
〈外来感染対策向上加算〉
Q1 施設基準にどのような変更があったのか。A1 ①の変更があり、②が追加されました。
①新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の診療等を実施する体制に係る施設基準要件について、第二種協定指定医療機関(発熱外来に係る措置を講ずるものに限る)であることに変更されました。
②以下の2つが追加されました。
ア.当該医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受け入れを行う旨を公表し、受け入れを行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有している。
イ.感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制または専門医への紹介が可能な連携体制があることが望ましい。
Q2 「第二種協定指定医療機関」とは何か。
A2 改正感染症法(2024年4月1日施行)による医療措置協定のもと、発熱外来または自宅療養者等への医療提供を担う医療機関として、都道府県知事から指定を受けた医療機関をいいます。
Q3 2024年3月31日において外来感染対策向上加算を届け出ている場合でも、第二種協定指定医療機関の指定を受ける必要はあるか。
A3 2024年3月31日において現に当該加算を届け出ている場合、A1①については2024年12月31日までの経過措置があるので、それまでに第二種協定指定医療機関の指定を受けた上で、改めて届出を出しなおす必要があります。
Q4 協定指定医療機関の指定を受けた後、都道府県がホームページ上に当該医療機関を協力指定医療機関として掲載するまでの間も、届出は可能か。
A4 協定指定医療機関の指定を受けた後であれば、届出可能です。
Q5 施設基準において、「当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表」していることが求められているが、当該公表については、当該保険医療機関が公表を行う必要があるのか。
A5 当該保険医療機関のホームページにより公表することが想定されますが、例えば、自治体、地域医師会等のホームページまたは広報誌に掲載されている場合等においては、別に当該保険医療機関のホームページで公表を行う必要はありません。
〈発熱患者等対応加算〉
Q6 外来感染対策向上加算の届出を行っていない診療所でも算定できるのか。A6 算定できません。外来感染対策向上加算の届出を行っている診療所で算定します。
Q7 「発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下で診療を行った場合に算定する」とあるが、情報通信機器を用いた診療の場合でも算定できるのか。
A7 算定できません。
〈抗菌薬適正使用体制加算〉
Q8 施設基準における「抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること」は具体的には何を指すのか。A8 診療所版感染対策連携共通プラットフォーム(以下「診療所版J-SIPHE」)に参加し抗菌薬の使用状況に関するデータを提出することを指します。
Q9 施設基準における「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること」について、どのように確認すればよいか。
A9 診療所版J-SIPHEにおいて、四半期ごとに抗菌薬の使用状況に関するデータの提出を受け付け、対象となる期間(表)において使用した抗菌薬のうちAccess抗菌薬の割合および参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位が返却されるため、その結果(初診料等における抗菌薬適正使用体制加算については診療所版J-SIPHEにおける結果を指す)が施設基準を満たす場合に、当該結果の証明書を添付の上届出を行います。なお、使用した抗菌薬のうちAccess抗菌薬の割合および参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位については、提出データの対象期間における抗菌薬の処方件数が30件以上ある場合に集計対象となります。
※データ提出方法およびデータ受付時期並びに結果の返却時期の詳細については、診療所版J-SIPHEのホームページを確認してください。
・診療所版J-SIPHE「OASCIS(オアシス)」(https://oascis.ncgm.go.jp/)
Q10 施設基準を満たすことを確認した上で届出を行った場合について、届出後の施設基準の適合性について、どのように考えればよいか。
A10 施設基準の届出を行った場合には、届出後についても診療所版J-SIPHEに少なくとも6カ月に1回はデータを提出した上で直近に提出したデータの対象期間における施設基準の適合性の確認を行い、満たしていなかった場合には変更の届出を行う必要があります。
〈医療情報取得加算〉
Q11 オンライン資格確認により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。A11 医療情報取得加算2または医療情報取得加算4を算定します。
Q12 患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
A12 いずれの場合も、医療情報取得加算1または医療情報取得加算3を算定します。
Q13 同一の保険医療機関において、同一月に、同一の患者について、他の疾患で初診料を2回算定した場合について、医療情報取得加算1または2を2回算定できるか。
A13 算定できません。
Q14 医療情報取得加算3および4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。
A14 いずれも算定できません。医療情報取得加算3または医療情報取得加算4のいずれかを3月に1回に限り算定できます。
医学管理等
〈生活習慣病管理料〉
Q15 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)等の施設基準において、「患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること」について、院内の見やすい場所に掲示していることが求められているが、本紙前号6面の「Q&A〈その1〉」のQA6の内容に加え、「当院では主に院内処方を行っています」または「当院では主に長期の投薬をご案内しています」といった内容を併せて院内掲示してもよいか。A15 差し支えありません。
在宅医療
〈在宅ターミナルケア加算・看取り加算〉
Q16 往診料に在宅ターミナルケア加算が新設されたが、どのような場合に算定できるか。A16 在宅で死亡した患者(往診を行った後24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む)であって、死亡日および死亡日前14日以内の計15日間に、退院時共同指導料1を算定し、かつ往診を行った場合に算定できます。
Q17 往診料に看取り加算が新設されたが、どのような場合に算定できるのか。
A17 死亡日および死亡日前14日以内の計15日間に退院時共同指導を行った上で、死亡日に往診を行い、当該患者を患家で看取った場合に算定できます。なお、事前に患者または家族等に対して、療養上の不安等を解消するために十分の説明と同意を行っている場合に限ります。
〈在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料〉
Q18 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3について、「情報通信機器を用いた指導管理については、CPAP療法を開始したことにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを対面診療で確認した場合に実施すること」とされているが、他の保険医療機関でCPAP療法を開始した患者が紹介された場合の取り扱いはどうなるのか。A18 当該指導管理を実施する保険医療機関において、CPAP療法を開始したことにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを対面診療で確認した場合に算定できます。なお、当該診療に係る初診日およびCPAP療法を開始したことにより、睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを、当該指導管理を実施する保険医療機関において対面診療で確認した日を診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。
表 J-SIPHEおよび診療所版J-SIPHEにおけるデータ受付時期等