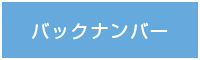2024年6月25日(2073号) ピックアップニュース
主張
戦後79年、「新しい戦前」にしないために
今夏は戦後79年になる。今後79年間、つまり今生まれた赤ん坊が79歳になるまでに戦争が起これば、今年は「戦前」となる。現在の情勢をみるに、その可能性は決して低くない。
政府は、いわゆる安保関連3文書を閣議決定し、「専守防衛」から「反撃能力」(敵基地攻撃能力)の保有を認め、隣国の主要都市を攻撃できる長距離ミサイルをアメリカから爆買いし、南西諸島への配備を進め他国を「威嚇」している。
現在、台湾有事や尖閣諸島への軍事侵攻を念頭に、沖縄・先島諸島の住民らを全員避難させる計画が進んでいる。先島諸島の5市町村の全住民約11万人と観光客約1万人を、九州各県と山口県に避難させるとしている。輸送には民間の航空機と船舶を用いるが、完了までに最短でも6日程度かかる。悪天候による足止めも考えられ、先島諸島には2週間程度滞在できる地下式のシェルターも整備する。
同時に与那国島では、陸上自衛隊駐屯地に日米共同演習の一環として日米の調整所が設けられ、共同演習も行われた。
このような動きを見ると、沖縄はもはや「戦争前夜」である。これらが兵庫県で進められていれば、私たちは受け入れられるのか。
かつての沖縄戦では、55万人の米軍が上陸し、当時の県民の4人に1人、約20万人が命を失った。軍隊は、県民を守る余裕をなくし、逃げ隠れた洞窟から住民を追い出した例もあった。戦時下で、住民にできるのはただ逃げ惑うことだけである。ウクライナやガザで現在進行中であり、それが戦争のリアルである。
麻生太郎自民党副総裁は、強い抑止力を機能させるためには、日本と米国、台湾には「戦う覚悟」が必要だと述べ、中国を「刺激」した。「戦う覚悟」というが、戦争となったときに第一に戦うのは指導者ではなく、自衛隊員であり、被害を受けるのは戦場になる地域の住民である。
戦争を知らない世代が指導者となり、「周辺安全保障環境の悪化には抑止力を」と繰り返す。
「抑止力」とは他国への威嚇によって、日本に対する武力攻撃をさせないようにすることである。威嚇には他国に対する相当の報復力つまり軍事力を必要とする。
威嚇政策は両国の相互不信を前提にしている。威嚇し不安を与えれば、相手国はそれに対抗し、抑止力を強化しようとさらに軍事力を強化する。いわゆる「安全保障のディレンマ」であり、現在の日本周辺の姿と重なる。
戦争は、双方の住民に多大な犠牲と破壊を生む。その認識と話し合いによる相互不信の解消こそが本来の「抑止力」である。今、この考え方が世界中で薄れてきている。
戦争を「させなかった」「戦後」79年間をこれからも継続するために、日本国憲法に基づき、武力ではなく、話し合いによる平和外交が求められる。
政府は、いわゆる安保関連3文書を閣議決定し、「専守防衛」から「反撃能力」(敵基地攻撃能力)の保有を認め、隣国の主要都市を攻撃できる長距離ミサイルをアメリカから爆買いし、南西諸島への配備を進め他国を「威嚇」している。
現在、台湾有事や尖閣諸島への軍事侵攻を念頭に、沖縄・先島諸島の住民らを全員避難させる計画が進んでいる。先島諸島の5市町村の全住民約11万人と観光客約1万人を、九州各県と山口県に避難させるとしている。輸送には民間の航空機と船舶を用いるが、完了までに最短でも6日程度かかる。悪天候による足止めも考えられ、先島諸島には2週間程度滞在できる地下式のシェルターも整備する。
同時に与那国島では、陸上自衛隊駐屯地に日米共同演習の一環として日米の調整所が設けられ、共同演習も行われた。
このような動きを見ると、沖縄はもはや「戦争前夜」である。これらが兵庫県で進められていれば、私たちは受け入れられるのか。
かつての沖縄戦では、55万人の米軍が上陸し、当時の県民の4人に1人、約20万人が命を失った。軍隊は、県民を守る余裕をなくし、逃げ隠れた洞窟から住民を追い出した例もあった。戦時下で、住民にできるのはただ逃げ惑うことだけである。ウクライナやガザで現在進行中であり、それが戦争のリアルである。
麻生太郎自民党副総裁は、強い抑止力を機能させるためには、日本と米国、台湾には「戦う覚悟」が必要だと述べ、中国を「刺激」した。「戦う覚悟」というが、戦争となったときに第一に戦うのは指導者ではなく、自衛隊員であり、被害を受けるのは戦場になる地域の住民である。
戦争を知らない世代が指導者となり、「周辺安全保障環境の悪化には抑止力を」と繰り返す。
「抑止力」とは他国への威嚇によって、日本に対する武力攻撃をさせないようにすることである。威嚇には他国に対する相当の報復力つまり軍事力を必要とする。
威嚇政策は両国の相互不信を前提にしている。威嚇し不安を与えれば、相手国はそれに対抗し、抑止力を強化しようとさらに軍事力を強化する。いわゆる「安全保障のディレンマ」であり、現在の日本周辺の姿と重なる。
戦争は、双方の住民に多大な犠牲と破壊を生む。その認識と話し合いによる相互不信の解消こそが本来の「抑止力」である。今、この考え方が世界中で薄れてきている。
戦争を「させなかった」「戦後」79年間をこれからも継続するために、日本国憲法に基づき、武力ではなく、話し合いによる平和外交が求められる。