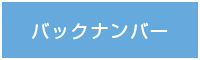2025年1月25日(2091号) ピックアップニュース
阪神・淡路大震災から30年
経験語り継ぎ新たなつながりを
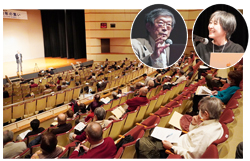
18日の「阪神・淡路大震災30年の集い」では、石橋克彦神戸大学名誉教授(上左)や石川県七尾市の根上昌子医師(上右)らが講演

ポスター展示では各地の被災地の経験を共有し、課題を確認した
協会と西宮・芦屋支部は18日、西宮市内で「阪神・淡路大震災30年の集い」を開催し、オンラインとあわせて282人(会場203人、Zoom79人)が参加した。
「震災経験を語り継ぐ・風化させない・新たなつながりを拡げる」ことを目的に開催した本企画は、メイン講演として、神戸大学の石橋克彦名誉教授が「『大地動乱の時代』と『原発震災』」をテーマに、来たるべき南海トラフ巨大地震への備えとして、社会と暮らし方を根本的に振り返り、特に原発とリニアは地震対策の対極であり、見直しが必要と指摘した。
他に、アスベスト問題や能登半島地震被災地の現状をテーマとした講演、阪神・淡路、東日本大震災・福島第一原発事故、熊本地震、能登半島地震など各地の被災地での経験・取り組みに関するポスター展示も行われ、参加者は活発に意見を交流した。
17日には協会などでつくる阪神・淡路大震災救援・復興兵庫県民会議(県民会議)がメモリアル集会「災害被災者のくらし再建・人間復興へ 住み続ける権利と人権」を、長田区内で開催し、約300人が参加。室崎益輝神戸大学名誉教授と井上英夫金沢大学名誉教授が記念講演し、「生業と暮らしの再建」を政府の責任で保障させる政策を求めるたたかいを続けていくことを確認した。
12日には協会も加わった実行委員会が、震災アスベストをテーマとしたシンポジウムを開催した。
談話
今後来る災害へ教訓を新たに
理事長 西山 裕康
 阪神・淡路大震災から30年。節目の年と言われますが、被災者にとっては29年目も31年目も大きく異なることはないでしょう。記憶を風化させてはならない、とも強調されますが、妻や夫、親や子どもを失った人たちが、後悔と苦しみが続く中で、誰に何を語ることができるのでしょうか。「忘れてほしくないが、そっとしておいてほしい」というのが正直な気持ちかもしれません。近くにいた、比較的被害の軽かった人が、震災を知らない世代や地域の方々へ、継続して粘り強く事実を継承していくことが亡くなられた方への供養であり、被災者への理解と共感、励ましになると考えます。
阪神・淡路大震災から30年。節目の年と言われますが、被災者にとっては29年目も31年目も大きく異なることはないでしょう。記憶を風化させてはならない、とも強調されますが、妻や夫、親や子どもを失った人たちが、後悔と苦しみが続く中で、誰に何を語ることができるのでしょうか。「忘れてほしくないが、そっとしておいてほしい」というのが正直な気持ちかもしれません。近くにいた、比較的被害の軽かった人が、震災を知らない世代や地域の方々へ、継続して粘り強く事実を継承していくことが亡くなられた方への供養であり、被災者への理解と共感、励ましになると考えます。
今年は戦後80年の年でもあります。この80年間、震度6以上の国内地震は、阪神・淡路大震災の前の50年間では6回、95年以降の30年間では65回発生しています。南海トラフ地震の発生確率は30年以内に80%とされ、これまでとは比べ物にならない広域複合災害が想定されます。発生は明日かもしれません。
阪神・淡路では死亡者6400人余り、住宅被害は全壊だけで10万棟以上、全焼は7千棟でした。一方、南海トラフは、死亡者32万人、全壊焼失238万棟、避難者950万人と想定されています。比較は不適切かもしれませんが、東京大空襲と二つの原爆投下による合計死亡者数に匹敵し、震災対策の優先順位は著しく高いといえます。
まずは、家屋の耐震化、家具の転倒防止、備蓄品等多方面から見直し、災害を最小化するために、個人として、そして社会として具体的な対策を怠ってはなりません。特に耐震化の遅れている住宅、高齢者や独居者など、対応が困難な方への対策が全体的な被害を少なくします。
発災直後は命を守り、その後は衣食住の確保、そして復旧、つまり生活、仕事の再建です。いずれも早い時期に被災者が安心と希望を持てるような政策が必要です。国民の命と健康、生活を保障するのは国の責任であり、自助の強調は単なる責任転嫁に他なりません。
毎年1月17日は、「創造的復興」の美名を借りた「大型、ハコモノ、上から目線」ではなく、住民本位の生活再建のための公的財政措置の拡充を要求する日としなければなりません。
兵庫協会は阪神・淡路大震災後、数々の活動を行い、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震等の災害に際しては速やかに支援活動を行い、今も継続しています。
この談話が、皆様に震災被害を共有し、教訓を新たにし、ご自身のできることを考えていただくきっかけになりましたら幸いです。