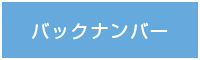2025年2月15日(2093号) ピックアップニュース
燭心
色覚検査といえば色覚表を用いた石原式検査を思い出す方が多いであろう。同検査は「感度」を重視し、僅かな個体差でも「異常」と判定する傾向がある。簡易検査として学校健診等で広く行われてきたが、本検査で「色覚異常」を指摘されても、実際に日常生活上の困難や就労における能力障害などを生じないこと等が明らかになり、03年度より学校健診の項目より削除された▼色覚に関する個体差はX染色体における遺伝子多型によるもので、伴性遺伝の形式をとるものが知られている。日本人男性の約8%は、色の識別に関わる3種の錐体細胞のうち、中間色(M)あるいは長波長(L)に対応する錐体細胞が機能せず「赤緑色弱」と呼ばれていた。M細胞が機能しなくても、色の識別に関して、ほとんど支障を経験することはない。L細胞が機能しない場合は、多少の困難さを経験することもあるが対応可能な場合が多い▼「色盲」「色弱」は実態を反映しない用語として廃止され「色覚異常」(多くの下位分類あり)と総称されている。最近は「色覚多様性」という概念が広がり、色覚異常の有無で制限のあった一部職種も「個別の適性を重視する」方針を打ち出している▼「君は色弱だから医者は無理だね」と教師に言われた記憶がある。医業では色覚異常による制限はないが「一定の努力」が推奨されている。千円札と五千円札の識別が苦手な私は、色覚障害のない職員に金種確認をお願いするなど「一定の努力」をしている(眞)