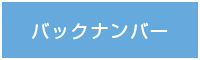2025年3月15日(2096号) ピックアップニュース
県弁護士会共催 市民シンポジウム 講演録
マイナ保険証推進で大丈夫?
県弁護士会共催 市民シンポジウム「使わなくていい?『マイナ保険証』」
協会が昨年11月23日、兵庫県弁護士会、日本弁護士連合会(日弁連)とともに共催して実施した市民シンポジウム「使わなくていい?『マイナ保険証』~どうして、私の受診歴がいろんな人に見られるの...?」。基調講演、報告の講演録を掲載する(文責・兵庫県保険医協会編集部)。
報告①

また、この番号が本人のものであることを証明するための手段として「マイナンバーカード」がある。このカードにはICチップが埋め込まれており、写真や個人情報が記録されている。
法律上、マイナンバーカードは便利な本人確認手段とされているが、取得は義務ではなく任意である。運転免許証や住民票などを利用することで本人確認が可能であるからだ。
しかし、政府はカードの普及に力を入れ、健康保険証としての利用やポイント制度の導入などで取得を促している。この動きに対しては、「任意であるべきものが事実上の強制になっているのではないか」という批判も根強い。
しかし、この仕組みには重大な問題点がある。まず、保険資格情報の更新にタイムラグが生じることや、システムエラー、手入力ミスが発生するリスクがある。例えば、会社を退職した場合、その情報が正確に反映されるまでに時間がかかることがある。また、医療機関でシステムにアクセスできない場合、患者は一時的に医療費を全額負担しなければならない可能性がある。このような不具合は、利用者の利便性を損なうだけでなく、医療現場で混乱を招く恐れがある。
この点で参考になるのが、アメリカでのデータ利用の例である。20年ほど前、アメリカのあるスーパーマーケットが顧客の買い物履歴を分析し、妊娠中の女性を特定するプログラムを開発した。買い物の傾向から妊娠の可能性を察知し、本人やその家族が気づく前にクーポンを送付するといった手法である。この事例は、データ分析が商業的には有効である一方で、プライバシー侵害のリスクをはらむことを示している。妊娠という極めて個人的な情報が、本人の許可なく利用されたことは、データ利用の危険性を象徴している。
日本のマイナンバーカードにおいても、医療データやその他の個人情報が民間企業に利用される可能性がある。このデータが商業的な目的で使われることで、国民のプライバシーが侵害される恐れがあるだけでなく、格差の拡大や不当な差別につながるリスクもある。このような利用が進むと情報管理の主導権を国や企業に握られることになり、国民一人ひとりの自由や権利が損なわれる恐れがある。
政府は、マイナンバーカードを利用して医療データの共有を進めることで、新薬開発や診療の効率化を目指していると説明している。しかし、このような「便利さ」の裏には、情報が悪用される可能性や、個人がその利用状況を把握しきれないリスクが存在する。制度を推進するのであれば、データの利用範囲を明確にし、厳格な規制を設ける必要がある。
以上のように、マイナンバーカードは利便性と同時に多くのリスクをはらんでいる。特に、情報の過剰な集約や商業利用に対して慎重な姿勢を取らなければならない。本日は、こうした観点を含めてマイナンバーカードに関する問題点を述べさせていただいた。
報告②

実際、従来の保険証を利用している国民が圧倒的に多く、24年9月時点では86%が従来型保険証を使用している。一方で、マイナ保険証を利用しているのはわずか13.9%にすぎない。この状況は国家公務員の間でも同様であり、彼らは職務上マイナンバーカードを所持しているものの、保険証として利用している割合は13.9%と低い。これは、利用が進まない原因が個人の思想やイデオロギーではなく、制度そのものにあることを示している。
こうしたトラブルの背景には、システムのタイムラグや不具合がある。年間500万人が結婚、離婚、出産、転居に伴い被保険者情報を変更する日本において、これらのデータをリアルタイムで更新することは技術的に難しい。トップダウンで進められたこの事業の現状は、IT知識の乏しい責任者による無理な推進が原因であり、現場の実態が無視された結果である。
また、介護現場ではマイナ保険証の利用が特に困難である。認知症患者や寝たきりの高齢者がカードを管理することは現実的ではなく、暗証番号や顔認証も利用が難しい。介護施設では、保険証廃止に反対する意見が9割以上を占めている。こうした現場の声を無視して制度を進めることは、混乱をさらに拡大させるだけである。
世論調査や現場の意見を見ても、保険証廃止への反対は圧倒的である。国民の8割以上が保険証を残すべきと回答しており、医療機関や介護施設でも同様の意見が多数を占めている。このような状況で政策を強行することは、民主主義の原則を無視するものであり、許されるべきではない。
現行の保険証を残すことで、誰もが公平に医療を受けられる制度を維持することができる。マイナ保険証を利用するかどうかは個人の自由であり、その選択権を尊重すべきである。
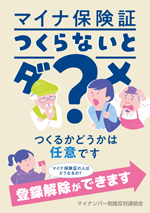
ご注文は、電話078-393-1807まで
基調講演

マイナンバー制度に対し、政府は一貫して「問題ない」という立場を崩さないが、その主張は現実とかけ離れている。当初、漏えいや悪用の懸念に対して、政府は「厳罰があるので漏えいはありえない」と説明していたが、情報漏えい事件はこれまで幾度となく発生している。特にフリーランスや多くの企業と取引を行う個人は、自らのマイナンバーを多数の相手に提供する必要があり、どこかから漏洩するリスクは避けられない。しかし、万一の漏えいに対する救済措置や具体的な対応策は示されず、結局は自己責任を押し付けられる構造が残っている。
例えば、南アフリカのアパルトヘイトでは、黒人を番号で管理し、支配の一環とした。また、戦前の日本も朝鮮半島や満州で住民を番号で管理し、カードに指紋を押させることで統治していた。こうした支配のための仕組みが、日本国内に復活しようとしているのがマイナンバー制度である。
マイナ保険証の導入によって、生命や健康に関わる情報が管理対象となり、情報漏えいのリスクがさらに高まる。過去には備前市がマイナンバーカード所持者のみに給食費無償化を適用しようとするなど、カードの有無によって差別的な扱いが生まれた事例もある。このような動きは、カード所持を事実上の「踏み絵」とする政府の考え方を如実に示している。保険証の一本化は、マイナンバーを中心とした監視社会構築の重要なステップであると考えられる。
さらに、顔認証や指紋認証などの生体認証技術がマイナンバー制度に組み込まれている。これらの技術は本人確認を便利にする一方で、個人の生体情報が管理・記録されるリスクを伴う。企業のマーケティングにおいても、これらの情報が活用され、個別の行動履歴や嗜好に基づく広告配信が可能になる。一方で、政府がこれらの技術を通じて国民の行動を監視する可能性も排除できない。
しかし、この制度には、社会全体に及ぼす重大な問題が内包されている。個人情報が一元管理されることで、国家や企業による監視や管理が容易になると同時に、不公平や差別が助長される恐れがある。例えば、かつて就職活動で履歴書に記載された本籍や親の職業が、差別や採用の拒否につながった例があるように、マイナンバーを利用した情報管理が新たな差別を生む可能性がある。
また、医療情報や健康情報が企業に利用されることへの懸念も強い。新薬開発などのビッグデータとしての活用は一定の意義があるが、個人の嗜好や病歴に基づくターゲティング広告が展開されることで、プライバシー侵害の問題が深刻化する恐れがある。
マイナ保険証の導入は、監視社会への道を開く重要な契機となる可能性がある。これを放置すれば、私たちはいつの間にか生活のあらゆる側面を管理される社会に生きることになるかもしれない。今こそ、国民一人ひとりがこの問題に向き合い、その影響について真剣に考えるべきである。
報告①
「マイナ保険証に関する法律問題」
利便性の裏に多くのリスク

元日弁連情報問題対策委員会委員長
大阪弁護士会 坂本 団弁護士
マイナンバー制度とマイナンバーカード
まず、マイナンバー制度の概要を説明する。この制度は「社会保障・税番号制度」として導入されたものであり、住民票を持つ全員に一意の番号を付与し、役所が持つ個人情報を一元的に管理する仕組みである。この番号を利用することで、情報の一元化が進み、行政手続きの効率化が図られるとしている。また、この番号が本人のものであることを証明するための手段として「マイナンバーカード」がある。このカードにはICチップが埋め込まれており、写真や個人情報が記録されている。
法律上、マイナンバーカードは便利な本人確認手段とされているが、取得は義務ではなく任意である。運転免許証や住民票などを利用することで本人確認が可能であるからだ。
しかし、政府はカードの普及に力を入れ、健康保険証としての利用やポイント制度の導入などで取得を促している。この動きに対しては、「任意であるべきものが事実上の強制になっているのではないか」という批判も根強い。
マイナ保険証 システムエラー等に懸念
次に、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みについて述べる。通常の健康保険証には、保険者名称や被保険者番号などが明記されているが、マイナンバーカードにはそのような情報は記載されていない。その代わりに、ICチップ内に記録された電子証明書を使用する。医療機関ではカードリーダーでこの電子証明書を読み取り、インターネット経由で保険資格情報を確認する。この仕組みにより、カードが健康保険証として機能するのである。しかし、この仕組みには重大な問題点がある。まず、保険資格情報の更新にタイムラグが生じることや、システムエラー、手入力ミスが発生するリスクがある。例えば、会社を退職した場合、その情報が正確に反映されるまでに時間がかかることがある。また、医療機関でシステムにアクセスできない場合、患者は一時的に医療費を全額負担しなければならない可能性がある。このような不具合は、利用者の利便性を損なうだけでなく、医療現場で混乱を招く恐れがある。
個人の医療データ使用でプライバシー侵害の恐れ
さらに懸念されるのは、マイナンバーカードがプライバシーに及ぼす影響である。電子証明書がもたらす利便性は評価される一方で、情報がどのように利用されるかについては、十分な規制がないのが現状である。例えば、生命保険会社が医療データを利用し、病気リスクの高い人に高額な保険料を課す可能性が指摘されている。また、データが他の情報と結びつくことで、個人の行動や状態が予測され、不利益を受けるリスクもある。この点で参考になるのが、アメリカでのデータ利用の例である。20年ほど前、アメリカのあるスーパーマーケットが顧客の買い物履歴を分析し、妊娠中の女性を特定するプログラムを開発した。買い物の傾向から妊娠の可能性を察知し、本人やその家族が気づく前にクーポンを送付するといった手法である。この事例は、データ分析が商業的には有効である一方で、プライバシー侵害のリスクをはらむことを示している。妊娠という極めて個人的な情報が、本人の許可なく利用されたことは、データ利用の危険性を象徴している。
日本のマイナンバーカードにおいても、医療データやその他の個人情報が民間企業に利用される可能性がある。このデータが商業的な目的で使われることで、国民のプライバシーが侵害される恐れがあるだけでなく、格差の拡大や不当な差別につながるリスクもある。このような利用が進むと情報管理の主導権を国や企業に握られることになり、国民一人ひとりの自由や権利が損なわれる恐れがある。
政府は、マイナンバーカードを利用して医療データの共有を進めることで、新薬開発や診療の効率化を目指していると説明している。しかし、このような「便利さ」の裏には、情報が悪用される可能性や、個人がその利用状況を把握しきれないリスクが存在する。制度を推進するのであれば、データの利用範囲を明確にし、厳格な規制を設ける必要がある。
以上のように、マイナンバーカードは利便性と同時に多くのリスクをはらんでいる。特に、情報の過剰な集約や商業利用に対して慎重な姿勢を取らなければならない。本日は、こうした観点を含めてマイナンバーカードに関する問題点を述べさせていただいた。
報告②
国民と医療・介護現場からの声を尊重すべき

兵庫県保険医協会理事長 西山 裕康氏
導入から3年しても普及しない現状
現在(昨年11月)、マイナ保険証の普及率が低いことが課題となっている。マイナンバーカードの所有率は75%であるが、健康保険証として登録している人は61%、さらに実際に持ち歩いている人は約50%にとどまる。保険証として利用している人の割合は15%程度であり、1億人以上が未利用の状況である。制度導入から3年経過しても十分に活用されていない現状は、深刻な問題である。実際、従来の保険証を利用している国民が圧倒的に多く、24年9月時点では86%が従来型保険証を使用している。一方で、マイナ保険証を利用しているのはわずか13.9%にすぎない。この状況は国家公務員の間でも同様であり、彼らは職務上マイナンバーカードを所持しているものの、保険証として利用している割合は13.9%と低い。これは、利用が進まない原因が個人の思想やイデオロギーではなく、制度そのものにあることを示している。
8割の国民が一本化に反対
全国的なアンケート調査では、81%の国民がマイナ保険証一本化に反対している。理由として挙げられるのは、従来の保険証の方が使いやすいこと、情報漏えいへの不安、カードを持ち歩きたくないこと、そして制度のメリットを感じないことなどである。こうした国民の不安や不満が解消されない限り、保険証廃止を進めるべきではない。現場無視の無理な推進が原因
さらに、マイナカード、マイナ保険証に関連するトラブルも多発している。他人の情報が登録される、窓口負担割合が誤って登録される、他人の住民票が発行されるなどの問題が報告されている。これらは単なる入力ミスではなく、個人情報の漏えい事件であり、個人情報保護委員会からデジタル庁に行政指導が行われる事態となった。また、医療機関でも混乱が生じており、72.8%の施設が何らかのトラブルを経験している。最も多いトラブルは「資格確認ができない」というものであり、業務効率化どころか現場の負担が増加しているのが現状である。こうしたトラブルの背景には、システムのタイムラグや不具合がある。年間500万人が結婚、離婚、出産、転居に伴い被保険者情報を変更する日本において、これらのデータをリアルタイムで更新することは技術的に難しい。トップダウンで進められたこの事業の現状は、IT知識の乏しい責任者による無理な推進が原因であり、現場の実態が無視された結果である。
また、介護現場ではマイナ保険証の利用が特に困難である。認知症患者や寝たきりの高齢者がカードを管理することは現実的ではなく、暗証番号や顔認証も利用が難しい。介護施設では、保険証廃止に反対する意見が9割以上を占めている。こうした現場の声を無視して制度を進めることは、混乱をさらに拡大させるだけである。
情報利用同意の仕組み管理体制に問題
さらに問題視されるのが、同意の仕組みとプライバシーの保護である。診察情報や薬剤情報などが一括で開示される仕組みは、患者の意思やプライバシーを軽視している。特に、がんや精神疾患、感染症、遺伝性疾患などの情報が広く共有される可能性があり、データの利用目的や管理体制が不明確であることは深刻な問題である。また、大まかな収入が共有される同意項目もあり、デジタル化がプライバシー侵害を助長する恐れがある。世論調査や現場の意見を見ても、保険証廃止への反対は圧倒的である。国民の8割以上が保険証を残すべきと回答しており、医療機関や介護施設でも同様の意見が多数を占めている。このような状況で政策を強行することは、民主主義の原則を無視するものであり、許されるべきではない。
現行の保険証を残すことで、誰もが公平に医療を受けられる制度を維持することができる。マイナ保険証を利用するかどうかは個人の自由であり、その選択権を尊重すべきである。
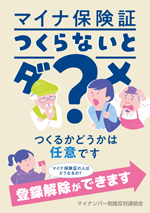
大好評!リーフレット
「マイナ保険証 つくらないとダメ?」
マイナ保険証作成は任意で登録解除もできることや、今の保険証がいつまで使えるかなどを分かりやすく示したリーフレットです。ご注文は、電話078-393-1807まで
基調講演
監視社会への道を開くマイナ保険証

ジャーナリスト
斎藤 貴男氏
漏えいへの対策・救済措置示されず
本日新幹線が遅延し、会場到着が遅れてしまった。その新幹線の中で考えたのだが、新幹線の運行が停止したら在来線を使って目的地に向かうという代替手段が取れるが、マイナ保険証に置き換わる制度では、紙の保険証という代替手段が失われる。資格確認がうまくいかない場合、現在は紙の保険証で対応できるが、それも廃止されれば、患者は受診を諦めざるを得ない状況が生まれる可能性がある。マイナンバー制度に対し、政府は一貫して「問題ない」という立場を崩さないが、その主張は現実とかけ離れている。当初、漏えいや悪用の懸念に対して、政府は「厳罰があるので漏えいはありえない」と説明していたが、情報漏えい事件はこれまで幾度となく発生している。特にフリーランスや多くの企業と取引を行う個人は、自らのマイナンバーを多数の相手に提供する必要があり、どこかから漏洩するリスクは避けられない。しかし、万一の漏えいに対する救済措置や具体的な対応策は示されず、結局は自己責任を押し付けられる構造が残っている。
制度の背景にある監視社会の思想
このような問題が放置されている背景には、マイナンバー制度に内在する監視社会の思想があるといえる。この制度は、政府が国民一人ひとりに番号を付けて管理するという発想のもと進められており、歴史的に見ると植民地支配や差別政策と共通する部分が多い。例えば、南アフリカのアパルトヘイトでは、黒人を番号で管理し、支配の一環とした。また、戦前の日本も朝鮮半島や満州で住民を番号で管理し、カードに指紋を押させることで統治していた。こうした支配のための仕組みが、日本国内に復活しようとしているのがマイナンバー制度である。
マイナ保険証の導入によって、生命や健康に関わる情報が管理対象となり、情報漏えいのリスクがさらに高まる。過去には備前市がマイナンバーカード所持者のみに給食費無償化を適用しようとするなど、カードの有無によって差別的な扱いが生まれた事例もある。このような動きは、カード所持を事実上の「踏み絵」とする政府の考え方を如実に示している。保険証の一本化は、マイナンバーを中心とした監視社会構築の重要なステップであると考えられる。
さらに、顔認証や指紋認証などの生体認証技術がマイナンバー制度に組み込まれている。これらの技術は本人確認を便利にする一方で、個人の生体情報が管理・記録されるリスクを伴う。企業のマーケティングにおいても、これらの情報が活用され、個別の行動履歴や嗜好に基づく広告配信が可能になる。一方で、政府がこれらの技術を通じて国民の行動を監視する可能性も排除できない。
マイナンバー制度が新たな差別を生む可能性
現代では、こうした監視社会への懸念が徐々に薄れつつある。それは、利便性を優先する風潮の中で、監視に対する警戒心が鈍化しているためである。政府関係者の中には「国民は奴隷になりたがっている」と発言した者もおり、このような発言は市民社会の反応の鈍さを反映している。過去には国民総背番号制に対する反対運動が大きな力を持ち、導入を阻止した時期もあったが、現在ではそのような運動の勢いは見られない。しかし、この制度には、社会全体に及ぼす重大な問題が内包されている。個人情報が一元管理されることで、国家や企業による監視や管理が容易になると同時に、不公平や差別が助長される恐れがある。例えば、かつて就職活動で履歴書に記載された本籍や親の職業が、差別や採用の拒否につながった例があるように、マイナンバーを利用した情報管理が新たな差別を生む可能性がある。
マイナ保険証資格確認書も期限あり
さらに、マイナ保険証の運用には多くの実務的な課題が残る。医療現場では、窓口での資格確認がうまくいかないトラブルが相次ぎ、システムの不具合やタイムラグによる混乱が報告されている。特に高齢者や障害者など、マイナンバーカードを利用するのが難しい層への対応が十分ではない。資格確認書が発行されるとしても、その運用期間が限られている可能性があり、多くの人が不安を抱えている。また、医療情報や健康情報が企業に利用されることへの懸念も強い。新薬開発などのビッグデータとしての活用は一定の意義があるが、個人の嗜好や病歴に基づくターゲティング広告が展開されることで、プライバシー侵害の問題が深刻化する恐れがある。
人間を番号で管理する是非を真剣に考えるべき
このような問題に直面している今こそ、マイナンバー制度とそれに関連するマイナ保険証の導入について、哲学的な視点からの議論が必要である。人間を単なる番号で管理することの是非や、利便性と人間の尊厳のどちらを優先すべきかについて、深く考えるべき時が来ている。マイナ保険証の導入は、監視社会への道を開く重要な契機となる可能性がある。これを放置すれば、私たちはいつの間にか生活のあらゆる側面を管理される社会に生きることになるかもしれない。今こそ、国民一人ひとりがこの問題に向き合い、その影響について真剣に考えるべきである。