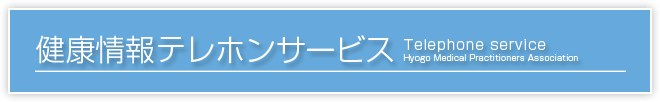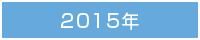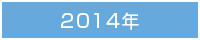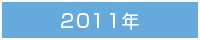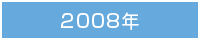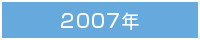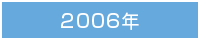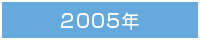2024年5月
【木曜】おしっこのトラブル 神経因性膀胱
神経因性膀胱という病気の名前を聞くと、堅苦しく、イメージできない膀胱の病気のように感じられますね。簡単に言うと、神経の病気のせいで、うまく働かなくなった膀胱の病気のことです。
膀胱がうまく働かないと、尿をためられなくなったり、排尿ができなくなったりします。実際の生活では尿がためられない場合は、冷たい水をさわると尿がもれる、急に尿をこらえきれない、という症状が起きます。逆に尿を出せない場合は、尿がでない、下にたれる、とぎれとぎれになる、という症状が起きます。その症状についてくる問題として、ぬれた下着をかえたり、公衆トイレで隣の人よりもおしっこの時間が長かったりするのも、ちょっと嫌ですよね。それは、神経が原因かもしれません。
それでは、簡単に神経と膀胱の関係を説明します。膀胱は尿をためる袋状の臓器で、排尿筋とよばれる薄いしなやかな筋肉でできています。その排尿筋という筋肉が伸び縮みすることで、尿をためたり、尿を出したりします。この膀胱の筋肉を伸び縮みさせている正体が、神経、というわけです。
ところで、私たちはどのようにして蓄尿しているのでしょう? それは、無意識に膀胱が勝手にひろがるからです。心臓が無意識にうごくのと同じように、膀胱も自律神経の命令で、無意識に膀胱の筋肉がゆるんでひろがり尿がたまります。これが正常な働きです。そこに自律神経の異常がおきると、正しく膀胱が緩まず広がらなくなって、逆に排尿筋が収縮し、強い尿意や尿漏れといった排尿のトラブルになります。たとえば脳梗塞や脊髄の損傷、糖尿病や腹部の大きな手術などで排尿に関連した神経に大きな損傷が起こることがあります。それらの病気によって自律神経内で正しい信号が送れなくなって膀胱に伝わらなくなります。これが神経因性膀胱のメカニズムなのです。
この障害を長期間放置すると、感染症や腎臓の機能が低下するため、適切な管理や予防が必要です。治療については神経の損傷の場所や程度によって異なり、個人差もおおきいです。そのため、泌尿器科をはじめ他の科の医師とも共同して、それぞれの状態にあわせた評価と治療が重要となります。
その最初の窓口の一つは泌尿器科の医師です。排尿のトラブルは一人でなやまずに、かかりつけ医や泌尿器科を受診しましょう。