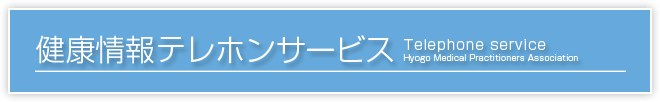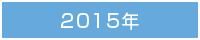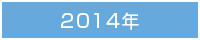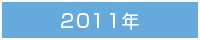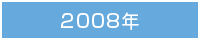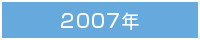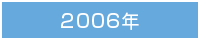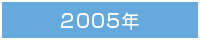2025年2月
【金土日】ASD(自閉症スペクトラム障害)
ASD(自閉症スペクトラム障害)は、社会的コミュニケーションや対人関係における困難さ、自分で決めた規則を曲げられない、電車やアニメなどへの強い執着を示すなど、特定の行動や興味の偏りが特徴とされる発達障害です。この障害は一人ひとりの症状や特性が異なり、知的能力や生活スキルに差が生じやすい「スペクトラム(連続体)」として捉えられています。ASDは近年、診断の理解と方法が進んだことにより、より多くの人々がその診断を受けるようになりましたが、地域での理解や支援はまだ十分とは言えません。
ASDの早期発見と支援は、本人が持つ潜在能力を引き出し、生活の質を向上させるために重要です。例えば、幼児期において視線の合いにくさや他者への関心の低さが見られる場合、ASDのサインである可能性があります。早期の段階で専門的な支援を受けることで、社会的な能力を高め、日常生活に適応しやすくなることが期待できます。地域における乳幼児健診や保健センターでの相談体制を充実させることで、こうした早期発見がより効果的に行えるでしょう。
地域社会でASDのある人々が暮らしやすい環境を整えるためには、支援の仕組みや理解の促進が欠かせません。こうした特性をもつ方々の多くは、変化への不安感が強かったり、刺激に敏感だったりします。地域住民や医療従事者がこうした特性を理解し、サポートすることで、当事者が安全かつ安心して生活できる環境が整います。また、ASDを抱える家族が孤立しないよう、地域での相談窓口などの活用を促すことも重要です。
ASDに関する理解を地域社会で広めるためには、住民への啓発活動が有効です。地域のイベントや健康講座などで、ASDの特性や関わり方について学ぶ機会を設けることが、偏見の解消や支援の質向上につながります。また、学校や職場でも理解を深めるための研修を行うことで、ASDのある人々が自分の力を発揮しやすい環境を整えることができます。
自閉症スペクトラム障害を理解し、地域全体で支えていくことは、ASDのある人々が安心して暮らせる社会を築くために欠かせません。私たち一人ひとりが理解を深め、当事者や家族を温かく受け入れる姿勢を持つことが、より包括的な地域社会の実現につながるでしょう。