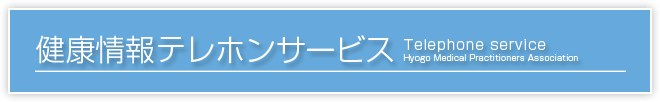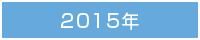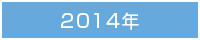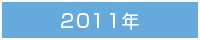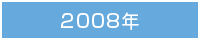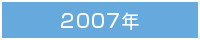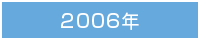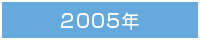2025年2月
【月曜】強度近視と病的近視
近視の強さは、屈折度数によって分類されています。ジオプトリーという単位で、通常は-0.5以上を近視と呼び、-6以上になると強度近視といいます。近視の原因に眼球の長さが通常より長い場合が挙げられ、眼球の長さが26.5mm以上で強度近視とされています。
近視には「病的近視」という状態があり、この状態になると、視力を司る黄斑部の網膜が傷つく「近視性牽引性黄斑疾患」という病気や、眼底でむくみを生じる「近視性脈絡膜新生血管症」などを合併し、視力が極端に低下してしまいます。眼鏡などで矯正しても視力が回復せず、失明に至ることもあります。
病的近視の場合、合併している病気によって治療法が変わります。眼内の硝子体内の注射、レーザー光で焼き固める方法、外科手術などの治療が挙げられます。
強度近視が必ず病的近視という訳ではありませんが、近視のない人に比べ白内障は5倍、緑内障は14倍、網膜剥離は22倍、網膜黄斑症は41倍も発症しやすいというデータがあり、強度近視であると病的な状態になりやすいことは明らかです。
病的近視の特徴に眼球の後ろが膨らんでくる後部ぶどう腫がありますが、これは白目(強膜)の強度が弱まることによって発症するとされています。白目の強度が低下する原因になる強度近視を防ぐ事、すなわち近視を予防する事が重要だということになります。
近視の予防にはいくつかエビデンスの確立した方法があります。主なものは自費診療となりますが、第1に「低濃度アトロピン」という点眼薬、第2に就寝中に特殊なコンタクトレンズを装着する「オルソケラトロジー」、第3に遠近両用コンタクトレンズの一種である「多焦点ソフトコンタクトレンズ」です。
近視になる最大の要因は、室内で手元の近いところを見続けてする活動が増えることです。まだエビデンスの確立には至っていませんが、経験上も太陽光(バイオレット光)を浴びての屋外での活動は近視の予防に効果的なようです。太陽光のあたる屋外で、子どもたちがしっかりと活動することが最も大事な近視予防になります。
コロナ禍で自宅で過ごす時間が長期化するにつれ、短期間で近視が急激に進行する子どもが増えたと言う報道がありました。将来、病的近視になって失明したり、日常生活に支障が出るということを防ぐためにも、近視の予防にしっかりと取り組むことが必要です。