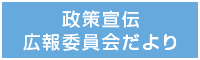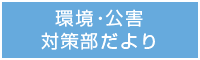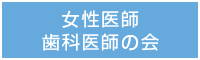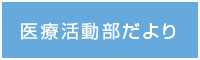政策宣伝広報委員会だより
政策解説 社会保障制度改革国民会議「報告書」解説(2) 医療費抑制のための医療提供体制「改革」 --国民だましの「フリーアクセス」元凶論--
2013.12.15
8月に発表された社会保障制度改革国民会議「報告書」の検証を行う政策解説。第2回は医療提供体制の検証を行う。
「報告書」は、医療提供体制を本格的に改革するとしている。
しかし、「報告書」が目的にしているのは、あくまで医療費を安く抑えることであり、医療崩壊をくいとめるために医師や看護師を増やすという方針は一言もない。
そして、患者が自由に医療機関を選択できるフリーアクセスが、高い医療費の元凶であるかのように描き、「フリーアクセス」の規制を、改革の目標としている。
改革の欺瞞性を明らかにするとともに、真の課題を提示したい。
「病院完結型医療」が支配的?
「報告書」は「医療・介護分野の改革」の冒頭に、「改革が求められる背景と社会保障制度改革国民会議の使命」を詳述している。
ここでは、現在の医療システムを「主に青壮年期の患者を対象とし」「救命・延命、治療、社会復帰を前提とした『病院完結型医療』」であるとし、「四半世紀以上も改革が求められているのに、なお支配的なままである」と特徴づけている。
だが、このような「病院完結型医療」を、現実に目にすることは現在では少ない。今では、治癒するまで入院できるのはまれで、多くはチューブをつけたままでも、痛みがあっても退院を余儀なくされる。それは国が定めた診療報酬によって、平均在院日数が短縮されるよう、厳しく「コントロール」されているからである。
「報告書」が、このように出発点からずれているのは、医療提供体制の問題は、高齢社会への対応だけだという前提に立っているからにほかならない。
ついで「報告書」は、「地域全体で治し、支える『地域完結型』の医療と介護」を、高齢社会のあるべき姿として位置づけ、「病院完結型」から「地域完結型」病院への転換を課題として設定。これまで第1次医療法改正、第2次医療法改正が行われ、福田・麻生政権下での社会保障国民会議、野田政権時の「社会保障・税一体改革」、第2次安倍政権における「経済財政運営と改革の方針」へと引き継がれてきたことを、「政権の変遷にかかわらず引き継がれ、医療・介護分野の改革の優先課題として位置づけられてきた」として評価するのである。
つまり、「報告書」がめざす方向は新しいものではなく、従前の政府方針を貫徹させようというものにほかならない。
病床削減では解消しない医療崩壊
「報告書」は、「人口当たり病床数は諸外国と比べて多い」ことをあげ、「人員配置は手薄で、過重労働が常態化している」ことを認める一方で、「選択と集中による構造的な改革が必要」としている。つまり、過重労働は病床が多すぎるためで、「地域完結型」に転換し、病床を削減すれば、医師不足は解消するという立場なのである。
しかし、医師の絶対数が人口比で少ないことは、国際比較を見れば明らかである(図1)。OECDデータによれば、人口千対でOECD平均3・15に対して日本は2・21で、データのある26カ国のうち、日本は23位と最低水準である。
医師の偏在がないわけではない。都道府県別の医師数(図2)をみれば、東京など都市部に集中する傾向がみられる。しかし、全都道府県を見回しても、OECD平均値を超える都道府県は1県もない。つまり、医師の絶対数が少ないもとでの偏在が、医療崩壊をいっそう深刻なものにしているのである。
「過重労働の常態化」を認めながら、その解決策を病床削減に求めることは、大病院がカバーする地域を広域化するだけで、対人口比での医師数を増やすことにはならず、過重労働の緩和にはなりようがない。
現にこの間の医療崩壊は、病床が減らされる中で起こっているのである。
90年代以降、病院を急性期と慢性期に区分けし、一般病床を削減し療養病床に転換する施策が進められてきた。1990年に126万床あった一般病床は、2010年に90万床まで減り、替わって療養病床が33万床に増えた(図3)。この「療養病床」は、「報告書」がいうところの「地域完結型」医療の基盤となることが期待された病床だが、人口対比での療養病床率を国際比較すると、実は、韓国と並んで世界一の水準である(図4)。
にもかかわらず、「報告書」がいうところの、「地域完結型」医療・介護が進まないのは、なぜなのか。
医療費削減のために病床を減らすこと、それ自体が目的とされ、地域の「包括ケアシステム」はまともに整備されなかったからである。
それを象徴するのが有床診療所の削減である。有床診療所は、地域医療において小規模入院施設として、きわめて有効である。ところが政府は、まともなシステムを構築する気がないため、有床診療所をきちんと位置付けることなく、診療報酬で冷遇してきた。結果、有床診療所は80年以降減少し、特に90年以降は急速に減少し、90年27・2万床から2010年には13・7万床へと半減した(図5)。
政府は、医療費抑制のために入院日数の短縮化を強引に推し進めてきただけなのである。
急性期を対象とした病院では、入院期間が1週間をすぎると、病院に支払われる医療費(診療報酬)が急激に下げられるため、抜糸前でも、チューブをつけたままでも、食べられなくても、痛みがあっても、患者さんに短期での退院を求めざるを得ないシステムになっている。
その結果、退院時の治癒率は2004年の8・72から2007年には3・65まで、3分の1まで下がっている(図6)。
一方、地域で患者を受け入れる施設は不足し、自宅には戻りようがないため、結局、病院や施設を転々とせざるをえない、いわゆる医療難民が発生している。「報告書」は、患者が「適切な」施設へ移動することを理想としているが、その実体は患者のたらい回しにすぎない。
本来、病院は、一人ひとりの患者に必要な医療は何か、地域にどのような受け皿があるのか、自宅で介護は可能かなど、個別に判断すべきである。政府がすすめるように病院の機能をパターン化し、患者を移動させようというのは、日本の医療現場にはそぐわない。
受け皿づくり失敗の責任を民間医療機関におしつけ
今回の「報告書」の新しさは、提供体制改革の方向性ではなく、それを具体化するための方策を強権的に、かつ「メガデータ」を基に行おうとしていることにある。
「報告書」はまず、これまでも「病院病床数を削減する方向に向かった」が、「適正数まで減らすことはできなかった」とし、その原因は医療機関が「民間資本で経営するという形(私的所有)で整備されてきた」からだとしている。「国や自治体などの公立の医療施設は全体のわずか14%、病床で22%しかない」、だから西欧や北欧のようには改革ができなかったのだと、「改革」が進まなかった責任を、民間医療機関に押し付けている。
しかし、医療・介護体制の整備を民間任せにしてきたのは政府自身である。公立の施設が少ないから改革が進まないというのは、民間医療機関への責任転嫁にほかならない。
今日の医療崩壊の原因は、病床の転換が進んでいないからではなく、病床数が多すぎるためでもない。絶対的なマンパワー不足にある。このことから目をそむける限り、「改革」はニセ改革にならざるをえない。
低医療費政策を徹底追求
今回、「報告書」は、「医療から介護へ」「病院・施設から地域・在宅へ」の流れを「本気で進める」としているが、そのための方策として、二つの転換を示している。
第1は、「データに基づく医療のシステムの制御という可能性を切り開き」、「日本の医療の一番の問題であった、制御機構がないままの医療提供体制という問題の克服に必ずや資する」ということである。
具体的には「病床機能報告制度」と称して、地域医療ビジョンを都道府県が策定し、「データによる制御機構をもって医療ニーズと提供体制のマッチングを図る」としている。どのような病院がどれだけ必要かは、データをもとに行政が決めるというのが、「報告書」の狙いである。
しかし、「本気で進める」と言いながら、報告書があてにしている「地域包括ケアシステムの構築」は、介護保険から介護支援サービスを外し、地域支援事業に移行させるというものだ。
受け皿となる地域包括支援事業の担い手は、介護支援事業者だけでなく、ボランティアを含むもので、主体となる自治体でまともに取り組むところはなく、実施しているのは全国で27市町しかない。政府自身は、相も変わらず机上の空論で「理想像」を描くだけで、実施は自治体任せというのでは、自治体が敬遠するのも無理からぬことである。
医療費、介護費の削減を目的にする限り、必要なマンパワーは最低限に絞られ、人件費も最低限に落とすことにならざるをえない。
そうした中でまともな連携などできるはずもなく、「報告書」が求めるのも、システムというより単なるネットワーク、連絡程度のことにすぎない。まさに羊頭狗肉の政策である。
フリーアクセスの変質
第2は、フリーアクセスに対する規制である。「報告書」は、日本の医療システムがうまくいかないことの理由の一つとして、「いつでも、どこでも、だれでも」医療機関にかかれる、いわゆるフリーアクセスを問題にしている。フリーアクセスに対して「ともすれば、いつでも、好きなところで、と極めて広く解釈されることもあった」とねじまげ、これを「必要な時に必要な医療にアクセスできる」に変えようというのである。
イギリスやカナダなどでは、医療を受けるのに何日も、あるいは月単位で待たされるということも珍しくない。
日本の国民皆保険がすばらしいと言われるのは、このフリーアクセスのおかげである。フリーアクセスがあるからこそ、早期受診が可能になり、疾病の重篤化が抑えられ、結果として医療費も少なくすんでいる。
「必要な時に必要な医療」とは、患者以外の誰かが、「必要」かを判断するということである。誰かが「必要」として認めるときだけ、受診できるようにしようというのは、国民皆保険を大きく後退させるものである。
開業医のあり方を歪める「ゲートキーパー」
この「フリーアクセス」制限のために、「報告書」が持ち出しているのが、「ゲートキーパーとしてのかかりつけ医の普及」である。
「総合診療医」など、これまでに何度も持ち出されてきた議論だが、今回の特徴は「国が保有するレセプト等データの利活用」をあげていることである。ゲートキーパーに患者さんを振り分けさせる際に、その基準にメガデータを使おうというのである。
データを使っての振り分けと言えば聞こえはよいが、実体は、開業医が自らの臨床経験から主体的に判断するのではなく、データによる一律的振り分けを強制しようというものである。これは本来のかかりつけ医としての役割を歪めて、医療現場での医師の裁量権を制限することにつながりかねない。
紹介状なしの病院受診に1万円
「報告書」は、紹介状のない病院外来受診についても、患者負担とする方向だ。報道では、200床以上の病院で1万円の負担とされている。しかし「200床」規模は、公立病院だけでなく民間の中規模病院も含まれる。そうした病院は当然、外来機能として、地域の患者の初診の受け皿としての機能を併せ持つ。中小病院から外来機能を奪うのは、地域医療を混乱させるだけである。
そもそも、大病院に患者が集中するのは、高い患者負担で受診抑制を招いていることが背景にある。早期受診が抑制されると、病気が悪化してから受診することになり、そうした患者さんがより機能の高い病院を志向するのは当然の傾向である。
しかも公立病院の統廃合が進められた結果、より少ない公立病院がより広い範囲をカバーするようになっており、ますます患者さんが集中する。こうした背景を抜きに、病院の外来受診を患者の選好の問題であるかのように扱うのは、問題のすりかえである。
必要なことは地域医療システムがきちんと機能して、開業医が患者の身近な存在として機能し、開業医を通じた病院選択がもっとも合理的であるようにしていくことである。そのためには、窓口負担を大幅に削減し、早期受診を促進する政策こそ必要である。過大な窓口負担金を課すことで受診の流れをコントロールしようというのは、真に効率的な医療提供体制とは真逆の政策だ。
国民のための医療提供体制とは、結局のところ、早期発見早期治療なのである。
高齢社会に対して、医師や歯科医師、看護師らに過重労働を課しつつ、安上がりの医療の継続をめざすこと、これが「報告書」の基本スタンスである。
このような「報告書」にまどわされず、地域医療の現実から出発して、医療従事者を大切にする社会こそ求められている。