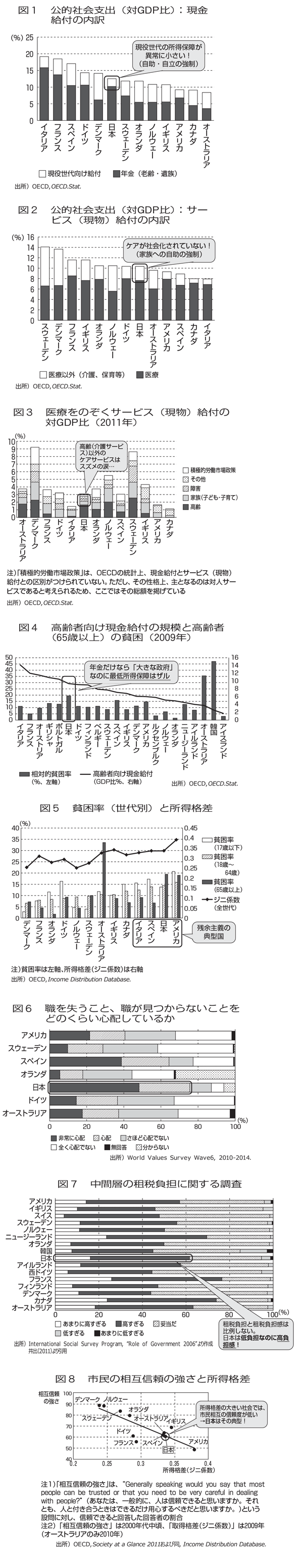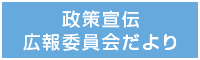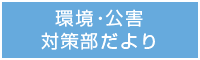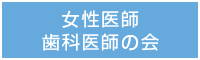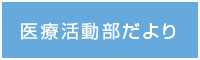政策宣伝広報委員会だより
第90回評議員会特別講演・講演録 患者負担増で国民も経済も疲弊
2017.01.05

埼玉大学人文社会科学研究科
高端正幸准教授
【たかはし まさゆき】1974年生。2002年東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。東京市政調査会(現後藤・安田記念東京都市研究所)研究員などを経て、現在、埼玉大学准教授。主な著書に『希望の構想』(共著、岩波書店、2006年)、『公私分担と公共政策』(共著、日本経済評論社、2008年)など
自己負担引き上げはやむを得ないのか
医師・歯科医師である皆さんにとって、患者負担増で国民が疲弊するのは、現場で日々感じておられることだと思う。しかし、それだけでなく患者負担増が財政も疲弊させるということを財政学的な観点からお話ししたい。政府や財務省によりこの間、社会保障や医療政策が大きく変化している。高齢化で医療費が増えているとして、政府は税や社会保険料を増やすだけでなく、医療を受ける人、つまり患者の自己負担を増やしている。そして、国民の間でも、それは必要、もしくはやむを得ないという考え方が支配的だ。この政策は財源を自己負担に求めるという点以外にも、患者のコスト意識を高めて、いわゆる「コンビニ受診」などといわれる受診を減らし、医療資源を効率的に使うという狙いもあるとされる。
しかし、患者負担を増やすと格差や貧困の拡大に拍車がかかる。必要な医療が受けられなくなるという懸念もある。これに対し、患者負担増を正当化する人たちは「低所得者には負担軽減を行い、そうでない普通の所得の人の負担を上げれば問題ない。生活保護の受給者にはそもそも医療費窓口負担がない」と言う。
しかし、このように、持てる者に負担をさせ、低所得者だけ負担軽減を行えばよいという議論は間違っている。このことは近年の財政学分野の研究、特に綿密な国際比較により明らかになっている。
残余主義の日本普遍主義の北欧
さて、日本社会の現状をみてみよう。この間、世帯所得が100万円も落ちている。貧困率も高まっている。しかも、失業や親の介護などちょっとしたリスクで貧困状態に陥ってしまう人が増えている。こうした状況を何とかしなければならない。一方で、日本は深刻な財政赤字を抱え、「ない袖は振れない」と言われる。いわば、日本は社会の危機と財政の危機の二重の危機に瀕している。
ここから、「社会保障を充実すべきか、財政再建を進めるべきか」という二者択一の選択を迫られてしまっているように感じる。しかし、そうではない。どちらも解決できるし、どちらかだけを解決することは困難なのだ。
そこで大切なのが「普遍主義」というキーワードだ。普遍主義に基づく政策に転換すれば、社会の危機も財政の危機も同時に克服できる。そこから患者負担増が愚策であることが明らかになる。
では「普遍主義」とはなんだろう。まずは「普遍主義」の対概念である「残余主義」について考えてみよう。というのも日本は「残余主義」だからだ。
一言でいえば、残余主義は、自助、自立、自己責任を重視する考え方だ。私たちが生きる市場経済の下で、人間というのは普通は自立する、普通の人は家族の助け合いと自分の稼ぎで生活できるという考えだ。そうなると自助、自立できない人だけを救済するということになる。日本が典型的な例である。こうした国は財政的には、税や社会保険料負担の低い「小さな政府」となる。
この逆の考え方が普遍主義だ。市場経済の下で、人間は自助、自立できるわけではないと考える。普通の人はさまざまなリスクにさらされて生きているという考え方だ。そこから、幅広い人々のニーズに着目して、困窮した人だけでなくあまねく人々に給付を行うことになる。この典型が北欧諸国だ。これらの国々は財政的には「大きな政府」となる。
自立・自助を強いる日本の社会保障制度
では、日本の社会保障について少しくわしくみてみよう。図1は、公的社会支出のうち現金給付の大きさを比較したものだ。医療は現物給付なので含まれない。ここに含まれているのは、年金や児童手当、雇用保険給付などだ。これをみると日本は真ん中くらいになる。しかし、その内訳を見ると大部分が年金で、それ以外はアメリカと同じくらい少なく、これら主要先進国の中で最低である。
次に現物給付をみてみよう(図2)。こちらも日本は真ん中くらいである。医療は各国と比較しても大きめになっているが、これは高齢化の影響である。医療以外の部分も各国と比べてやや少ない程度である。
しかしこの中身をみてみると、高齢者向けである介護サービス以外はすずめの涙である(図3)。介護もまだまだ不十分だが、その他の給付は他国に比べて非常に少ない。その他の給付とは、子育てや障害者向け給付、積極的労働市場政策だ。積極的労働市場政策というのは、失業給付ではなく、職業訓練や長期にわたる失業でメンタルに障害を抱える人へのケアやカウンセリングなどのことである。
ここから分かるのは現金給付であれ現物給付であれ、現役世代が受益者となるサービスが非常に手薄であるということである。これをもって、「高齢者には手厚く、若者には厳しい」と世代間対立を描くような風潮もある。
しかし、高齢になり定年を迎えると所得が少なくなるので年金制度はそれなりに整備されているだけであり、日本の社会保障制度が、高齢者も含め国民に自助・自立を強いるものであることから来ているものだ。そうした社会保障政策を世代別にみると給付に偏りが出るだけである。
というのも、高齢者や困窮した人の救済に熱心なのかといえばそうでもない。自助・自立を高齢者や困窮者にまで貫徹させているのが日本の特徴だ。
図4を見ると分かるように、年金の給付規模は「大きな政府」並みだが、高齢者の貧困率は非常に高く、年金の最低所得保障機能は「ザル」ということが分かる。長らく生活保護受給者の半数以上が高齢者であるということもうなずける。だから、日本の社会保障制度が高齢者に手厚いなどというのは誤解である。
では、どういう経緯でこうなってしまったのか。
戦後の日本の財政について、慶應義塾大学の井手英策教授は「土建国家」財政とネーミングしている。
高度経済成長期に政府の税収が増えていく。増えた税収をどういう形で国民に還元したのか、日本では主に所得税の減税を行い、国民の手元にお金を残した。ヨーロッパの「大きな政府」の国々はそれを社会保障の充実で国民に還元した。これが大きな違いだ。
また、60年代後半からは地方で公共事業を行うことによって、農業収入が減少しつつあった農家に兼業化を促し、農村の家計を支えた。
これらは、減税や公共事業により自立・自助的な所得確保を促すものであった。しかし、高度経済成長という条件がなくなると、結果として残余主義的な自助・自立、自己責任性だけが日本社会に残されたのだ。
弱者を生まない普遍主義へ転換を
こうして日本は、誰もが生活の困難に簡単に直面しうる社会になった。だから、生活が困窮してから支えるという発想ではなく、困窮しないようにリスクから解放するという発想に転換しないといけない。日本やアングロサクソンのように、自己責任を強調し、低所得になってしまった人だけを選び出して救済しようとするのではなく、低所得になる前に、疾病や要介護、障害、失業というリスクを社会でシェアするのが普遍主義の考え方だ。
日本の生活保護の捕足率は15%程度だ。捕足率というのは、本来生活保護を受けるべき所得水準の人のうち生活保護を受けている人の割合だ。スウェーデンの捕足率は82%だが、受給者は多くない。それは、生活保護を受給しなければならなくなる前に、さまざまな社会保障サービスがあるからだ。
図5をみると日本やアメリカなどは所得格差も大きく、各世代の貧困率も高い。これらの国々は典型的な残余主義の国だ。こうした国の人々は、職を失うこと、職が見つからないことを非常に心配している(図6)。残余主義は生活だけでなく心理面でも人々を追いつめていることが分かる。
やはり日本も残余主義から普遍主義に転換しなければいけない。「弱者を救え」ではなく、「弱者を生まない」ということが普遍主義のメッセージだ。
普遍主義の国は財政赤字が小さい
日本の財政は厳しく、普遍主義をとるのは無理ではないかという人もいる。しかし、実は、残余主義の国は共通して財政赤字が大きい。逆に北欧のように普遍主義をとり、幅広く人々のニーズを満たしている国は大きな政府だが、なぜか財政赤字は小さい。その理由が、ここ10年で綿密な国際比較ができるようになって明らかになってきた。図7は中間層の租税負担に関する調査だが、日本では租税負担が「あまりに高すぎる」「高すぎる」と答える中間層の割合が6割程度いる。
しかし実際の負担を比較してみると、日本は韓国やアメリカよりも少し大きいくらいで、負担の重さは最低レベルである。ノルウェーやデンマークは日本の倍くらい負担しているが、そういった人たちでも日本と同じくらいしか税金を高いと感じていない。
これはどういうことなのだろう。近年の研究で、ここに残余主義と普遍主義が関係していることが明らかになった。
残余主義で給付を限定している財政では、一般の人は税を支払っても、それによって自分の生活が支えられているという実感が弱い。これは当然不満につながる。だから、社会保障の給付を受けている低所得者への視線が厳しくなる。
一般の人たちは「自分が支払った税金はどこにいった」と感じ、生活保護受給者や失業者などに使われていると考える。だからそういう人々に対して厳しくなる。そして、「なぜヤツらのために税金を払わないといけないのか」となり、低所得者とそうでない人の亀裂が社会に生まれる。
実際に図8で分かるように所得格差が大きな国ほど、他人を信じられない。格差の大きな国では、アメリカが典型だが、裕福かそうでないかで、住むことのできる場所も、行ける学校も、人生で得る経験も、使う言葉すら違う。だから見知らぬ他人を信頼できなくなり、「自分とは違う人間だ」と考える。しかし、平等であれば、だいたい自分と同じような経験をして、同じような常識感覚があり、話も通じるだろうと思う。結果として、他人を自分と同じような人だと思い、信頼ができる。
つまり支出を減らすために自助・自立を強調すればするほど、社会に亀裂ができ、中間層は負担を拒否することになる。そして結果として財源が不足する。
逆に幅広く人々のニーズをカバーする普遍主義であれば、格差は縮小し、人々の間に連帯・共感が生まれる。そして、受益感を得られている中間層の税負担への同意も得られやすくなる。だから大きな政府であっても財源が不足することなく、財政赤字にならないのだ。
これが近年注目されている財政学分野での成果だ。「財政健全化」と言って、自己負担を増やしても財政赤字は解消しない。
自己負担増はモラルハザード招く
日本では、自助・自立の強要により、財政も社会もズタズタになっている。いわば誰も助け合いに参加しないという状況にある。さらに、高齢者と現役世代、福祉を利用する人と自立する人、都市と農村など様々な形の対立を90年代以降、政治が利用してきた。こうした対立を利用して、地方交付税を削減したり、社会保障の自己負担を増やしたり、給付削減を行ってきた。こうした対立を煽る意見に説得され、他者を信じず、他者を叩くことで自分を守るという社会状況が深まっている。非常に危機的な状況である。
医療はさまざまな社会保障の中で、すべての人に必要なサービスだ。だれでも必要になるし、最も大切な命を守るサービスだ。だから自己責任を強調し、自己負担で買わせるのではなく、普遍主義的に誰にでも給付をしなければならない。
現在、日本の医療制度はそれほど優秀とはいえないが、一応自己負担を抑えながら、医療提供体制が整えられている。OECD諸国と比較しても、患者負担は高くない。この制度を壊してしまってもいいのかということだ。
政府は医療費窓口負担引き上げの理由について、「負担できる人に負担してもらうことが公平だ」という。それこそが財政学的に最も言ってはいけないことだ。持てる者と持たざる者を差別すれば、不信感が拡大する。その結果、人々が社会的な連帯に参加しなくなり、税や保険料の負担に抵抗するようになってしまう。結果、財政が破たんする。このことに財務省は気付いていない。
医療費窓口負担を引き下げると過剰受診、モラルハザードが起きるという。自己負担を引き上げることで、患者にコスト意識を持たせ過剰な受診を控えさせる必要があるという。
しかし、これは小手先のテクニックだ。こうしたことを行えば医療は「お金を出して買うべきもの」となり、むしろ患者のモラルは低下する。
アメリカで行われた有名な社会実験を紹介したい。この社会実験は保育について行われたものだが、医療にも適用できると思われる。アメリカのとある町の保育所では、預けた子どもを午後5時までに迎えにこなければならなかった。しかし、時間までになかなか迎えにこられない親もいる。それを減らすために午後5時以降に迎えに来た場合には、いくらかの自己負担を徴収することにした。それで午後5時以降に迎えに来る親は減っただろうか。結果は全く逆だった。親たちが、お金を払えば遅くなっても構わないと思うようになったからだ。
この社会実験には続きがある。その後、再び自己負担を廃止したが、午後5時以降に迎えにくる親は以前の水準に減らなかったのである。
一度低下したモラルを再び取り戻すのは難しい。だから、医療の自己負担は引き上げるべきではないのだ。しかし、すでに日本でも医療費窓口負担は引き上げられ続け、医療がお金で買うサービスになりつつある。再び窓口負担を引き下げてもモラルは戻らないかもしれない。しかし、だからこそこれ以上、患者負担を引き上げてはならないのである。